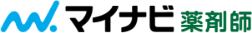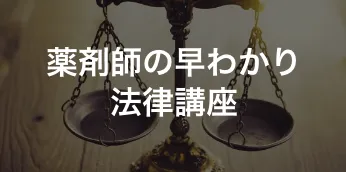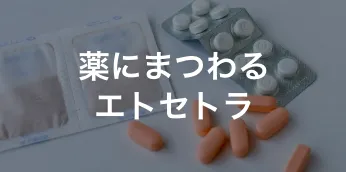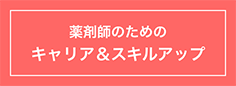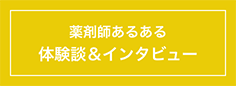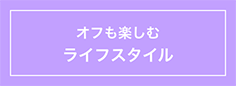学べば学ぶほど、奥が深い薬の世界。もと製薬企業研究員のサイエンスライター・佐藤健太郎氏が、そんな「薬」についてのあらゆる雑学を綴るコラムです。薬のトリビアなどを伝えられると、患者さんとの距離も近くなるかもしれませんね。
覚せい剤など、薬物乱用の話題がよくマスコミを賑わせています。中でも最近大きな問題になっているのは、いわゆる危険ドラッグと呼ばれるものでしょう。店舗で販売されても法的に取り締まりがしにくく、誰でも簡単に入手できてしまうため、大きな社会問題となっています。
薬剤師のみなさんならご存知の方も多いとは思いますが、簡単に現状をおさらいしておきましょう。日本で、「合法ハーブ」などと称したドラッグが問題になり始めたのは、2009年ごろからのことです。法的にも問題なく、手軽に陶酔感を味わえる「軽い薬物」という印象を与えるためか、その販売はあっという間に拡大してゆきました。ネットや店頭での販売はもちろん、自動販売機で堂々と販売されていたケースすらあったようです。
しかし実際には、その有効成分は植物由来成分などではなく、多くの場合人工的に合成された「合成ドラッグ」でした。これらを草にまぶしたり、芳香剤などのように製品化したりなどしたものが、堂々と販売されていたのです。
2012年ごろからは、これら薬物の服用者が死亡したり、交通事故を引き起こしたりなどのケースが相次いで発生し、社会問題化し始めました。このため名称も「合法ハーブ」ではなく「脱法ハーブ」へ、さらに2014年7月からは危険性をアピールするため「危険ドラッグ」と名称が変わり、現在に至っています。その実体はハーブなどではありませんから、ネーミングセンスはともかく、「ドラッグ」への名称変更は妥当というべきでしょう。
実際、その危険性は、すでに法規制を受けている麻薬・覚せい剤と変わりない――というより、ある面ではずっとたちが悪い薬物だともいえます。たとえば、ある種の危険ドラッグでは、服用後に体が硬直して動かなくなるなどの作用があります。車の運転中にこうした作用が出ると、ハンドルを切ることもブレーキを踏むこともできなくなります。これが、危険ドラッグ服用者の事故が相次ぎ、しかも事故の規模が大きい一因となっています。
危険ドラッグによって幻覚・幻聴・疲労感などの作用が出ることはもちろんですが、場合によっては脳に不可逆な損傷をもたらし、知能障害や麻痺などの後遺症が残ることも多いようです。最悪の場合、死に至ることもあるわけですから、そのリスクは一時の快楽にはまったく見合いません。

警察としても次々に法規制を厳しくし、取り締まりを図ってはいますが、なかなか撲滅には至っていません。法をすり抜ける新たなドラッグが、次々に出現するからです。なぜこうなるのかといえば、危険ドラッグは脳科学研究や製薬企業による新薬研究がもとになっているからです。
脳内では、ホルモンなど各種の脳内物質が分泌され、受容体に結合することで作用を現します。モルヒネやマリファナなどの麻薬類は、これら脳内物質の代わりに受容体に結合して「脳をだます」ことで、陶酔感や幻覚などの作用をもたらします。こうした物質の構造を一部変換し、都合のよい作用だけを残せれば、優れた鎮痛剤や睡眠薬などを創り出し得ます。
こうした合成ドラッグの歴史は、C. R. A. ライトという研究者による、1874年の実験に始まります。彼は、鎮痛剤モルヒネを無水酢酸で処理し、アセチル基という原子団を取りつけてみたのです。1898年この化合物は、モルヒネのような習慣性がない優れた薬、という売り文句のもと、咳止め薬としてドイツのバイエル社から発売されます。しかしこの薬は、モルヒネを遥かに上回る快感と習慣性を備えていました。これこそが、ヘロインに他なりません。
このように、当初はよかれと思って合成した化合物が、実は強い麻薬作用を持っていたという例は少なくありません。当然、これらは法令によって禁止されますが、闇でこれらを合成して流す者が現れ、違法薬物として流通しているのが現状です。
これらは、日本では覚せい剤取締法などの法律によって規制されています。これらは基本的に、特定の構造式を持つ薬物を対象にして、その製造や所持を禁じるという体系になっています。現在出回っている危険ドラッグは、この法律の穴を突いたものですが、その詳細については次回以降で述べていくこととしましょう。