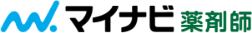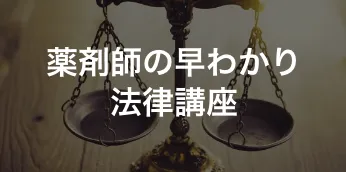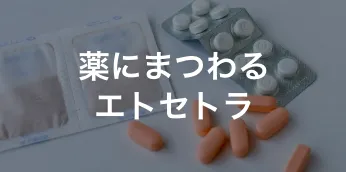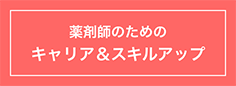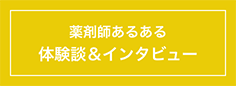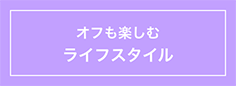学べば学ぶほど、奥が深い薬の世界。もと製薬企業研究員のサイエンスライター・佐藤健太郎氏が、そんな「薬」についてのあらゆる雑学を綴るコラムです。薬のトリビアなどを伝えられると、患者さんとの距離も近くなるかもしれませんね。
しばらく前、製薬業界では「2010年問題」ということがしきりにいわれていました。2010年前後に、それまで各社のドル箱であった多くの医薬の特許が切れ、製薬企業の収益が一挙に落ち込むと懸念された問題を指します。
医薬品の特許は、最長25年で切れます。その期間を過ぎるとジェネリックメーカーが同じ成分の薬を発売できるので、先発品の売り上げは激減します。これがいわゆる「パテントクリフ」(特許の崖)と呼ばれるもので、特に世界最大の市場である米国では、この傾向が顕著です。先発品メーカーがこれをしのぐには、特許切れの前にそれに代わる新薬を次々と創り出すほかはありません。
1990年代から2000年代にかけて、増大する新薬の開発費をまかなうため、製薬企業各社は互いに合併を繰り返しました。こうして巨大化した会社が利益を出すためには、大型新薬創出を狙うほかありません。しかし、すでに感染症や高血圧などの治療薬には完成度の高い薬が出揃い、それらを超える新薬開発は難しい状態でした。大型新薬の生まれやすい糖尿病や消炎鎮痛剤などの領域では副作用問題が発生し、臨床試験が厳格化しました。
これらの要因が重なり、21世紀に入ってから新薬の創出はぐっと減少しました。米国食品医薬局(FDA)は、1996年には53点の新薬を承認しましたが、2005~2010年ごろには年20点を切るまでに落ち込んでいます。この傾向は、米国だけでなく世界各国で共通でした。
つまり2010年問題とは、特許が切れることが問題ではなく、新薬が生まれにくくなったことこそがその本質です。この問題に関しては、拙著『医薬品クライシス』(新潮新書)でも詳しく論じましたので、興味のある方はご覧ください。
それから5年を経た現在、製薬業界はどうなっているでしょうか。結論からいえば、欧米大手の多くはうまく危機を脱したといえます。その切り札となったのは、バイオテクノロジーを利用して製造する「バイオ医薬」、中でも「抗体医薬」と呼ばれる新しいジャンルの薬です。
抗体は、人体に入り込んできた細菌やウイルスなどの作るタンパク質に反応して、これに結合してしまうタンパク質であり、免疫作用の重要な一環を担っています。抗体医薬は病気の原因となる、体内のタンパク質に結合する抗体を遺伝子工学的手法によって作り出し、治療に用いようというものです。

抗体医薬が登場したのは1990年代後半のことで、乳がん治療薬ハーセプチン、リウマチ治療薬レミケードなどがその嚆矢でした。その後、がんやリウマチなどを中心に各種の抗体医薬が登場し、これらの領域の医療を大きく変えつつあります。抗体医薬は大いに売り上げを伸ばし、すでに世界の医薬品販売額トップ10のうち7つまでを抗体医薬をはじめとするバイオ医薬が占めるようになっています。
今までの創薬は、細菌を培養して薬理作用のある化合物を抽出する「発酵法」や、フラスコ内での化学合成による「合成法」が主流でした。しかし抗体医薬は、バイオテクノロジーを基盤としており、研究方法も生産過程もまったく異なります。このため、抗体医薬創出には、一から技術を学び、取り入れる必要があります。
しかし日本の大手製薬企業の多くはこの流れに乗り遅れ、自前で抗体医薬を創出できずにいます。現状で国産の抗体医薬は、中外製薬のアクテムラ(リウマチなどの治療薬)、協和発酵キリンのポテリジオ(成人T細胞白血病リンパ腫治療薬)、小野薬品のオプジーボ(悪性黒色腫治療薬)など、わずか数点に過ぎません。
そこで国内大手製薬企業は、海外バイオベンチャー企業の有力な新薬候補を買い取って臨床試験を行う、あるいはベンチャーごと買収して抗体技術を取り入れる方向に進んでいます。ただし、優れた技術を持った企業は争奪戦となっており、買収額も非常に高価になっているため、費用対効果が疑問視されるケースも出ています。
ただ、抗体医薬はその性質上、細胞に入っていくことができないため、対象疾患は限定されています。がんや免疫関連疾患、一部の感染症などを除いた病気の治療薬は、今も発酵法や合成法によらねばなりません。しかし近年、製薬企業の発酵・合成部門の縮小が進んでおり、ベンチャーや大学への依存度がますます高まっているのが現状です。
大企業からはイノベーションが生まれにくいのはあらゆる分野でいわれることであり、こうした変革期にはベンチャーが活躍するのは必然なのかもしれません。しかし、製薬企業が自前の研究能力を自ら削ってしまうのが正しいことなのか、疑問は拭えません。それが是か非か、その答えはこれから10年、20年先に明らかになることでしょう。