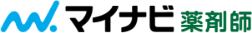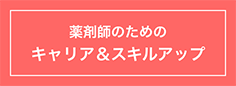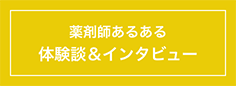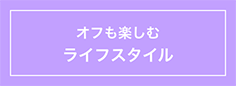タバサは医師免許を持ち、町に病人が出るとその「気配」を察知して、その場所へ出向いていったり、町の人たちの出生証明書や死亡診断書のほとんどを書いたりと、一般的な薬剤師とはかなり違います。
主人公・由美との生活では、答える必要のない質問には一切答えないのですが、薬局を継ぐことを余儀なくされた運命や、自宅の庭で母親が命を断った悲しい過去、自分の名前の由来といった個人的なことを打ち明けることもあります。
タバサの薬局のある町では、人が亡くなっても葬式をしない、他人にはあまり干渉しないといった独特な習慣やルールが存在します。タバサの調剤する薬について意味ありげなことを言う自転車屋の店主や、タバサの薬を飲んで亡くなっていく人、「機嫌の悪い妖精のような」老女と、その老女を町から追いだそうとする若い母親など、町の人たちの言動に主人公は翻弄されます。

不思議な世界観の中で物語が進行する一方で、タバサが薬局を営む一人の薬剤師として、リアルな描写も登場します。例えば営業時間中にタバサと由美が一緒に外出するため、薬局を無人にしなければならなくなったとき。「シャッターは閉めずに、自動ドアだけ開かないようにして、張り紙をしておきましょう」と言い、使い込んで黄ばんだ「すぐに戻ります」と書かれた紙をドアに掲げるシーンは、個人経営の小さな薬局なら実際にありそうな話。また、タバサが薬を乳鉢ですりつぶし薬包紙で包むシーンでは、一つひとつの動きが細やかに描写されており、その光景が目に浮かびます。
夢の中のような世界と、現実的で人間臭い描写が入り混じった独特の世界は、読んでいるとどんどんひき込まれる魅力があります。
不思議な町の話とはいえ、薬剤師であるタバサが町の人たちから頼りにされ、タバサや先代である父親が長年にわたって住人たちを支えているといった点は、現実世界の薬局と同じです。町で唯一の薬局が地域を支える姿は、地方都市での薬局のあり方にも通じるといえるかもしれません。