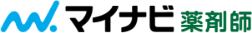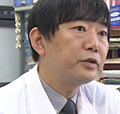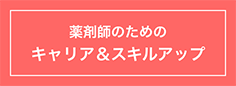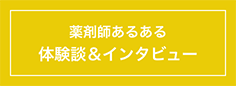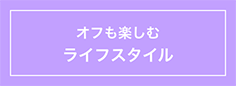映画・ドラマ

「たまには仕事に関連する映画を見てみようかな」と感じたことはありませんか? 医療や病気に関する映画・ドラマ作品は数多くありますが、いざとなるとどんな作品を見ればいいのか、迷ってしまう人もいるのでは。このコラムでは北品川藤クリニック院長・石原藤樹先生と看護師ライターの坂口千絵さんが、「医療者」としての目線で映画・ドラマをご紹介します。

vol.35「白い巨塔」(1966年・日本)
東教授の定年を控え、その後任教授の地位をめぐって揺れる大阪・浪速大学医学部第一外科。若きエリート助教授・財前五郎が有力視されていたが、野心家で傲慢な財前を人間的に嫌う東教授が対立候補を擁立。教授選挙へ向け熾烈な裏工作合戦が始まる。そんな折、財前は、同期の里見助教授から依頼された患者を医療ミスにより死亡させてしまう。財前は教授の座を手に入れたものの誤診で訴えられてしまい――。山崎豊子による同名の長編小説を、田宮二郎主演で巨匠・山本薩夫が映画化。今なお色あせない、日本映画史に燦然と輝く社会派映画の金字塔。

―大学病院の腐敗を描いた社会派医療ドラマの金字塔―
今日ご紹介するのは、1966年公開の日本映画「白い巨塔」です。公開当時から大評判になり興行的に成功するとともに、キネマ旬報の邦画ベスト1など、作品としての評価も高い、社会派医療ドラマの代表作です。この作品以降、多くの医療を扱ったドラマや映画が生まれましたが、大学病院の教授選や医療過誤の裁判を扱った日本映画としては、いまだにこの作品を超えるものはないと思います。
原作は山崎豊子のベストセラー小説で、すぐに続編も書かれましたが、映画はその正編のみを元にして、ほぼ原作通りに映像化しています。
主人公の財前五郎(田宮二郎)は、関西の帝大、浪花大学医学部附属病院第一外科の若き助教授で、食道がんの再建手術においては、他の追随を許さない外科手術の名手です。同教室の東教授(東野英治郎)は、関東の帝大東都大学の出身で、学究肌の名医ですが、手術の腕だけで成り上がった財前のことを嫌っています。財前は貧しい農家の出身で、金もうけ主義の産婦人科開業医の養子に入ったという経緯があるので、家柄の良いエリートを自負する東教授には、その存在自体が許せないのです。
東教授には退官が迫り、その実績や助教授という立場から言って、財前が次期教授になることは当然と、本人はもとより周囲の誰もが思っています。しかし、東教授がひそかに、母校の教授で医学界のドンの一人である船尾教授(滝沢修)と図って、対抗馬を擁立したことから、仁義なき教授選が幕を開けることになります。
財前側、東側で様々な策をめぐらし、スリリングな選挙戦が行われます。その一方で、自分の医療手腕には絶対の自信を持つ財前に、手術は完璧であったにも関わらず、術後に容態が悪化して患者が死亡するという事態が起こります。実は、胃がん術前に肺転移の見落としがあったのです。
大学病院の教授選が、患者のための医療を無視して行われていることを、教授選と患者の容態急変を並行して描くことで、自然に観客に感じさせるという構成が極めて巧みです。選挙戦の攻防は、思いがけない伏兵が現れたりと、意外性に富んでおもしろく、ひと癖もふた癖もあるキャラクターが次々と登場して飽きさせません。
原作自体が起伏に富み、キャラクターの立ったとてもおもしろいものですが、名脚本家として知られる橋本忍の脚本は、長大な原作を巧みに整理して、短いやり取りでそのキャラクターを印象づける手法が鮮やかです。演出に当たった山本薩夫監督は、骨太の社会派作品を得意とする大家ですが、特に山崎豊子作品の映画化とは相性が良く、この『白い巨塔』を皮切りにして、『華麗なる一族』、『不毛地帯』とヒット作を連発することになります。
キャストは何と言っても主役を演じた田宮二郎が当たり役で、その後テレビドラマでも同役を演じました。ドラマでは続編の内容も描かれ、財前の死までを演じきっています。抜群に恰好良くて、悪党であるのに魅力的という、こうした役柄は後にも先にも田宮二郎ならではという気がします。脇役陣は俳優座の東野英次郎と小沢栄太郎、劇団民藝の滝沢修、文学座の加藤武と、当時の新劇を代表する演技派が固めています。財前の愛人を演じた小川真由美の妖艶さを含めて、その演技のぶつかり合いが映画としての最大の魅力です。
医療者の立場から見ると、前半の教授選の描写にしても、後半の医療裁判のやり取りにしても、1960年代当時の医学界の雰囲気と、医療が一般の人にどのように捉えられていたのかが、かなりリアルに写し取られていると思います。1980年代頃の教授選については、私自身もその内実を少し見聞きしていますが、映画に描かれている内容と、そう大きな違いはなかったように思います。ただ、学者の集団ですから、札束が乱れ飛んだり、ポストをちらつかせて篭絡したり…というようなところまでは、なかったのではないかと推察しています。
医療裁判についての描写は、当時の最新の知見が取り入れられていて、かなり高レベルの論争である点が感心させられます。通常の胃のレントゲン検査や胃カメラで診断の付かなかった胃がんを、財前は患者にバリウムを飲ませてその動きを注視し、健康保険で認められている2枚のレントゲン写真を撮影するだけで診断します。
しかし、早期がんのため転移はないという先入観から、実際には肺転移であった胸部レントゲンの陰影を、陳旧性結核と断定して手術を行ってしまうのです。その後がん性胸膜炎を併発して、患者は急変するのですが、教授選のことで頭がいっぱいの財前は、自身では一度も患者を診察することはなく、そのために決定的に患者家族との関係が決裂してしまいます。
今の感覚では、「なぜCTを撮らなかったのか」と不思議に感じるところですが、CTが日本の医療現場に導入されたのは1975年以降のこと。映画の舞台となった1960年代には、胃カメラの導入は始まっていたものの、CTはまだなかったのです。この辺りの事情を理解していると、より深くこの映画を鑑賞することができると思います。
医療はこの映画の舞台となった1960年代から、間違いなく大きな進歩を遂げましたが、患者の気持ちを置き去りにしたような医療は、当時よりむしろ今の方が顕在化しているように思います。医師の序列や権力抗争についても、当時とは形を変えながら、存在し続けているようです。その意味で1960年代に山崎豊子が糾弾した「白い巨塔」は、まだ現実であるのかも知れません。
善悪がはっきりし過ぎていて台詞が時に説教臭い点など、いま観ると古めかしい感じも否めませんが、今なお医療ドラマの最高峰であることは間違いありません。薬剤師の立場からも参考になることが多いと思います。なにより、日本映画を代表する傑作ですので、未見の方はぜひご覧になってみてください。
あわせて読みたい記事