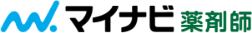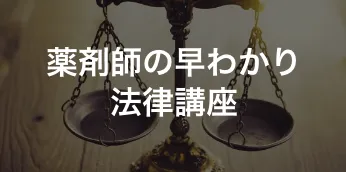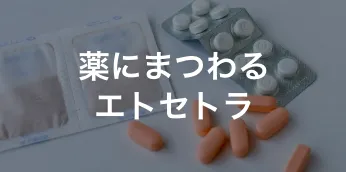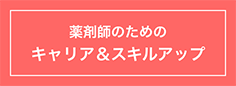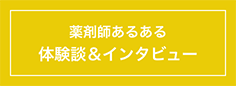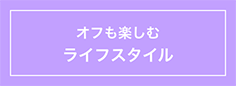学べば学ぶほど、奥が深い薬の世界。もと製薬企業研究員のサイエンスライター・佐藤健太郎氏が、そんな「薬」についてのあらゆる雑学を綴るコラムです。

薬はなぜ苦いのか?
「良薬は口に苦し」ということわざに代表されるように、効果のある薬ほど苦くて飲みにくいといわれます。実体験としても薬の味を「おいしくてじっくり味わいたい」と感じたことなど一度もない方が大多数ではないでしょうか? なぜ薬は苦く飲みにくいのか―—今回は薬の「味」について考察します。

子どもは苦さに敏感
筆者は5歳の娘を持つ身ですので、小さな子どもに薬を飲ませる大変さをよく実感します。できる限り水や白湯で飲むのがよいのは確かですが、それではなかなか飲んでくれません。ミルクやアイスクリームに混ぜたり、市販の服薬用ゼリーなどを用いたりするなどの手段もありますが、それでも飲んでくれず頭を抱えることもしばしばです。
糖衣錠やチュアブル錠といった、飲みやすく工夫した製品もありますが、小さい子には効果がないことも少なくありません。コーティングや甘味料なども進歩しているのだから、もう少し美味しくできないものかと思ったりもしますが、あまりに美味しすぎて子供がたくさん飲みたがるようになってもそれはそれでまずいのかもしれません。
小さな子どもが薬の苦さに敏感なのは、単純に舌の味蕾の数が多いからです。味覚のセンサーである味蕾は、大人になるにつれて数が減り、40代になると子供の頃の3分の1ほどになってしまいます。小さな子が薬を耐え難いほど苦く感じるのも、やむを得ないところでしょう。
もちろん、大人にとっても薬の味は快いものではありません。マクロライド系抗生物質など、味の悪い医薬は多く、服薬コンプライアンス低下の原因ともなっています。「良薬は口に苦し」とは孔子の言葉だそうですが、これは2500年後の今でも変わっていません。
現代の技術で、薬自体の味ももう少し改善できないのかと言われることもありますが、これはちょっと難しい注文です。医薬研究者としては、十分な薬効と安全性を確保するだけで精一杯で、薬の味まではとうてい手が回りません。
そもそも、医薬品の候補となる化合物は思わぬ生理作用を持つ可能性も高く、ひとつひとつ味を確かめることなどできようはずもありません(ちなみに、今ではとうてい考えられませんが、19世紀の化学論文誌には化合物のデータとして、融点や色の他に「味」という欄もありました。おそらく、化学者の健康にも少なからず悪影響があったでしょう)。

薬はなぜ苦い?
それにしても、なぜ薬はみな揃いも揃ってまずいのか?原因は、人類の進化の過程に求められそうです。
味覚は、食べ物が体に必要なものかどうかを判定するセンサーとして発達したと考えられます。たとえば、ブドウ糖や砂糖のように水酸基(-OH)をたくさん持った化合物は、甘みを感じさせます。こうした構造は酸化分解を受け付けやすく、体内ですぐに燃えてエネルギーになるのです。すなわち甘みというのは、エネルギー源として重要な化合物を舌が判別し、快い味としてたくさん取り入れようとする仕掛けなのです。
同様に塩味なども、体のイオンバランスをとるために必要なナトリウムイオンを摂取するためのセンサーと考えられます。またグルタミン酸ナトリウムにうま味を感じるのは、生体にとって重要なタンパク質の所在を感知するためでしょう。
では苦味という感覚がなぜ発達したかといえば、毒に対する危険信号であったと考えられます。自然界で代表的な毒といえばアルカロイド類で、これらは窒素を含んだ堅固な骨格が特徴です。こうした構造であるため、アルカロイド類は体内の重要タンパク質に結合しやすく、しばしば毒性を発揮します。このためこうした化合物を舌で感知し、飲み込む前に吐き出させてしまうよう、苦味という味覚が発達したのでしょう。
こうした、タンパク質に結合しやすいアルカロイド類のうち、たまたま症状を癒す方に働くものを、我々は天然物医薬と呼んでいるわけです。もちろんアルカロイドでない医薬や、人工合成の医薬もたくさんありますが、それらとて体内のタンパク質に結合しやすい構造であるのは同じことです。必然、その味も苦くなりがち――というのが、筆者の推測です。
コンプライアンスからアドヒアランスへ
最近では、「服薬コンプライアンス」ではなく、「服薬アドヒアランス」という言葉が使われるようになってきています。医者の指示にただ服従(コンプライアンス)するのではなく、患者が治療方針の決定に賛同し、積極的に治療を受ける(アドヒアランス)ことが重要である、という考え方の変化です。
そういう意味では、味をごまかしてなんとか薬を飲んでもらうのではなく、きちんと服薬の意義を患者さんに理解してもらい、口に苦い良薬を自らの意志で飲んでもらうよう、働きかけるべきということになるのでしょう。
我が家の娘も最近は、病気を治すために意を決して苦い薬を飲んでくれるようになってきました。目に涙を溜めながら粉薬をぐっと飲み込み、やがて熱が下がって元気になるたび、その表情は少しずつ大人びてゆく気がしています。
<関連記事を読む>
薬はなぜ色とりどりか?
薬の名前の由来を知ろう
プラセボ効果の不思議
企業で働く薬剤師の求人特集