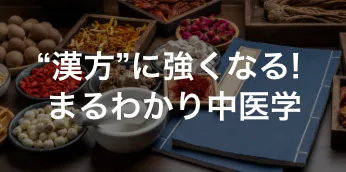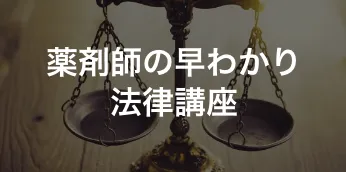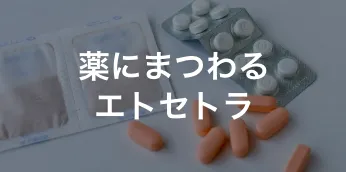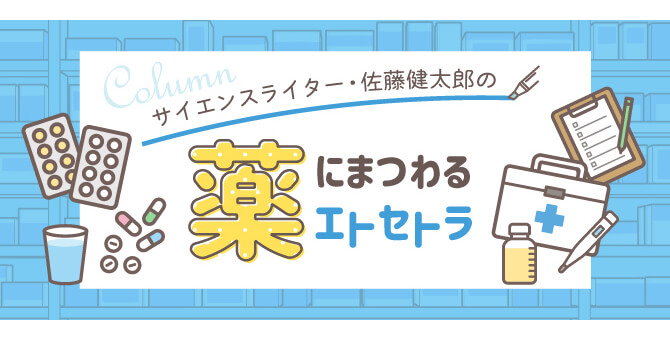
学べば学ぶほど、奥が深い薬の世界。もと製薬企業研究員のサイエンスライター・佐藤健太郎氏が、そんな「薬」についてのあらゆる雑学を綴るコラムです。

iPS細胞の実用化が創薬の現場で進む?研究の最新動向と今後の課題
山中伸弥・京都大学教授によって、人工多能性幹細胞(いわゆるiPS細胞)が初めて発表されたのは、2006年のことです。その発見は世界に大きな衝撃を与え、2012年には山中教授にノーベル生理学・医学賞が授与されました。
それから20年近くを経て、iPS細胞の応用研究は大きく進展しました。創薬研究の分野においても、iPS細胞は大きな貢献を果たしています。今回は、そうした展開について紹介してみましょう。
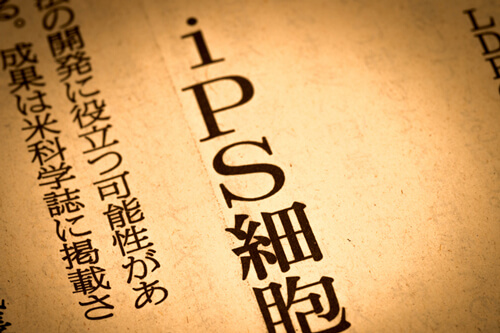
iPS細胞とは
まずiPS細胞とは何か、おさらいをしておきましょう。通常、人間の細胞のほとんどは一つの種類にしかなりえず、他の種類の細胞に変化することはありません。たとえば、皮膚の細胞から肝臓の細胞が生み出されたりはしません。
しかし幹細胞と呼ばれる特殊な細胞は、様々な種類の細胞を生み出す(分化する)能力を持っています。そして、一度分化した細胞が幹細胞に戻ることはありません。こんなことが起きたら大変であり、細胞の運命は一方通行というのが生物学の常識でした。
ところが山中教授は、人間の皮膚や血液などの体細胞に対し、たった4つの遺伝子を導入するだけで、多くの細胞に分化する能力と、ほぼ無限に増殖する能力を獲得した多能性幹細胞に変化することを示しました。これがiPS細胞です。
iPS細胞を利用すれば、理論上は皮膚などの細胞から各種の体細胞や臓器を作り出すことができます。また、iPS細胞は自分の細胞から作れますので、拒絶反応などの問題も起きません。受精卵から作成するES細胞などと比べて倫理的な問題も小さいので、生物学全体に大きな進歩をもたらしえます。
創薬分野におけるiPS細胞
創薬研究におけるiPS細胞の重要な応用として、疾患モデルの作成が挙げられます。たとえば京都大学のチームは、この病気の患者から作ったiPS細胞を大脳皮質神経細胞へと分化させ、これを用いてアミロイドβを減少させる化合物のスクリーニングを行いました。
その結果、これまでパーキンソン病などの治療に用いられていたブロモクリプチンが、高い効果を示すことが明らかになりました。ブロモクリプチンは、iPS細胞を用いた創薬としては初めて第Ⅲ相臨床試験の段階に進んでおり、実用化が期待されています。
参考:遺伝性アルツハイマー病iPS創薬で見つけた薬で最終治験|NHK 関西のニュース
アルツハイマー病は、これまでも膨大な研究がなされてきましたが、多くが失敗に終わってきました。その理由のひとつが、実験動物とヒトの間にある大きな溝でした。
炎症や高血圧などならともかく、脳や中枢の仕組みには動物とヒトの間に大きな差があり、信頼できる病態モデルが作りにくかったのです。特に家族性アルツハイマー病は、その家系に特有の遺伝子の変異に由来する疾患ですからなおさらです。
今回のモデルはこうした問題を乗り越えうるものであり、iPS細胞ならではの成果といえます。また、本連載で前回取り上げた、動物実験の縮小・廃止につながるものであることも、大きなポイントといえそうです。
🔽 医薬品開発における動物実験の現状と廃止に向けた取り組みについて解説した記事はこちら
iPS細胞を活用した毒性評価
化合物の毒性評価にも、同じく実験動物が使われます。ここにも、iPS細胞の活用が浸透しつつあります。
たとえば、ある種の化合物には、心臓に作用して致死性の不整脈を誘発するものがあります。こうした化合物を早期にふるい落とすため、モルモットやウサギなどを使った試験が行われてきました。
しかし近年、iPS細胞から心筋細胞を分化させ、これを不整脈リスク予測に用いる手法が進展しています。拍動する心筋細胞に対して薬剤を添加し、心拍リズムや活動電位などを測定するというものです。
すでにこの手法を用いた心毒性予測を国際標準化すべく、プロジェクトが動き出しています。
参考:CiPA – 包括的in vitro催不整脈アッセイ|Sophion Bioscience
その他、前回紹介したオルガノイド(3D組織モデル)や生体機能チップなどと組み合わせ、よりヒトの臓器に近いモデルで毒性評価を行う技術も進展しつつあります。動物実験をなくしてゆく動きは、こうしたiPS細胞による技術の裏付けあればこそともいえるでしょう。
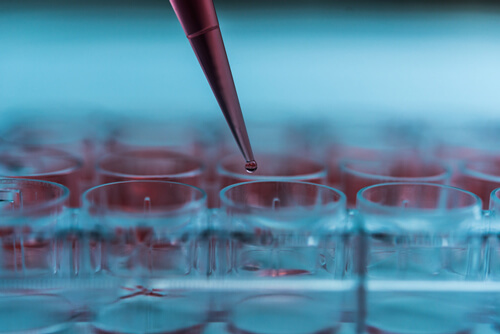
今後の課題
とはいえ、iPS細胞を用いる創薬には、まだまだ課題も多く積み重なっています。iPS細胞から各種の細胞への分化の際には、まだ細胞の性質や分化の度合いにばらつきが生じやすく、このためスクリーニングの精度が不十分なケースが出てきます。
また、iPS細胞を用いる創薬はどうしても労力がかかり、コストが高くつきます。スループットを上げることも容易ではなく、大規模なスクリーニングは困難なことが多いのです。
こうした状況ですので、iPS細胞を用いる各種試験が、薬事承認の根拠として十分信頼のおけるものになるには、まだ研究の積み重ねが必要と思われます。また、これら手法の信頼性を評価し、標準化を進めるには、ガイドラインの整備なども不可欠でしょう。
iPS細胞の創薬応用にはまだ多くの課題がありますが、疾患モデルや毒性評価、個別化医療の分野で着実に成果を上げつつあります。今後のさらなる進展のためには、研究者、企業及び規制当局の協業が、鍵を握ることになりそうです。