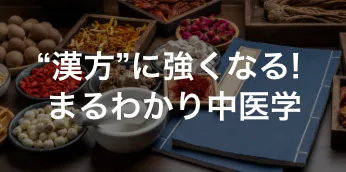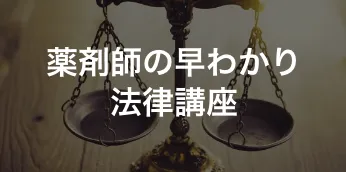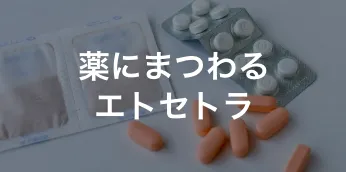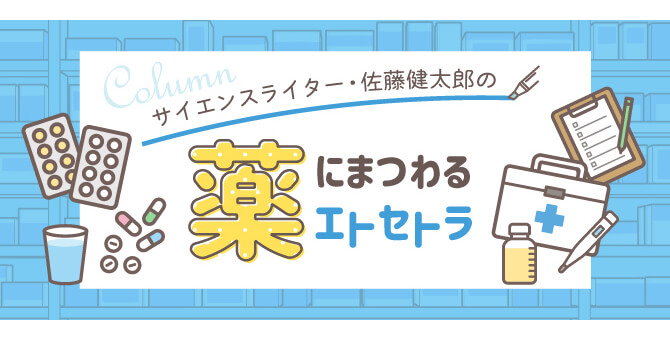
学べば学ぶほど、奥が深い薬の世界。もと製薬企業研究員のサイエンスライター・佐藤健太郎氏が、そんな「薬」についてのあらゆる雑学を綴るコラムです。

スイスに世界的な製薬会社が多いのはなぜ?
2024年の世界製薬企業売上ランキングを見ると、トップ10のうち6社が米国企業で、その強さは今さら言うまでもありません。
しかしその中にあって、存在感を放っているのがロシュとノバルティスのスイス勢です。ロシュは並み居る巨大製薬企業を押さえて業界首位に君臨しており、ノバルティスも7位につけています。日本ではダントツの武田薬品でも世界では14位ですから、その実力がわかります。
参考:【2025年版】製薬会社世界ランキング―トップ3はロシュ、メルク、ファイザー…リリーがトップ10入り|AnswersNews
スイスで活躍する製薬企業は、この2社だけではありません。国内には数百ものバイオベンチャーが存在し、各国のメガファーマと提携するなど、活発な研究を続けています。実際、スイスといえば時計など精密機械工業のイメージが強いですが、医薬品産業の輸出額は時計の4倍にも達しており、国の基幹産業となっています。
スイスは、面積でいえば九州よりやや大きい程度、人口は日本の約15分の1ほどでしかありません。にもかかわらず、製薬業界におけるスイスのこの強さはいったい何なのか。今回は、その秘密に迫ってみましょう。

地理・歴史的背景
地図でスイスを見てみると、イタリア・フランス・ドイツ・オーストリアに囲まれた、ヨーロッパの要衝といえる位置を占めていることがわかります。南方にはアルプス山脈がそびえ、フランスやドイツとの国境には大きな湖があるなど、全体として他国から攻め込みにくい環境にあります。
またスイスは、1815年のウィーン会議で「永世中立国」となっています。国民皆兵の体制で防備を固めており、ナチスドイツさえもスイスへの侵攻を計画したものの結局見送っているほどです。また政治的にも長年安定しており、こうした環境が産業を育てる基盤になったといえます。
教育環境
スイスは教育水準の高さでも有名で、特に理数系教育に力を入れていることで知られます。アインシュタイン、レントゲン、シュレーディンガーなどを輩出したチューリッヒ大学、ノーベル賞受賞者22人を出しているスイス連邦工科大学チューリッヒ校、その姉妹校であるローザンヌ校などがあり、いずれも世界大学ランキングの上位常連となっています。
また、フランスやドイツなどの強国に隣接し、4か国語が国内で用いられているためもあり、スイスには昔から多くの人材が流入しています。特に大戦期には、戦火を避けた科学者たちの避難所としても機能しました。たとえばアインシュタインは若い時代をスイスで過ごし、相対性理論など多くの成果をここで挙げています。
現在でも、これら研究機関には国家や大企業から多額の投資が行われ、基礎から応用まで幅広くハイレベルな研究が行われています。ここで育成された優秀な人材が、強力な製薬産業を支える基盤となっています。

バーゼルで生まれた2強
19世紀後半ごろ、コールタールなどを原料とした染料の化学合成が盛んになります。ヨーロッパの製薬企業の多くは、このころに設立された染料会社が起源となっています。
ノバルティスの源流となった3社も、この例に漏れません。チバ社、ガイギー社はいずれも1850年代にスイスのバーゼルで染料製造を開始し、後に合併してチバガイギーとなります。
またサンド社は1886年にやはりバーゼルで設立され、染料や医薬などを製造していました。同社は1996年にチバガイギーと合併し、ノバルティスが誕生します。
そしてロシュも、1896年にバーゼルで医薬品会社として誕生し、今日まで発展を続けてきました。つまりスイスの誇る2つのメガファーマは、いずれもバーゼルの地で誕生し、現在まで続いているということになります。
もちろんこれは偶然ではありません。バーゼルは、多くの大学があるチューリッヒに近い他、バーゼル大学も多くのノーベル賞受賞者を輩出した名門です。フランス・ドイツとの国境に位置しており、多方面の人材を受け入れやすい立地でもあります。
またバーゼル中心部には、ヨーロッパ有数の大河であるライン川が流れています。このため原料や製品の輸送に便利ですし、必要な工業用水の確保も容易です。
さらに、スイスは銀行制度が発達していることも有名であり、資金調達の面でも有利な環境でした。バーゼルの街にこうした数々の条件が揃っていたことが、世界有数の医薬品産業を育てる下地になったといえるでしょう。
化学・医薬産業の都であるバーゼルの伝統は、現代にも受け継がれています。ロシュとノバルティスは今もこの街に本拠を構えていますし、抗真菌剤などを主力とするバジレアファーマシューティカ社、バイオインフォマティクスのジーンデータ社など、800社にも上るバイオベンチャーがこの街に軒を連ねています。
天然資源に乏しく、人材育成こそが鍵という点で、日本はスイスと似た環境ともいえます。世界トップレベルの医薬品メーカーを育んだスイスのあり方は、日本にとっても大いに参考になるところがあるのではないでしょうか。