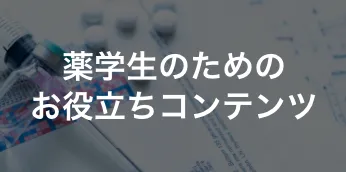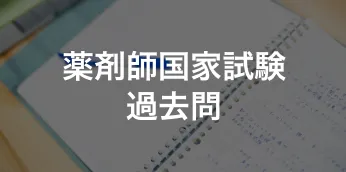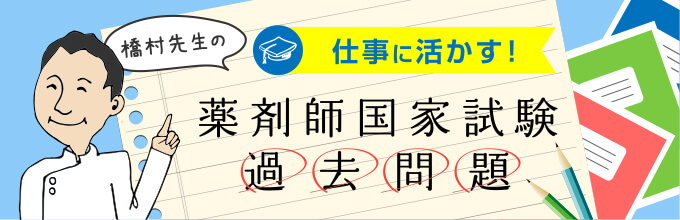
薬剤師国家試験は薬剤師なら誰もが必ず通った道。毎年、試験の難易度や合格率が話題になりますが、国試は“現役薬剤師”として基本的な知識を再確認するチャンス。橋村先生の解説で、国家試験の過去問を「おさらい」しましょう!
ここ2~3年、カフェイン含有製品の過量摂取が原因と思われる中毒事例が多発し、死亡事例も出てきています。この頃出はじめたのが、これまでの栄養ドリンク剤のカテゴリーではなく、清涼飲料水に属するカフェイン高含有商品“エナジードリンク”。そのため、これらの商品の過剰摂取がカフェイン中毒を引き起こしているかのような印象がもたれています。
しかし、カフェイン含有の製剤を消費者に提供する立場にある薬剤師として、本当に影響していることは何であるかということを確認すべきです。今回は薬剤師国家試験第102回を題材にみていきましょう。
【過去問題】
学校薬剤師が中学校の校長から薬物乱用防止教室の講師を依頼された。
問240(実務)
講義での説明として適切なのはどれか。2つ選べ。
- 1近年の薬物乱用の特徴として覚醒剤の使用が減少しています。
- 2乱用される薬物の多くは、繰り返し使用していると耐性という現象が起こり、徐々に使用量が増えていきます。
- 3危険ドラッグの依存性は大麻や覚醒剤と比べると強くありません。
- 4覚醒剤とは異なり、危険ドラッグは使用をやめた後に禁断症状が出ることはありません。
- 5危険ドラッグには、麻薬や覚醒剤と同様に、多幸感を高め幻覚作用を起こす成分が含まれていることがあります。
2、5
 解説
解説
- 1:使用量に明らかな減少傾向は認められません。
- 3,4:現在の危険ドラッグには、覚醒剤・大麻の成分に化学構造を似せて作られた物質などが添加されています。そのため、それぞれの症状が強く発現することはあっても、弱く発現するようなことは起きません。
– 実務での活かし方 –

カフェインは天然アルカロイドでメチルキサンチン類に属し、コーヒーの原料であるコーヒーナッツをはじめ、茶葉、カカオナッツ、ガラナナッツ、コーラナッツ、マテ葉などさまざまな植物の種子、葉などに含まれています。主にコーヒー等の天然由来成分として摂取され、清涼飲料水や、市販の総合感冒薬、解熱鎮痛薬などにも利用されています。
代謝経路は、人体に摂取後肝臓における脱メチル化で、84%が脂肪代謝促進に作用するパラキサンチン、12%が尿量増加に影響を与えるテオブロミン、4%が気管支喘息の治療に使用されるテオフィリンに代謝されます。
主な作用機序は、アデノシン受容体阻害作用による神経細胞の興奮です。非選択的なホスホジエステラーゼ阻害作用によりcAMPやcGMPが増加、それに伴う細胞内カルシウム濃度の上昇による心筋収縮力向上などがあります。
過量による中毒症状に関しては表1を確認してください。基本的にはテオフィリン中毒と類似した症状発現(中枢神経系、消化器系、循環器系)になります。
| 重症度 | 症状 |
|---|---|
| 軽症~中等症 | 食欲不振、振戦、不穏、悪心、嘔吐、頻脈 |
| 重症 | 低カリウム血症、高血糖、代謝性アシドーシス、横紋筋融解症、低血圧、意識障害、痙攣、不整脈 |
 事例
事例
カフェイン中毒事例と、実際のカフェイン含有製剤・商品との関係を確認します。
日本中毒学会・埼玉医大ER中毒センター上条氏らによると、2011年4月~2016年3月の約5年間にカフェインの過剰摂取により救急搬送された患者101例(男:女=53:48)(1.2g~82.6g中間値7.2g)(表2)のうち、原因となった製剤の96%がカフェイン含有錠剤であったと報告されています。国内ではカフェインの摂取許容量の規定はなく、欧州食品安全機関が規定するカフェイン1日摂取量は一般成人が400mg/日、妊婦が200mg/日となっています。
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 10人 | 5人 | 24人 | 25人 | 37人 |
次に、カフェイン含有量とコストの関係を表3で確認しましょう。
| 一般的な商品(100ml) | カフェイン含有量(mg) | コスト |
|---|---|---|
| カフェイン含有錠剤 | 100 | 16円 |
| コーヒー | 60 | 100円前後 |
| エナジードリンク | 40 | 210円/185ml |
| 紅茶 | 30 | 100円前後 |
| 煎茶 | 10 | 100円前後 |
カフェインの致死量が5g程度とした場合(実際は3~10gとかなり幅があり、統一されていません)、エナジードリンクであれば約63本分、約13,000円に対し、錠剤では50錠800円程度で済んでしまいます。費用や含有量を含めて考慮すれば、錠剤の方がカフェインを過量摂取してしまう可能性が高いと言えるでしょう。
では、なぜメディアなどでカフェイン中毒の原因がエナジードリンク類であるかのように報道されているのでしょうか?
それにはまず販売に関する背景が隠されています。2005年に日本におけるエナジードリンクの先駆けとしてレッドブル®が販売開始され、2011年にモンスターエナジー®、それ以降各社が多数販売を開始。2013年には自販機販売開始(カフェイン含有錠剤は1973年に発売)となっています。このエナジードリンクは食品衛生法上、食品扱いとなり清涼飲料水に分類され、清涼飲料水と栄養ドリンクや錠剤とは販売方法に大きな違いがあります(表4)。
| 種類 | 分類 | 販売経路 |
|---|---|---|
| 栄養ドリンク | 医薬品 | 薬局・ドラッグストアなど |
| 医薬部外品 | 上記に加えコンビニ・スーパー・自販機でも可 | |
| エナジードリンク | 清涼飲料水 | |
| カフェイン錠剤 | <第3類医薬品 | 薬局・ドラッグストアなど(ネット販売可※) |
表4からも判断できるように、清涼飲料水としてのエナジードリンクは誰にでも手軽に手に入れられます。このような背景もあり現在のような報道に至ったのかもしれません。
カフェインには現在販売量の規制などがありません。今まで示してきたように、カフェイン中毒の原因となっているのは、スーパーやコンビニで買えるエナジードリンク類ではなく第3類とはいえ規制のある医薬品と言えます。このことを考えると、規制がないからと大量購入したり、頻回に購入を繰り返すような患者へは、自由に販売するのではなく、薬剤師として用法用量を順守するよう注意喚起を行ったほうがよいでしょう。