農薬開発では日本が最強‐“成功体験”を武器に

農薬の研究開発は、日本メーカーの世界一強――。日本の製薬企業が新薬の産みの苦しみにあえぐ中、日本で登録された新規農薬の半数近くは、日本の農薬メーカーが生み出し、世界でも多く使われているという事実はあまり知られていない。なぜ日本から新しい農薬が次々と生まれてくるのか。医薬では世界有数の開発受託機関(CRO)で、農薬・化学品分野でも世界最大手のエンヴィーゴアジア太平洋地域農薬・化学品ビジネス統轄本部長の堀越光男氏、上級顧問の五十嵐丕氏は、「ベテラン研究者の成功体験と、若手研究者が物事を決定できる自由な研究環境が、農薬の研究開発に好循環を生み出している」と強調する。グローバル化し欧米からイノベーションが発信される時代に入っているが、今もなお日本企業が技術力とチームワークを武器に頑張っている事業領域がある。
日本は、世界最大の農薬創出国といっても過言ではない。2012年6月時点の調査で、日本で農薬登録された383剤のうち159剤(41.5%)が日本の農薬メーカーが開発したと報告されている。海外で販売されている農薬も日本発がズラリと揃う。エンヴィーゴによると、1996~2016年までの20年間で同社が欧州申請した新規農薬18品目のうち、日本企業が創出した品目で半数を占めるほどの実力だ。日本の農薬メーカーは、日本のみならず、世界の農業をも支えているのだ。
なぜ、それほどまでに日本の農薬メーカーは強いのか。農薬学会誌には、「多様な農業を営む農耕文化と化学技術力が高いレベルにあり、高質的な農業創意性が達成できている」と記載されているように、歴史的に農薬創出力が強かった。それは今も続いており、堀越氏は「新規農薬開発に対する意欲が強い」とシンプルに表現する。
農薬の開発プロセスは医薬品と似ている。雑草や菌、害虫などターゲットに応じて化合物のスクリーニングを行い、一定数の化合物に絞り込んだ後に合成を行い、化合物の毒性や環境に与える影響への評価から一つの化合物に選定する。試験データをもとに各国当局に申請を行い、審査を経て登録されるという流れだ。ターゲット探索から化合物合成まで約3年、その後の安全性評価や環境評価では3~5年、申請から登録までに2年とおよそ10年で一つの農薬を開発している。
農薬の市場環境変化にいち早く対応してきた。農薬には除草剤、殺菌剤、殺虫剤、殺虫殺菌剤など様々な種類が存在し、医薬品開発のように特定領域に強いスペシャリティ化が進行している。日本の主要農薬メーカーを見ると、殺虫剤に強い会社、殺菌剤に強い会社、除草剤に強い会社とそれぞれが特色を発揮している。
現在では、一つの剤が持つ市場規模は縮小し、製品寿命は短くなってきている。日本国内の農薬市場は、休耕地が増えた関係で耕地面積が減り、過去の4000億円から現在は3300億円と縮小傾向にある。五十嵐氏によると、「過去には日本だけで100億円を売り上げた大型農薬もあったが、今では10億円を売り上げる原体も少なくなっている」という。さらに、新規農薬の投入後、何年か経つとそれに抵抗性を示す害虫が現れて、農薬が効かなくなるという現象もしばしば見られる。
例えばダニ剤。高温多湿の日本ではダニが出やすく、5年間隔でダニ剤の世代交代を考え、次世代農薬を開発しなければならず、新しい農薬を継続的に投入していく必要があるのだ。そのため、「開発の意思決定を行う場合も、“ゴー”が出やすい環境にある」(五十嵐氏)という事情からも、各社は早期段階から様々なリスクを予測し、スピード感を持って開発している。
グローバル化にも先手を打ち、対応も早かった。日本での登録を済ませた後に海外市場での登録を目指すという企業戦略だった頃に比べ、化合物の特性や適応範囲によっては日本よりも海外向けの開発を優先したり、世界同時開発を選ぶ時代に入っている。日本の農薬メーカーは25年前からグローバルを見据えて開発しており、原体登録を保有しながら各地域で販路を持つ海外企業にライセンスする事業展開も進めている。
30代の研究者が意思決定‐「日本発農薬」が4割強の衝撃
農薬開発を生み出す秘訣は、研究開発組織の雰囲気にも現れている。日本の農薬メーカーの研究所に行くと、「研究者の目がきらきらしている」という印象を受けるという。
10年に一つの新規農薬を「自社から生み出していく」という情熱がみなぎっており、開発成功確率の低下や規制の厳格化、市場の縮小といった負の環境変化を跳ね返す原動力になっている。
農薬創りを支えるのは、「成功体験」。研究所には、初期のR&Dから生物評価、安全性評価を含め、研究開発の専門家を揃える。医薬品開発は外部資源を活用したオープンイノベーションが主流となっているが、農薬は自社開発へのこだわりが強い。数々の新規農薬を創出した成功体験を持つ研究者が存在し、企業も彼らの経験を大事にして、農薬創りに挑んでいるのだ。
一人ひとりがスペシャリストでありながらもチームワークに重点を置く企業の研究姿勢に加え、リード化合物の最適化段階で特許戦略や製造コスト、日本市場での有効性や初期安全性評価の担当者と情報共有がなされている研究環境が後押しする。
堀越氏は、「海外メーカーでは研究開発で分業化が進む傾向にあるが、日本のメーカーは全員が一つのチームで研究開発を進めている」と話す。まさに、研究者の成功体験が組織内でシェアされ、チームワークで研究所の高いモチベーションを維持し、開発の方向性で精度の高い意思決定を行っている。
この研究者が持つ成功体験に、若手の発想力・行動力が融合する。農薬の研究開発現場では、30歳代の若き人材がリードする。若手研究者に研究開発に関しての意思決定が行える権限が与えられており、現場から上長へと研究アイデアがどんどん提案されているという。
成功体験を持つ人材が近くで黙って見守る環境があるから、若手がイノベーションに対する挑戦で物怖じすることなく、「自分が新しい農薬を生み出してやる」というモチベーションを持った仕事が可能になる。失敗に寛容な環境下で、入社後間もない頃から経験が積み上がり、有能な研究者がつくられていく基盤になっているという。
そして自分たちが創った農薬がどう生かされているのかをカスタマーから得ている。農家から農薬に関するフィードバックをもらい、次の研究開発に生かしていく。
研究者の成功体験が次世代に伝承され、若い研究者が持つ発想と化学反応して新たな農薬が生まれ、それが顧客の声によって改良されていくメカニズムが、PDCAサイクルとして回転している。
CROの活用は“医薬以上”‐開発期間短縮とコスト削減
自社研究開発基盤が充実している日本の農薬メーカーだが、CROの戦略的活用を進めていることも見逃せない。数社のCROを使い分ける農薬メーカー、1社のCROを集中的に使う農薬メーカーとその戦略は様々だが、GLP制度の導入により、安全性評価や環境評価の試験を外部委託することによって、開発コストの削減やスピードアップを図っている。
エンヴィーゴが受託した農薬メーカーのプロジェクトでは、毒性試験の開始から申請までに通常で5年以上かかる期間を3年3カ月まで短縮することに成功した。医薬品と同様、農薬の研究開発プロセスではターゲットの探索で多大な期間と費用を必要とする中、農薬メーカーは初期のR&Dに経営資源を集中しており、CROとパートナーシップを組む必要性が高まっている。自社ラボで長期試験を実施しないことを決定する農薬メーカーもあり、「医薬よりもCROの活用事例が多いかもしれない」という。
医薬品メーカーと農薬メーカーでは、研究開発環境で共通する部分が多い。だからこそ、日本の農薬メーカーが世界を牽引しているという事実は重く、成功体験を持った様々な専門家が一つのチームを構成しながらも、現場視点を持つ若い世代の研究者が意思決定を行える自由な研究環境は、医薬品メーカーも参考にすべき点ではないだろうか。医薬品開発プロセスは農薬よりも長く、合成、非臨床、臨床の一つのチームで情報共有し、最適な意思決定に結びつけていく意義は大きい。
研究者の個から生まれるチームワークの強い組織は、研究開発に好循環をもたらすだけではなく、失敗から成功につながるヒントを見つけることができ、失敗を恐れずにイノベーションに挑戦していく企業カルチャーを強くできる。
出典:薬事日報

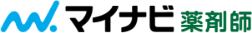



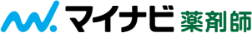










薬+読 編集部からのコメント
製薬企業が創薬に苦しむ中、日本で登録された新規農薬の半数近くは、日本の農薬メーカーが生み出し、世界でも多く使われています。
なぜ日本の新しい農薬は次々と生み出され、成功するのか。農薬・化学品分野でも世界最大手のエンヴィーゴアジア太平洋地域農薬・化学品ビジネス統轄本部長の堀越光男氏、上級顧問の五十嵐丕氏は、ベテラン研究者の成功体験と、若手研究者が物事を決定できる自由な研究環境などを理由に挙げています。