薬剤師の3交代廃止検討~働き方改革で夜間対応減 九州大学病院薬剤部
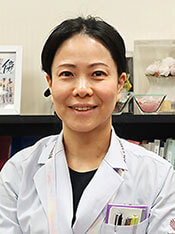
九州大学病院薬剤部は、薬剤師の勤務体制を3交代から2交代へ変更することを検討している。遅い時間まで診療している医師の注射薬オーダに対応するため、2003年に日勤、準夜、深夜という全国的にも稀な3交代制の導入に踏み切った。注射薬の処方から実施までの時間を短くすることで、中止や変更を極力少なくする意図もあったが、近年の働き方改革で医師の長時間労働の是正が求められ、夜間対応の必要性は徐々に小さくなっている。2交代制に変更して日勤帯で働く薬剤師数を増やし、対人業務を拡充したい考えだ。
3交代制を開始したのは、注射薬オーダシステムの導入に伴って、医師から注射薬オーダの締切時間をできるだけ遅く設定してほしいと強く要望されたことがきっかけ。現在は日勤帯(8時15分~17時00分)、準夜帯(15時00分~23時45分)、深夜帯(23時45分~8時30分)の3区分を設けて薬剤師を配置している。注射薬オーダの締切時間を内科系診療科は16時、外科系診療科は20時に設定し、準夜帯の薬剤師が注射薬の個人セット化などを担当している。
3交代制で20年以上運用してきたが、社会の変化に応じて医師のニーズも変わってきた。現在は、医師の勤務時間内の注射薬オーダ割合は約96%と高い。
背景について、内田まやこ教授・薬剤部長(写真)は、「働き方改革の影響で、医師の時間外労働の上限が設けられた。それに伴い、医師や薬剤師、看護師の全職種で時間外労働の削減が必要になってきた」と語る。
薬剤師にとっても、準夜や深夜の出勤、土日勤務による振替休日によって、平日の日勤帯の業務は全薬剤師の約70%の人員で回さざるを得ず、負担が大きいことが課題だった。このほか、準夜帯退勤時、深夜帯出勤時の交通手段や安全性確保に加えて、日勤翌日の深夜勤務や準夜勤務翌日の日勤の場合に、休息を十分に取れないことも問題だった。
来年のシステム更新のタイミングに合わせて、3交代から2交代への変更を実現したい考えだ。日勤帯と夜勤帯の2交代制が実現すれば、注射薬オーダの締切時間は一本化され、日勤帯での対応になる。夜勤帯は少人数体制になり、日勤帯に薬剤師を回せる。内田氏は「まずはセントラル業務に対応する人数を確保し、病棟業務のさらなる充実化を行っていきたい」と展望を語る。
現在は各病棟に1人ずつ専任薬剤師を配置しているが、シフトによって不在となることもある。「常時1病棟に1人、薬剤師がいる体制を目指したい。薬物療法の変更や調整が多い病棟では2病棟に3人配置することも考えたい」と内田氏。患者と薬剤師の接点や対話を増やし、副作用の予防や軽減のみならず、患者の悩みを聴取し、医師への処方提案につなげたいという。
同院の病床数は1252床で、薬剤師数は教員を含めて97人。以前に比べて薬剤師数は段階的に増えているが、タスクシフトの進展による業務量の増加で、マンパワーはまだ十分とは言い難い。将来の地域病院への薬剤師出向を見据えて、来春には定員枠を3人増員できることになった。
内田氏は24年10月に同院教授・薬剤部長に就いた。1999年に神戸学院大学薬学部を卒業し、同大学院修士課程を修了後、同院に入職し15年間臨床現場で働いた。16年には大阪薬科大学(現在の大阪医科薬科大学)の講師に就任。21年からは同志社女子大学薬学部教授を務めていた。
同院での豊富な臨床経験や大学教員経験、研究実績が評価されて抜擢された。内田氏は、選考の背景に「若い薬剤師のロールモデルとなるような臨床経験と研究実績が求められたのではないか」と話す。「まさか、こんな形で再び戻ってこられるとは夢にも思わなかった。薬剤師冥利に尽きる。薬剤師のほか、医師、看護師、事務職などに顔なじみも多く、日々支えていただいている」と話す。
教育や研究での貢献も期待されている。「医療は過去に築き上げられたエビデンスで成り立つ。医療を常に最適化する努力が必要。薬剤部だからこそできる臨床研究にも取り組みたい」と話している。
出典:株式会社薬事日報社












薬+読 編集部からのコメント
2003年より日勤、準夜、深夜という全国的にも稀である3交代制の導入に踏み切っていた九州大学病院薬剤部が、薬剤師の勤務体制を3交代から2交代へ変更することを検討。近年の働き方改革で医師の長時間労働の是正が求められ、夜間対応の必要性が徐々に小さくなっていることが背景にあります。