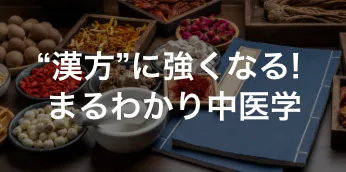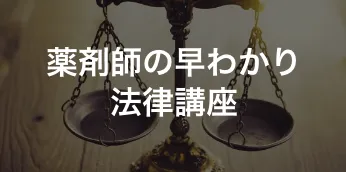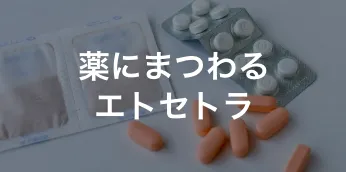知れば知るほど奥が深い漢方の世界。患者さんへのアドバイスに、将来の転職に、漢方の知識やスキルは役立つはず。薬剤師として今後生き残っていくためにも、漢方の学びは強みに。中医学の基本から身近な漢方の話まで、薬剤師・国際中医師の中垣亜希子先生が解説。
第113回 肝気鬱結(かんきうっけつ)とは?ストレスが症状となって現れる理由
現代の日本は、精神的なストレスによって、心や体に不調を感じる人が多くいます。西洋医学が心と身体のつながりを認めるよりもずっと前から、中医学はこれを重視し、理論や治療法を発展させてきました。近年注目されている「腸脳相関」もそのひとつです。
中医学は、精神的ストレスによる心身の不調に対する養生法・治療法の宝庫です。今回は、ストレスがかかったときに心と体に起こるパターンを中医学的に考えてみましょう。
ストレスがあると、気の巡りは悪くなる(肝気鬱結)
ストレスがあると気の巡りが悪くなります。
ここで言うストレスとは、多分主に精神的なストレスや負荷を指しています。「主に」と表現したのは、精神的なものだけが原因ではなく、ほかの種類のストレスも関係することがあるからです。
また、ここで言う「気の巡り」とは、主に「肝気(かんき)の巡り」を指します。肝気=肝の気とは、五臓(肝・心・脾・肺・腎)のうちの「肝」に宿る「気」のことです。
肝気の巡りが悪くなることを、「肝気鬱結(かんきうっけつ)」と言います。略して「肝鬱(かんうつ)」。「肝気」が「うっ滞(鬱滞)」して「むすんでしまった(かたまった!)」という意味です。
そして、肝気は、「情緒」「感情」「気分」「機嫌」といった意味を持ちます。
何かが原因で肝気の巡りが悪くなるとこれらが不安定になる、あるいは、これらが不安定になると肝気の巡りが悪くなる…といった具合です。
本記事ではこのあと、さまざまな症状や病気、体の状態を「肝気鬱結(肝鬱)」の例として紹介していきます。ただし、それらの原因が必ずしも肝鬱であるとは限りません。肝鬱が関係していることもあれば、別の原因によることもあります。あるいは、複数の要因が絡み合っている場合もあります。
たとえば「頭痛」の場合、中医学ではその原因として以下のようなさまざまな見立てが考えられます。
・肝気の巡りが悪くなる「肝鬱」
・血流が悪い「血瘀(けつお)」
・気も血も足りていない「気血両虚(きけつりょうきょ)」
・水のだぶつきがある「湿邪(しつじゃ)」
…などなど
このように、頭痛という一つの症状だけでは、「虚」か「実」か、「寒」か「熱」か、あるいはどの臓腑に関係するのかを見極めるのは難しいのです。
本記事では「肝鬱」をテーマに、肝鬱と関連しやすい症状を例示しますが、それらの症状=肝鬱とは断定できませんので、あらかじめご承知おきください。
中医学の教科書には肝気鬱結証の症状が羅列されていますが、今回は私の薬局にいらした患者さんの体験も踏まえてお伝えしようと思います。やや程度が重かったり、やや主観が入ったりすることを念頭に置いて、お読みいただければ幸いです。

ストレスがいろいろな症状となって現れるのはなぜ?
ストレスは肝鬱を招き、肝鬱は全身のいろいろな症状を招きます。
それは、肝が全身の気の巡りを調節する役割(=疏泄(そせつ)作用)を担う臓器だからです。
人体の中で、「気」の流れを管理しているのは、「肺」と「肝」です。
肺は息を吐いて気を外(陽)側へ、息を吸って気を内(陰)側へと、全身の気の在り方に大きく影響を及ぼします。
それもあって、気功やヨガの修行法には、呼吸の仕方に厳しい要求があります。修行をゆるーく行えば、健康法になります。呼吸が心身に大きな影響を与えることは、大昔から世界中の民族が気づいていたのです。
他方で、肝は、「疏泄(そせつ)」作用によって、全身の気に大きく影響し、全身の気の流れを管理します(疏泄作用)。肝がちゃんと機能していれば、全身の気が滞りなく、流れるべき方向に流れます。
「疏泄」の「疏」の字を分解すると、偏(へん:左側)の部分は「切り開く」という意味、旁(つくり:右側)は「流れる」という意味、「泄」は「捨てていく」という意味です。
つまり、肝の疏泄作用とは、「切り開いて、流して、通して、代謝する(捨てていく)」といった意味です。肝の疏泄作用は、現代風に言えば、自律神経系の調節作用や精神情緒系の安定なども含んでいます。
肺と肝は協調して、気の在り方・気の流れを管理していますが、肺と肝では不調の現れ方・現れる部位などが異なります。
西洋医学では「肝臓」は沈黙の臓器などと表現されますが、中医学の「肝」は最もうるさく、心と体の両方に、いろんなサイン・アラートを出して訴えます。だから、トラブルがあるととても分かりやすいです。
🔽 中医学の「肝」について解説した記事はこちら
肝は気を上や下へ向かわせたり、あるいは外へ発散させたり、内にしまいこませたりして、頭のてっぺんからつま先まで、「気」がなめらかに滞りなく行きわたらせるようにする働きを担います。ゆえに、肝のコンディションが悪くなると、気がのびのびと巡らず、行き届かず、心と身体のあちこちにいろいろな症状となって現れます。
今回はその中から、①気分・感情・情緒の不調と、②メンタルの熱がこもる(肝鬱化火)について解説します。
【ストレスはさまざまな症状となって現れる】
↓
肝気の巡りが悪くなる(肝気鬱結、略して肝鬱)
↓
全身の気の巡りが悪くなる
↓
いろいろな不調が現れる(以下は代表的なパターン。これらのうち一部だけが現れることもある)
① 気分・感情・情緒の不調
② メンタルの熱がこもる(肝鬱化火)
③ 全身の筋肉が固くなる
④ 気が上逆する
⑤ 水や血の巡りにまで及ぶ
など
春は「肝」がダメージを受けやすい季節
昔から、春先の暖かさが増すころは「木の芽どき」などと呼ばれ、心身の不調をきたしやすいと言われてきました。それもそのはず、1年の中でも春は肝がコンディションを崩しやすい時季です。
春になると自然界には「小陽の気(しょうようのき)」というエネルギーが満ちてきます。この「小陽の気」は、人体の五臓のうちの「肝の気」の性質と似ています。小陽の気に肝気があおられ、肝がコンディションを崩し、肝気の巡りが悪くなり、肝鬱の症状が現れやすくなるというわけです。
春に不調が現れやすい人とそうでもない人の体質の違いは、主にもともとの肝のコンディションの違いによるものです。
もちろん、引っ越し・就職・進学といったライフイベントが心身に与える影響も大きいです。しかし、こうした環境の変化がなくても、毎年春になると心身のバランス(特にメンタルに不随して)を崩しやすい方もいます。そういう人はもともと肝気鬱結な体質があると考えられます。
肝鬱が招く心身のパターン① 情緒・感情・気分の不調
肝気は、「情緒」「感情」「気分」「機嫌」という意味を持ちます。
肝気が鬱結すると、イライラ、気分がくさくさする、憂鬱、不愉快、我慢、緊張、不満が多い、負担を感じるをするなどの精神状態になります。そのため、ストレスがかかった状態を、肝鬱と表現しがちです。肝気鬱結証を持つ人を、中医学を学ぶ人は親しみをこめて「肝鬱さん」と呼んだりします。
肝鬱を招くストレスというのは、ドラマチックなものから、ほんの小さな我慢や不満の積み重ねまであります。我慢の多い毎日や、突発的な強い精神的ストレス、緊張、悩み事、納得がいかない、理不尽な思いをするなどといったものです。
たとえば、外出のたびに、周囲のマナーや所作が気になる人もいます。あるいは、いわゆる社会の常識や、普通を求められる生きづらさにストレスを感じることもあるでしょう。子ども時代のいじめられた経験・虐待・トラウマ、親が求めた理想像になれなかったことに、大人になっても苦しむ方はたくさんいます。
また、苦手なコト・ヒトと対峙する際も、気の巡りは滞ります。例えば、大人数の前で話すので何日も前から緊張しているとか、威圧的な人と顔を合わせなければならなくて考えただけでドキドキする…とか。緊張で夜も眠れない、緊張で何ものどを通らない…なんてことを経験したことがある人も少なくないはずです。
これ以降も肝鬱による心身への症状の現われ方を書いていきますので読んでいくうちに分かるかと思いますが、長期間の我慢や不満が及ぼす心身への害は普通ではないな…と思うことがあります。
ポジティブなこともストレスになり得る
肝鬱を招くストレスは、なにも苦手なこと・嫌なことなどネガティブなことだけが原因ではありません。熱望してようやく叶ったことや、楽しんでいる学業・仕事だったとしても、責任や負担が重すぎる、期限が短すぎる、やることが多すぎる、その内容のレベルがまだ自分に見合ってない…など、いわゆる「荷が重い」状態も原因となります。自覚としてマイナスな感情を持っていなくても、です。
また、その人の人生がかかっているような、深刻な相談を受ける方も、肝気鬱結せざるを得ない印象です。例えば、自分にしかできない役目と感じる職業、切実で深刻な相談内容を抱える場合は特にそうでしょう。
精神的なことがきっかけではなく、他の病態から肝鬱になるパターンも
肝気の流れは、他の病気や不調によっても妨げられることがあります。最近では、新型コロナウイルス感染症の後遺症で不眠や気分の落ち込みが続くといった例が分かりやすいでしょうか。
「肝気がスッキリ通っていないと、気持ちもスッキリしない」し、その逆に、「気持ちが落ち込むと、肝気の流れも滞る」ということになります。このように、肝気の停滞/感情の不調は互いに影響し合っています。
肝鬱さんがよくなるメンタルの状態や症状
肝気の巡りが悪くなると、精神・情緒・気分・感情・睡眠などの状態が不安定になります。以下に箇条書きで例を挙げていきます。
特に女性の場合は、思い当たるストレス要素がなくとも、月経周期や更年期などが深く関係して引き起こしているケースも割と多い印象です。
ちょっとしたことですぐ腹を立てる、いつも怒るようなことであってもいつもより更に怒る…など。
・なんだかムカつく、とにかくムカつく
身近な人にあたる。ひどくなると、職場や友人関係を壊しかねない。
・気分がくさくさする
・気分が落ち込みやすい
・憂鬱、抑うつ
・緊張
・不愉快、不満、負担、理不尽をよく感じる
・ため息をつく
・寝つきが悪く、寝られないとイライラする
・怖い夢をみる(追いかけられる、焦る、仕事をしている系の夢)
・寝ても疲れがとれない
考え事・悩み事がいつも頭から離れない。寝ている間も考えているような感じで、頭や気持ちが休まらない。肝鬱の場合、その人にとって適切な睡眠時間が十分にとれていても疲労感がとれない。
・(女性の場合)特に月経前に上記の症状が強まる
・(女性の場合)特に排卵期に上記の症状が強まる
「肝気鬱結」と言うと、患者さんから「それって鬱病ってことですか?」と、たまに質問されます。結論から言って、中医学の肝気鬱結は西洋医学の鬱病とはイコールではありません。
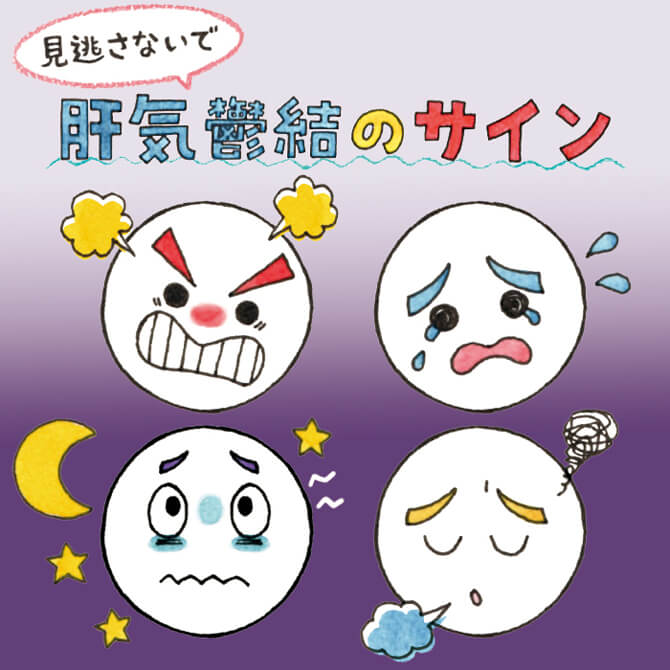
肝鬱が招く心身のパターン② メンタルの熱がこもる(肝鬱化火)
「気」は身体を温めるエネルギーのようなものですから、肝気鬱結によって「気」が詰まり続けると、ボッ!!と「熱」に変わります。肝気は特に強い気ですから、強い熱源となります。この現象を中医学では、「肝鬱化火(かんうつ・かか)」と呼びます。「化」は「変化」を意味しますので、肝鬱化火という中医学用語は「肝鬱が火に変化する」ということです。
なお、肝鬱があるからといって、すべてのケースで化火するわけではありません。とはいえ、私の実感として、肝鬱が長く続いたり、短期でも猛烈な精神的負荷が加わったりすると、化火に至るケースが多いように思います。
また、孤独も、非常に強い熱を生みます。西洋医学的にも、孤独が炎症を生むことは分かっています。
肝鬱化火によって生まれたメンタルの熱を、「肝熱(かんねつ)」とか「肝火(かんか)」などと呼びます。どちらも似たような意味です。肝熱よりも肝火のほうが少し熱の勢いが強いとする解釈もあるかもしれません。
多分にメンタル状態が関係して生まれた熱なのでメンタルの熱と呼びましたが、肝火・肝熱はさらなるメンタル症状を引き起こしますし、フィジカル症状も引き起こします。
中医学でいう「熱」や「火」は、実際の体温が高い場合もそうでない場合もあります。自覚として、ほてりや熱っぽさがある場合も、ない場合もあります。では、肝熱・肝火をどうやって見分けるかといったら、全身の症候からです。
メンタルの火が引き起こす、さまざまな症状・病態
肝鬱化火によってメンタルの熱がこもると、熱は必ずそのはけ口を求めます。そのはけ口となった場所に症状が現れます。しかも、肝火は心(しん)に飛び火しやすく、肝火から心火が引き起こされることも非常に多いです。肝火も心火もどちらもメンタルの火と言えます。
臨床で私が多く出くわすのは、皮膚のトラブルです。私の漢方薬局は、皮膚病に特化しているわけではないにもかかわらず、です。
中国最古の医学書『黄帝内経(こうていだいけい)』に、「諸痛痒瘡,皆属於心(諸々の痛み・痒み・瘡は皆、心に属す)」と記載があります。
現代の中医学の教科書では(中医基礎理論や中医診断学)、皮膚は「肺」と結びつけて説明されていますので、皮膚病と言えば、まずは「肺」をイメージします。しかし、『黄帝内経』には、皮膚と「心」の結びつきについて、はっきりと記述されています。つまり、皮膚は、五臓の中の「肺」の支配下にあるだけでなく、「心」の支配下にもあるということです。
私の祖母をみていたベテランの心臓内科医が、「大人の皮膚病の90%はストレスが深く関係しているからね」とつぶやいたのを耳にして、心底おどろいたことがあります。この医師はおそらく『黄帝内経』を読んだわけではないでしょう。自分の専門分野とは関係なく、患者さんに真摯に向き合ってきたことのあらわれだと思いました。
メンタルの火によって引き起こされる皮膚トラブルは、じんましん、湿疹、ふきでもの、ニキビ、アトピー性皮膚炎、乾癬、帯状疱疹などさまざまです。あるいは、結膜炎、霰粒腫などの眼の粘膜の炎症、口唇ヘルペス、口内炎などの粘膜の炎症、そのほか、診断がつかない(または皮膚科医によって診断名が変わるような)皮膚や粘膜の赤み・痒み・炎症などです。しつこく繰り返して治らない場合は、もしかして湿熱が関係しているかもしれません。
【メンタルの火が引き起こすいろいろ】
身体のどこかがかゆくなる・赤くなる・炎症が起きやすいイメージ。
舌の両端が他より赤い場合、「肝火」や「肝熱」が考えられますが、肝火・肝熱があるからといって必ずしも舌の側面が赤くなるわけではありません。
舌の尖端が他より赤い場合、「心火」や「心熱」が考えられますが、これも同様に心火・心熱があれば必ず赤くなるとは限りません。
・頭痛、めまい
・耳鳴、難聴、突発性難聴、耳が詰まった感じ
・頭鳴り
・眼が脹るように痛む、眼が痛む、眼が赤い
・眼圧が高い
一般的には正常な範囲の数値だとしても、その人の今までの眼圧より高いという状態も含む。普段の平熱が分かっているから発熱に気づくのと同じ原理で、出発点と現在の地点の差が重要ポイント(例:正常眼圧緑内障など)。
・血圧が高い
一般的には正常な範囲の数値だとしても、その人の今までの血圧より高いという状態も含む。
・怒りムードをまとっている
ふだんあまり怒らない人が怒るよりも、怒りっぽいタイプ(=肝火タイプ)の人が怒ってないときのほうが、よっぽど怒っている。ちなみに、肝火はなくて心火だけの人は、怒りっぽくなかったりする。
・ますます不眠症(睡眠の質が低下)
・顔が赤い
・食欲が増す
ストレスで食欲が増すのは、肝火が胃に飛び火→胃熱(胃火)が生じた状態。胃熱が食べたものを燃やしてすぐに消火してしまうため、すぐにお腹がすく。その逆で、ストレスで食欲をなくすタイプもある(こちらは次回で解説)。
肝火・心火は、「火」のように、いずれも“上へ上へ”と燃え盛る性質を持つため、頭部や顔まわり(頭面部)に症状が現れやすい傾向があります。
特に肝火は暴力的なパワーをもち、しばしば暴発します。この状態を「肝火上炎(かんかじょうえん)」と呼び、「気」「血」「熱」がすべて上へ突き上がるように動くのが特徴です。
「気」が強く突き上げることによって、脳の圧も上がりますので、例えば眼圧の上昇、耳鳴り、頭痛などの症状が引き起こされることがあります。一方で、皮膚病などは頭面部だけでなく、全身に散らばることも多いです。
それから、肝の疏泄が滞るので、肝経の通り道や肝が関係するエリアで症状が起きやすいというのもあります。
たとえば、ニキビ・ふきでものならこめかみやフェイスライン、頭痛なら偏頭痛やこめかみあたりが痛む、身体の側面部や、肝と関わりの深い目、胸(おっぱい)、生殖器系…などが肝胆経の通り道です。
無理していませんか?「肝」のサインに耳をすませて
漢方相談の初回では、みなさん深いところを話してはくれません。相手(中垣)が信頼するに足る人物かも分かりませんから当然です。しかし、心身のあちこちに現れているサインから、「長い間、かなり強いストレスがあった」ということは伝わってきます。
打ち解けてくると背景を話してくださるようになり、「だから、こんなに肝鬱の症状が強かったのか…!」と納得するのです。
長年の肝鬱は心身に強い悪影響を及ぼし、いろいろな症状・病気とつながります。発育段階の若いときには、努力して克服したり挑戦したりすることが大切な場面もあるでしょう。しかし、ある程度の年齢を重ねたら、あるいは、若くても内面を深く見つめて自身をよく理解していたら、本当にどうにも自分には合わないことからは無理をせずに離れたり、避けたりして良いのです。自分を一番大切にしてあげられるのは、やっぱり自分自身ですから。
次回は、肝鬱が招くパターン「③全身の筋肉が固くなる」以降を解説します。たとえば、緊張して呼吸が浅くなるなども③に入ります。お役に立ちますように。次回、お楽しみに!
参考文献:
・小金井信宏(著)『中医学ってなんだろう(1)人間のしくみ』東洋学術出版社 2009年
・内山恵子(著)『中医診断学ノート』東洋学術出版社 2002年
・丁光迪(著)、小金井 信宏(翻訳)『中薬の配合』東洋学術出版社 2005年
・凌一揆(主編)『中薬学』上海科学技術出版社 2008年
・中山医学院(編)、神戸中医学研究会(訳・編)『漢薬の臨床応用』医歯薬出版株式会社 1994年
・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための中薬学』医歯薬出版株式会社 2004年
・翁 維健(編集)『中医飲食営養学』上海科学技術出版社 2014年6月
・日本中医食養学会(編著)、日本中医学院(監修)『薬膳食典 食物性味表』燎原書店 2019年
・許 済群(編集)、王 錦之(編集)『方剤学』上海科学技術出版社 2014年
・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための方剤学』医歯薬出版株式会社 2004年
・伊藤良・山本巖(監修)、神戸中医学研究会(編著)『中医処方解説』医歯薬出版株式会社 1996年
・李時珍(著)、陳貴廷等(点校)『本草綱目 金陵版点校本』中医古籍出版社 1994年
・白川静(著)『常用字解』平凡社 2003年