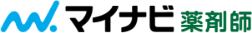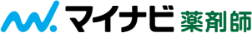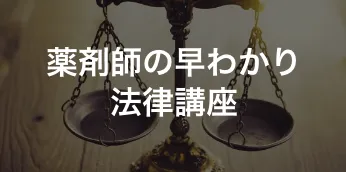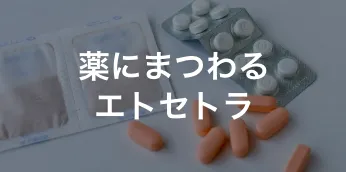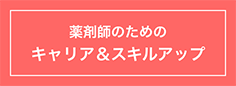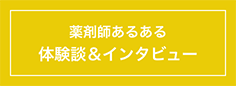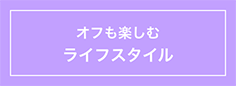学べば学ぶほど、奥が深い薬の世界。もと製薬企業研究員のサイエンスライター・佐藤健太郎氏が、そんな「薬」についてのあらゆる雑学を綴るコラムです。薬のトリビアなどを伝えられると、患者さんとの距離も近くなるかもしれませんね。
医薬の歴史を調べていると、昔はこんなものが薬として使われていたのか、と驚くようなケースに出くわします。今回の主役、クロロホルムもそのひとつでしょう。クロロホルムはサスペンスドラマなどでもよく登場しますから、化学になじみのない方でも、その名前を耳にしたことがおそらくあるのではないでしょうか。
クロロホルムが発見されたのは1830年代のことで、有機化学の開祖の一人であるユストゥス・フォン・リービッヒほか、何人かの科学者が独立に、別々の方法でこれを見つけ出しています。
クロロホルムは「甘い芳香を持つ」と記録されていますが、かなり刺激も強いので、あまり「芳香」という感じはしません。意外なことに、クロロホルムは砂糖の40倍という、非常に強い甘味を持つのだそうです(もちろん味見などしてはいけません)。
そのクロロホルムが、どう医薬として使われていたのでしょうか? ひとつは、その麻酔作用を利用するものです。
人類は、驚くほど古くから外科手術を行ってきました。新石器時代の遺跡からは、頭蓋骨に穴を開ける「穿頭術」が行われた人骨が、多数発見されています。自然治癒した形跡があることから、手術は死後ではなく生前に行われ、患者は頭に穴の空いたまましばらく生存していたと考えられる(!)のだそうです。メソポタミアや古代インドにおいても、結石の除去や鼻の整形など、極めて高度な手術が行われていました。ただ問題は、当時は麻酔薬というものが存在しなかったため、患者は甚だしい苦痛に耐えながら手術を受けるしかなかったという点です。
長年にわたる手術の苦痛から人類が解放されたのは、19世紀半ばになり、亜酸化窒素やエーテルを用いた麻酔手術が行われるようになってからです。ただしこれらには、引火性や気管支への負担などの欠点がありました。そこで他の麻酔薬を探していた医師ジェームス・シンプソンは、クロロホルムに行き当たります。

シンプソンは友人や親戚を集め、クロロホルムを吸引する実験を行いました。実験開始当初は、被験者の女性が「私は天使!」と歌い始め、海軍士官は雄鶏が鳴くような声を挙げ、シンプソン自身は椅子から跳び上がった後に逆立ちし、ドスンと床に倒れるという、実にとんでもない状況に陥ったと記録されています。
こうした苦労(?)の末、シンプソンはクロロホルム麻酔の方法を確立し、無痛分娩にも成功します。当初は教会などから批判も受けましたが、ヴィクトリア女王が2人の子供をクロロホルム麻酔で出産したことで、世にも受け入れられていきました。女王は進歩的な人物で、史上初の化学合成染料で染めたドレスを着用するなど、新しい科学の成果を世に広めるために大いに貢献しています。
ところでクロロホルムは、ドラマや映画の中でもよく登場します。悪漢がハンカチに数滴クロロホルムを染み込ませて、後ろから被害者の口元にぐっと押し付ける。被害者は数秒で意識を失い、その間に拉致されてしまう――というのが、よく見かけるパターンです。
実際のところをいうと、あのシーンはまったくのウソです。クロロホルムに麻酔作用があるのは事実ですが、数分かけて深く吸い込むくらいでないと、意識を失うまでには至りません。また、クロロホルムには毒性もあるため、下手な使い方をすれば深刻な障害が残ることや、死に至る場合さえあります。というわけで、ちょっと試しにクロロホルムを吸い込んでみるなどということは、間違ってもすべきではありません。
これと別に、19世紀末からは、コレラや偏頭痛、不眠症などに効く万能薬として、「クロロダイン」という薬が人気を集めます。明治期に日本を訪れたイギリスの女性旅行家イザベラ・バードも、北海道で出会った女性の病気を、このクロロダインで治したと記録しています。これは、アヘンチンキをクロロホルム水溶液に溶かした実に物騒な薬ですが、少なくとも1930年代まで広く使われていたようです。
こうして長く活躍したクロロホルムですが、その後毒性があることがはっきりしましたので、現在では医薬として使われることはありません。しかし、いろいろな化合物をよく溶かすことから溶媒として重要であり、医薬品研究には欠かせない存在です。かつて自らがスタープレイヤーであったクロロホルムは、今は裏方として医薬品の世界を支えています。