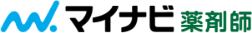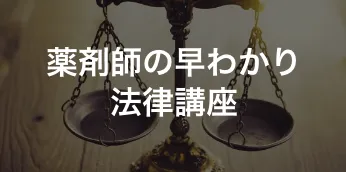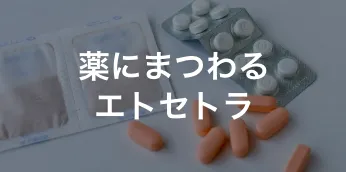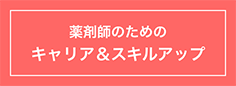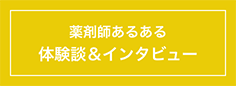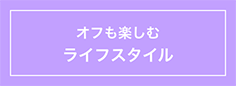学べば学ぶほど、奥が深い薬の世界。もと製薬企業研究員のサイエンスライター・佐藤健太郎氏が、そんな「薬」についてのあらゆる雑学を綴るコラムです。薬のトリビアなどを伝えられると、患者さんとの距離も近くなるかもしれませんね。
みなさんが「医薬」といわれて思い浮かべるイメージは、どのようなものでしょうか? 筆者の場合、赤や青、ピンクや黄色などの、カラフルなカプセルや錠剤です。実際、ウェブで「薬」と入力して画像検索すると、色とりどりで鮮やかな写真やイラストが、たくさんヒットしてきます。
といっても、有効成分である医薬化合物自体は無色であることがほとんどであり、鮮やかな色は着色剤によるものです。数少ない例外が抗炎症薬のアズレン類で、青い色がついている分子です。その名前自体も、青色を意味する「azul」に由来しています。青いユニフォームをまとったサッカーイタリア代表の愛称「アッズーリ」、フランスの有名な観光地・コートダジュールなども、これと同じ語源からきている言葉です。
カモミールなどのハーブを加熱蒸留すると、青く色づいた精油が得られます。これは、植物に含まれるテルペンが熱によってアズレンに変化したものです。アズレンには抗菌作用、抗炎症作用があることが古くから知られ、民間薬として活用されてきました。現在でもアズレンは胃薬やうがい薬などに配合されており、身近な薬のひとつとなっています。
赤い薬としては、アントラサイクリン系抗がん剤があります。この薬の分子構造は、アカネから得られる赤色色素アリザリンとよく似ているため、強烈な赤色に見えるのです。尿まで赤く着色してしまうため、あらかじめ注意しておかないと、患者さんが驚いてしまう薬です。
それ自体が無色でも、体内で代謝を受けて色のある化合物に変化し、尿が着色してしまう薬もあります。抗がん剤フルタミドは、尿が琥珀色や黄緑色に着色してしまうことがありますし、抗生物質セフジニルは鉄イオンと結びつき、尿や便が赤く着色するケースがあります。その他、汗や唾液、コンタクトレンズが着色するような薬剤も存在します。
なぜ薬に色をつける?
しかし、ほとんどの医薬は本来無色です。なぜそこに、わざわざ色を着けるのでしょうか? この傾向が始まったのは1960年代のことで、それほど昔のことではありません。1975年頃からはソフトジェルのカプセルが普及し、それに合わせてカラフルな薬が一気に広まってゆきます。またこのころに各種の合成着色料が普及したことも、その背景にありそうです。

日本の薬にあまり派手なものが多くないのは、着色料のどぎつい色があまり好まれないせいかもしれません。アメリカなどは着色料にあまり抵抗のない国柄なのか、昔から食品や飲料なども派手な色彩のものが市場にあふれていますから、鮮やかな色彩の薬も受け入れられやすいのでしょう。
こうしてカラフルな医薬が広まった理由のひとつは、他社の薬との差別化を図ることでしょう。特に海外では、バイアグラといえば青いひし型の錠剤のイメージが定着していますし、胃酸分泌抑制薬ネキシウムは「パープル・ピル」(紫の薬)のキャッチフレーズで有名であるなど、色彩が医薬のイメージと強くリンクしています。
筆者が出席したある新薬のイベントでは、発表用スライドの背景色から社員のネクタイの色までがすべて、新薬のイメージカラーに統一されていて驚いたことがあります。自由競争の国アメリカでは、薬の色もマーケティングにおける重要な要素であるようです。
しかし医薬に色が着けられる最大の理由は、患者さんの印象に残り、飲み忘れることがないようにするためです。筆者にも経験がありますが、きちんと薬を飲み切る患者さんは、思うより少ないものです。さまざまな調査でも、半数以上の患者が薬を飲み忘れた経験を持つというデータが出ています。となれば、強烈な色で忘れぬよう印象づけるのも、悪くない手段でしょう。
別の調査によれば、薬剤についている色は、薬の味に対する印象に結びついているといいます。黄色い薬は塩味、ピンクの薬は甘い味、青や白は苦味を連想させるというデータが出ています。すると、特に子供向けの薬はピンクにしておけば、かなり抵抗感を減らせるのかもしれません(もっともこれはインドでの調査結果であり、食文化などによって色の印象はずいぶん違いそうです。日本なら、黒っぽい正露丸のような色が、一番苦味を連想させるかもしれません)。
ともあれ、どんな薬も飲まなければ絶対に効きませんから、見た目というのは薬にとって想像以上に大きな要素です。いかにも効きそうな色というのがわかれば、よりプラセボ効果を引き出して、効能を高めてくれることもありえるでしょう。研究者は薬の作用や体内動態ばかりに目を向け、味や見た目などは考えもしませんが、実は大いに工夫の余地がある領域かもしれません。