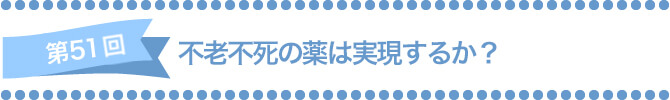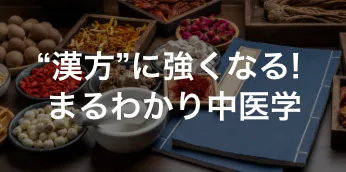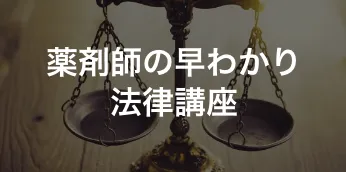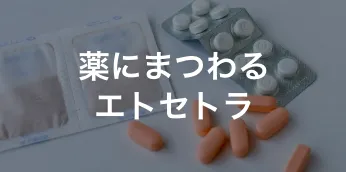学べば学ぶほど、奥が深い薬の世界。もと製薬企業研究員のサイエンスライター・佐藤健太郎氏が、そんな「薬」についてのあらゆる雑学を綴るコラムです。
Googleが設立した長生き研究の会社、赤ワインの抗酸化成分「レスベラトロール」、線虫の寿命が延びた「ピロロキノリンキノン」etc.今回は、サイエンスライター佐藤健太郎氏が“不老不死の薬”について考察します。

Googleが設立した長生き研究の会社とは
今回は新年ということで、めでたい話題――長生きのお話でもしてみましょう。
不老長寿こそが人類の究極の願いであることは、今も昔も変わりはありません。秦の始皇帝が中国を統一した後、不老不死に執着して各地に臣下を派遣し、これを探させた話は有名です。日本にも徐福という人物が秘薬を求めて訪れたといわれ、各地に徐福来航伝説が残されています。
現代でも、Googleが「Calico(キャリコ)」という会社を設立し、長寿に関する研究を進めさせています。絶対的な富と力を得た者が、最後に目指すのは不老不死というのは、古今東西同じであるとみえます。
しかし、いくら科学技術が発達しているとはいえ、不老不死などということが可能なのでしょうか?
もちろん「不死」の方はそう簡単ではないでしょうが、「不老」の方は徐々に実現してきているともいえます。以前に比べて、60代や70代の人たちがずいぶん若く元気であるのは、みなさんも感じておられると思います。
たとえば手塚治虫が1974年ごろに描いたマンガでは、60歳の女性が非常に老け込んだ姿に描かれていることに驚きます。現代の60歳と見比べると、まさに隔世の感があります。
こうしたところを見ると、このわずか40年あまりで、日本人は10年か15年分くらいのアンチエイジングに成功しているといってもよいと思えます。食事や住環境の変化など、原因はいろいろ考えられそうですが、この先さらに「不老」傾向が進む可能性は十分にありそうです。
赤ワインは不老不死の妙薬?
では医薬によってさらなる不老を目指すことはできるのか?
すでに、いろいろなアプローチが行なわれています。有名なのは、赤ワインの成分として注目されたレスベラトロールでしょう。すでにサプリメント等として販売されていますから、ご存知の方も多いと思います。
フランス人は高脂肪の食事を摂り、喫煙率も比較的高いにもかかわらず、虚血性心疾患にかかる率が他国に比べて低いというデータがあります(フレンチ・パラドックス)。
この原因となっているのが赤ワインであり、中でもレスベラトロールが要因ではないかと考えられたのでした。
レスベラトロールは、サーチュインというタンパク質に作用し、これが各種遺伝子の調節を行なうことで寿命を延ばすという理屈です。
世界のワイン愛好者を大いに喜ばせたこの仮説ですが、その後否定的な結果も出ています。また、レスベラトロールの作用の研究者が書いた論文に、多数の捏造箇所が指摘されたような一件もありました。
臨床試験なども進んでいますが、何しろ老化に関する研究は長い時間がかかり、はっきりした結論は出ていません。副作用や至適用量なども判明していませんから、レスベラトロールのサプリメントなどを推奨できる状況ではないでしょう。
レスベラトロールには抗酸化作用もあり、これも注目された一因でした。DNAや各種タンパク質などを破壊し、機能を失わせる活性酸素を除くことで、老化を防止できるというロジックです。
しかし近年では、抗酸化作用を持つビタミンを摂取しても、寿命延長につながらないことが大規模調査によってわかっており、「老化の原因は活性酸素」という単純な考えはほぼ否定されています。
ピロロキノリンキノンが寿命を延ばす?
最近、名古屋大のグループによって、ピロロキノリンキノン(PQQ)という化合物を投与することで、線虫の寿命を延ばせることが示されました。
PQQは、細胞膜上で低レベルの活性酸素を発生させ、これが生体防御に関わる遺伝子を活性化して寿命を伸ばすと考えられています。
このように、「活性酸素=悪」というような単純な考えではなく、きめ細かく捉えていかねば不老長寿は目指せないということになります。
老化や死というのは、一本道のように単純に肉体が衰えていくものではなく、もっと複雑な過程と考えられます。
たとえば、人間は年をとると皮膚にシワができ、固くなります。これは、皮膚を作るコラーゲン鎖の間に橋渡しの結合が増えてゆき、柔軟性を失った結果です。
また、細胞は基本的に次々に壊れては作られ、どんどん入れ替わっています。しかし、脳細胞や心筋細胞のように、入れ替わらないものもあります。不老不死を目指すのであれば、これらの細胞の補充を行なわねばなりません。
さらなる難関として、DNA複製の際に出るミスの蓄積があります。これらは、がんの要因でもありますし、ミトコンドリアDNAの複製エラーはエネルギー産生の不全を招きます。また、細胞内外に蓄積する老廃物の除去なども課題となってきます。
このように、いろいろな形で進んでゆく老化現象を、それぞれに適した手段で食い止めるとうのが、多少なりとも現実的な「不老不死」への道なのかもしれません。
もっとも、それで本当に不老不死に近づくのか、もし実現したらいったい何が起こるのか――それは、全くの未知数ではあります。