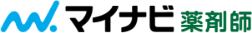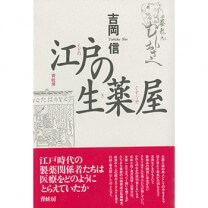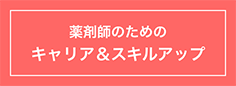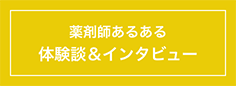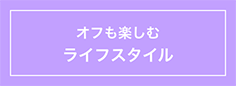現代では薬局で薬が販売され、誰もが気軽に自分に必要な薬を手にすることができます。このような「売薬」の文化は、いつから始まったのでしょうか? 本書によると、現在の薬局のような店が登場したのは江戸時代のこと。当時の薬局は「生薬(きぐすり)屋」などと呼ばれ、幅広い商品が扱われていたそうです。
もともと、生薬を刻んだり、それに手を加えて薬を作ったりするのは医師の仕事でした。生薬屋が医師に代わってそれらの仕事を行い、薬を販売することによって、一般の人も手軽に薬を利用できるようになったのです。
江戸時代に薬の販売が盛んになった背景には、身分制度も影響していると著者はいいます。当時、医者にかかることができたのは階級の高い一部の人だけ。多くの庶民は病気になっても自分で治すしかありませんでした。そんな「自分の病気やけがは自分で治す」というセルフメディケーションの意識があったからこそ、売薬が多くの人々に必要とされていたのです。

本書には薬を販売するにあたっての商人たちの工夫や努力についても、詳細に書かれています。薬の広告の発祥は、江戸の戯作者・浮世絵師の“山東京伝”が著作活動のかたわらに経営していた生薬屋だとあります。京伝は自著の余白に自分の経営する生薬屋で販売する薬「読書丸」の効能を掲載しました。それによってこの薬を人気商品に押し上げ、さらには挿絵と文章で構成された、CMの大元ともいえるような広告も製作していたそうです。
そのほかにも薬の宣伝では、行商人が三度笠に合羽(かっぱ)の旅人姿で町を練り歩き、ユニークな呼び込みで薬を売る「藤八五文(とうはちごもん)」や、人通りの多い場所で行われる熊の肝の膏薬(こうやく)販売も巧みな口上で多くの人をひきつけました。
江戸時代に薬の販売に携わってきた人々の姿勢には「商人」として、薬を購入するお客さんにどうアピールするか、どのように商品の魅力を伝えたらよいかと試行錯誤する姿勢がうかがえます。
もちろん、現代の医療においては薬の効果や副作用のリスクといった患者さんへの情報提供は欠かせないものです。しかし、それと同時に商品である薬に親しみを持ってもらい、困ったときに店を訪れてもらえるようにすることは、現代の薬局にも求められていることといえるのではないでしょうか。