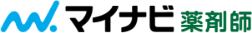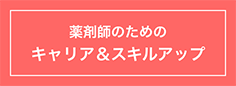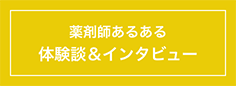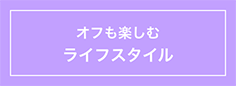映画・ドラマ

「たまには仕事に関連する映画を見てみようかな」と感じたことはありませんか? 医療や病気に関する映画・ドラマ作品は数多くありますが、いざとなるとどんな作品を見ればいいのか、迷ってしまう人もいるのでは。このコラムでは看護師ライターの坂口千絵さんが、「医療者」としての目線で映画・ドラマをご紹介します。

vol.5 「華岡青洲の妻」(1967年・日本)
華岡家に嫁いだ加恵は、夫となる雲平(のちの青洲)が医学の修業で留守のため、三年間、姑だけに仕えた。ようやく戻った雲平の前で、姑・於継は加恵につらくあたるようになり、妻・加恵もいつしか姑に憎しみを抱く。女ふたりの対立が深まる中、雲平は麻酔薬の研究に憑かれたように打ち込んでいた。ある日、於継は自分を麻酔薬の人体実験に使ってくれと言い出す。驚いた加恵もまた同じことを申し出る。危険を顧みず、自らの身体を実験台に差し出そうとするふたりを前に、青洲の決断は……。
有吉佐和子の大ベストセラー小説「華岡青洲の妻」を映画化した本作は、市川雷蔵(青洲)、若尾文子(妻・加恵)、高峰秀子(母・於継)という最高のキャスティングで、増村保造監督のメガホンのもとに“女の生き方”を描く。

主人公の華岡青洲は1804年、世界で初めて全身麻酔を用いた乳がん手術を成功させたと同時に、麻酔薬の「通仙散」を開発した人物として知られています。
欧州ではすでに乳がん手術が行われていましたが、まだ全身麻酔薬がない時代。患者の苦痛はどれほどのものか、想像を絶するものがあります。
青洲は医師としての修業中に読んだ書物から、外科的手術における最重要課題が麻酔法の確立であることを知ります。その後、約20年もの歳月をかけて研究を重ね、麻酔薬の「通仙散」を開発しました。
「通仙散」は、チョウセンアサガオやトリカブトなど数種類の薬草を配合した内服薬。毒性が強く、扱いは非常に難しかったといわれています。内服から手術開始が可能となるまでに約6時間、さらに患者が意識を回復するまでに6~8時間と、かなり長い時間がかかるため、青洲が用いた麻酔法は幕末から明治維新の頃にかけて次第に廃れていきました。
しかし「通仙散」が開発されてから、現代の麻酔の起源であるエーテルを用いた手術が行われるまでに40年もの年月を要したことを考えると、青洲の業績は偉大であるといえるのではないでしょうか。
「通仙散」が麻酔薬として正式に用いられるまでには数十人の人体実験が行われ、母の於継と妻の加恵も参加したといわれています。息子のため、夫のために身を捧げた母と妻の美談のようですが、そこで繰り広げられたのは壮絶なバトル。二人がまるで競うかのように自分が実験台になることを申し出るシーンは、この作品の見どころのひとつです。青洲は、われこそはと争う二人の姿に呆然。自分の命を引き換えにしてもと張り合う「嫁と姑の壮絶な確執」には、青洲ならずとも目を見張るものがあります。
加恵と於継の関係性を長きに渡って目の当たりにしてきた青洲の妹は、加恵にこう言います。
「私の一生では嫁にいかなんだのが、何にも代えがたい仕合せやったのやしてよし。嫁にも姑にもならないで済んだのやもの……」
第三者に“自分は結婚しなくて幸せだった”とまで思わせてしまうのですから、対立の根深さは相当なものです。
お互いに決して本心を悟られないように振る舞う於継と加恵のやりとりは、どこまでが表の顔で、どこからが裏の顔なのかがわかりにくく、背筋が寒くなるような凄みがあります。
嫁姑の争いをよそに、ひたすら麻酔薬の開発に没頭した青洲は、全身麻酔での手術の成功をきっかけにその名が全国に知れ渡るようになります。青洲はその後、医塾「春林軒」を設立し、生涯を終えるまでに1000人以上の門下生を育て、医学の発展に大きく貢献しました。
青洲の情熱や努力もさることながら、於継と加恵の献身なくしては麻酔薬の誕生はありえませんでした。現代の新薬開発のプロセスでも、被験者の方の協力が欠かせませんが、安全性には最大限配慮されるのが通常です。青洲が研究に没頭した江戸時代の治験は、命を落とす危険が伴っていたこと。そうした歴史の積み重ねがあって現代の医薬があることに、あらためて感じ入りました。
あわせて読みたい記事