薬の一包化は、患者さんの服薬コンプライアンスの向上に役立ちます。しかし、一包化にはデメリットもあるため、薬剤師はメリット・デメリットを把握し、適切に対応することが求められるでしょう。本記事では、薬の一包化の概要や対象患者さん、一包化の流れ(やり方)、一包化加算(現・外来服薬支援料2)について解説するとともに、メリットやデメリットについてもお伝えします。加えて、一包化におけるヒヤリハット事例も紹介します。

- 1.一包化とは?
- 1-1.一包化の対象患者さん
- 2.一包化の流れ
- 2-1.一包化指示の確認
- 2-2.処方内容の確認
- 2-3.一包化を行う
- 2-4.分包の内容を確認
- 3.一包化のメリット
- 3-1.服薬が簡単になる
- 3-2.管理の手間が少ない
- 3-3.服薬コンプライアンスが向上する
- 3-4.PTPシートの誤飲対策になる
- 4.一包化のデメリット
- 4-1.一包化に時間がかかる
- 4-2.患者さんの薬識が低下しやすい
- 5.一包化加算(現・外来服薬支援料2)とは?
- 6.一包化におけるヒヤリハット事例
- 6-1.1回2錠のところ1錠で調剤
- 6-2.吸湿性の高い医薬品を一包化
- 7.一包化は服薬コンプライアンスの向上やシートの誤飲対策に寄与する
1.一包化とは?
一包化とは、複数の薬剤を分包して、服用時点ごとに一つにまとめることです。以下のような処方がされている場合に一包化を行うと、外来服薬支援料2(旧・一包化加算)が算定できます。
● 用法が同じ3種類以上の内服用固形剤
一包化は、薬剤師が治療上の必要性があると判断した場合に、処方箋の受付ごとに行うことができます。ただし、医師の指示がない場合は、一包化を行う旨を医師に伝え、了解を得なければなりません。
参照:調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省
1-1.一包化の対象患者さん
一包化の対象となる患者さんとして、以下のような人が挙げられます。
● 自身で服薬管理をするのが難しい
● 服薬コンプライアンスが悪い
手指が不自由な人や、視力が低下している人、パーキンソン病の人などはシートから錠剤を取り出すのが難しい場合があります。認知機能が低下している場合には、家族などのサポートが必要となるケースがあるため、管理者の負担軽減を目的に一包化をすることもあるでしょう。
また、認知機能に問題ないものの、飲み忘れや飲み間違いなどの疑いがある患者さんもいます。そういった場合には、服薬管理が容易になるよう一包化をすることがあります。
参照:調剤(その3)|中央社会保険医療協議会
2.一包化の流れ
ここでは、一包化の流れについて解説します。

2-1.一包化指示の確認
一包化を行うためには、医師の了解を得る必要があります。そのため、まずは処方箋に一包化の指示が入っているかを確認しましょう。医師の指示が入っている場合には一包化を行います。
患者さんや家族などが一包化を希望するものの医師の指示がない場合には、医師へ問い合わせを行い、一包化の了解を得ます。
2-2.処方内容の確認
医薬品の中には、湿気や光に弱いといった理由で、一包化に向かない薬があります。そのため、一包化をする前に、一包化が難しい処方薬があるかをチェックしましょう。
乾燥材や遮光袋などでの対応が難しいと判断した場合は、該当する医薬品のみをシート管理にしたり、一包化が可能なジェネリック医薬品を検討したりします。処方変更でしか対応できない場合は、医師へ問い合わせを行います。
2-3.一包化を行う
処方内容の確認が終わったら、一包化を行います。自動分包機を使用する場合は、あらかじめ分包機にセットされている医薬品以外の処方薬を必要数集めましょう。自動分包機がない場合は、すべての処方薬の必要数を集めます。
処方薬の準備ができたら、集めた処方薬を分包機のカートにセットして分包します。分包機によっては、「朝食後」などの用法や服用日、患者氏名などが印字できます。印字をする場合は、分包する前に分包機に情報を入力しましょう。
2-4.分包の内容を確認
処方薬が分包されたら、処方内容と分包内の錠剤に相違がないかを確認します。錠剤・カプセル剤などの「個数」と薬に印字されている「識別コード」を一包ずつすべての処方薬で確認し、間違いなく一包化されていることをチェックします。
合わせて、ゴミやホコリなどが入っていないかも確認しましょう。
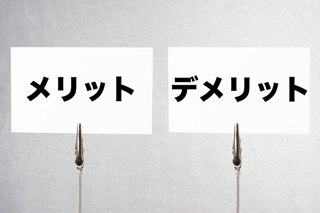
3.一包化のメリット
一包化には、さまざまなメリットがあります。それぞれのメリットについて詳しくお伝えします。
3-1.服薬が簡単になる
一包化を行うと、一包に服用時点で飲まなければならない薬がまとめられているため、患者さんが飲み間違えたり、飲み忘れたりすることを防げます。
複数の処方薬をシート管理している場合、自分で飲む薬の種類や錠数を選ばなければなりません。そのため、一つだけ飲み忘れたり、飲んでいないと思い込んで重複して飲んでしまったりすることがあります。薬をシートから出しているうちに一つだけ落としてしまい、落としたことにも気づかず服用する可能性もあるでしょう。そういった服用の手間やリスクを軽減できる点が、一包化のメリットです。
3-2.管理の手間が少ない
シートで処方薬を管理していると、用法用量ごとに薬袋を分け、服用する度に間違いがないよう確認しなければなりません。一包化であれば、「朝食後の薬袋」「昼食後の薬袋」といった形で管理ができます。処方薬一つひとつを管理する必要がないため、管理の手間が少なくなるでしょう。
また、家族やヘルパーさんなどが服薬介助をしている場合、負担を軽減できる点もメリットです。
3-3.服薬コンプライアンスが向上する
服薬コンプライアンスが向上するのもメリットです。一包化は、服用する用法を1袋選び、開封してそのまま服用するため、管理から服用までの手間がかかりません。1種類ずつ用法用量を確認してシートから出す作業がなく、服薬管理が簡単になります。
そのため、飲み間違いや飲み忘れ、重複服用を防ぎやすくなり、服薬コンプライアンスの向上が期待できるでしょう。
🔽 服薬コンプライアンスについて解説した記事はこちら
3-4.PTPシートの誤飲対策になる
患者さんの中には、服薬管理を簡単にするために、1錠ずつシートを切り分けて、お薬ケースやお薬カレンダーなどに保管している人がいます。シートを切り分ける管理法は、服用時点ごとに薬を用意する手間が省け、飲み忘れなどにも気が付きやすいのがメリットです。
しかし、服用時にシートから薬を出さずに、シートごと服用してしまう事例が問題となっています。食道などに留まったシートを内視鏡で取り除いた事例などが複数報告されていることから、一包化はPTPシートの誤飲対策になる点もメリットといえます。
参照:調剤(その3)|中央社会保険医療協議会
参照:【4】一包化調剤に関するヒヤリ・ハット|日本医療機能評価機構
4.一包化のデメリット
一包化のデメリットには、薬局で一包化をするのに時間がかかる点や、患者さんの薬識が低下しやすい点が挙げられます。それぞれについて詳しくお伝えします。
4-1.一包化に時間がかかる
一包化は、薬をシートから1錠ずつ取り出して分包機にセットし、分包後には一包ずつ中身の確認を行います。そのため、すべての工程が終了するまで、ある程度の時間が必要です。処方日数や処方数が多いほど、患者さんの待ち時間が長くなってしまう点はデメリットでしょう。
また、薬局が混んでいたり、処方薬が足りなかったりすることで待ち時間が長引くと、クレームにつながるケースもあります。一包化をする場合は、あらかじめ時間がかかることや、準備ができるまでの目途を伝えることが大切です。
🔽 薬局の待ち時間が長いときの対応方法について解説した記事はこちら
4-2.患者さんの薬識が低下しやすい
一包化をすると、複数の薬がそのまま入っている状態となるため、どれが何の薬なのか分かりにくくなります。用法だけを確認してそのまま服用すればよいため、間違いなく飲むために薬情を確認するといった機会も少なくなりがちです。そのため、一包化をする患者さんの薬識が低下しやすいのはデメリットといえるでしょう。
もちろん、一包化をしている患者さんにも、薬の色と形で薬効や薬の名前などを答えられる人はいます。しかし、「記載された用法通りに分包品を飲んでおけばよい」と考える患者さんも一定数います。
それぞれの薬効や注意点について理解し、どの薬にどんな副作用があるかを把握することは、薬物治療を安全に行うためにとても大切です。そのため、一包化を行う患者さんには、薬情を錠剤の写真にしたり、指導時に薬効や副作用を確認したりするなどの丁寧な情報提供を行う必要があるでしょう。
参照:調剤(その3)|中央社会保険医療協議会
5.一包化加算(現・外来服薬支援料2)とは?
外来服薬支援料2(旧・一包化加算)とは、患者さんの服薬コンプライアンスを向上させることを目的に、一包化を行った際に算定できる薬学管理料です。
前述の通り、一包化は以下のような処方について、薬剤師が必要性を判断し、医師の了解のもとで行うことができます。
● 用法が同じ3種類以上の内服用固形剤
外来服薬支援料2は、処方箋受付1回につき1回算定でき、算定点数は処方日数によって異なります。また、外来服薬支援料2を算定する場合は、内服薬の剤数のカウント方法について理解しなければなりません。
外来服薬支援料2における剤数の考え方や計算方法について詳しく知りたい場合は、次の記事をご覧ください。
🔽 外来服薬支援料2(旧・一包化加算)について解説した記事はこちら
6.一包化におけるヒヤリハット事例
日本医療機能評価機構で公表している一包化のヒヤリハット事例を参考に、薬局で起こりやすい事例を紹介します。
6-1.1回2錠のところ1錠で調剤
A錠が1日1回、1回2錠で処方されている薬剤について、1回1錠で一包化を行い、監査者も気が付かず患者さんへ渡ってしまうケースです。こういった場合では、患者さんからの連絡や棚卸で、調剤ミスに気が付くことが多いでしょう。
日本医療機能評価機構に集まったヒヤリハット事例では、患者さんに残薬があったために服用前に調剤薬の回収ができたケースや、状態が悪化し入院を余儀なくされるケースがありました。調剤ミスは患者さんの健康を著しく害す可能性があります。調剤ミスに気が付いた場合は、早急に連絡して謝罪し、対応方法について説明を行わなければなりません。
6-2.吸湿性の高い医薬品を一包化
バルプロ酸ナトリウムやアスパラギン酸カリウムなどは、製品によって吸湿性が高く一包化に向いていないものがあります。一包化に向いていない薬剤を把握していなかったために、一包化して患者さんに渡してしまうというヒヤリハット事例が紹介されていました。
吸湿性の高い薬を一包化すると、安定性が保てず十分な効果が得られない可能性があります。扱っている医薬品の中で一包化に向いていないものがある場合は、あらかじめピックアップしてスタッフと共有したり、分包機の近くに一覧を置いたりするとよいでしょう。
参照:薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業:事例検索|日本医療機能評価機構
参照:【4】一包化調剤に関するヒヤリ・ハット|日本医療機能評価機構

7.一包化は服薬コンプライアンスの向上やシートの誤飲対策に寄与する
一包化は服薬管理が簡易化するため、服薬コンプライアンスの向上が期待されます。また、患者さんがシートから薬を出すのを忘れて、シートごと飲んでしまうリスクも回避できます。患者さん以外の家族やヘルパーさんなどが服薬介助をする際の負担軽減も期待できるため、一包化にはさまざまなメリットがあるといえるでしょう。
一方で、一包化をするのに時間が必要な点や、患者さんの薬識が低下しやすい点などはデメリットです。薬剤師は、一包化にかかる時間について患者さんから了承を得るとともに、患者さんが主体的に薬物治療に参加できるよう情報提供や服薬指導を行う必要があります。

薬剤師ライター。2児の母。大学卒業後、調剤薬局→病院→調剤薬局と3度の転職を経験。循環器内科・小児科・内科・糖尿病科など幅広い診療科の経験を積む。2人目を出産後、仕事と子育ての両立が難しくなったことがきっかけで、Webライターとして活動開始。転職・ビジネス・栄養・美容など幅広いジャンルの記事を執筆。趣味は家庭菜園、裁縫、BBQ、キャンプ。
あわせて読みたい記事





































