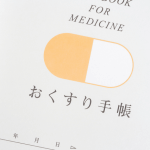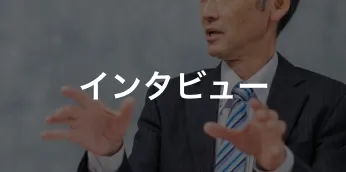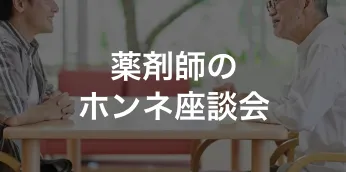薬剤師・薬局の仕事は、一般の利用者の立場からは分かりにくい部分も多いかもしれません。薬剤師・薬局に関する素朴な疑問について、薬剤師さんに詳しく解説してもらいました!
薬剤師って全部の薬の情報を暗記しているの?
勤務先で取り扱いのある医薬品は網羅していますが、それ以外は添付文書などで確認しています

薬剤師としては、「世の中にある全部の医薬品の情報が頭に入っている」とカッコいいことを言ってみたいものですが、そんなわけはありません。
現在、医療機関などで保険診療に使われている医療用医薬品は、全部で約1万3000品目もあります。
参照:薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について|厚生労働省
調剤薬局なり病院の薬局なりで取り扱っている医薬品のことを「採用薬」と呼んでいますが、その種類や数は医療機関によって異なり、2020年度調査では、一般病院の平均で内服薬596、外用薬214、注射薬356という結果でした。
参照:医療機関における医薬品採用と適正使用に関する実態調査2020|J-STAGE
たいていの薬剤師は、自分の勤務先の医薬品については、ほぼ網羅的に知っています。そうでないと仕事になりません。もちろん、忘れてしまって資料を見返すこともありますが、そのたびに記憶は強化されていきます。
しかし、それ以外の医薬品の情報が必要になることも多々あります。例えば、「患者さんに質問された」「お薬手帳に記載がある」「(病院で)入院時に患者さんが他院で処方されている医薬品を持参した」といったケースです。これらの医薬品については、今飲んでいるものと作用の重複はないか、一緒に飲んで問題ないかを判断する必要性が出てきます。こうした場合、薬剤師は医薬品の基礎情報「添付文書」に立ち帰ります。
添付文書とは、使用上の注意、用法・用量、服用した際の効能や副作用などを記載した書面のことです。これは医師をはじめとした医療従事者など、製品を使う人を対象に作成されており、患者さんの安全のため、医薬品を正しく適切に使う際の基本となる重要な公文書です。
添付文書には、上記の情報の他、飲んではいけない人、飲む際に注意を要する人などの情報もあります。添付文書の情報は、医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトから検索すれば入手できますし、各製薬会社のウェブサイトでの検索も可能です。それらを見て、薬剤師は自施設で取り扱いのない、よく知らない医薬品の情報を得るのです。
まれに、持参薬の中には、包装のない裸の錠剤やカプセル剤が混ざっていることもありますが、その場合は本体に記載のある会社コードやマーク、数字から製品を特定していきます。
参照:錠剤・カプセル等の会社コード一覧表|日本製薬団体連合会
医薬品の数は膨大なので、人により得手不得手があるのは仕方のないことかもしれません。薬剤師が苦手な医薬品として比較的よく耳にするのは、抗がん剤と漢方薬です。
苦手な理由は、抗がん剤はひとえに理解が難しいことに尽きると思います。がん専門薬剤師などの資格を取得していて、日々携わっている人は別にして、関与する機会が少ない薬剤師にとっては、深い理解に至るまではハードルが高いのが現実です。
また、漢方薬については大学でも十分に時間をかけては学びません。したがって、自分で勉強するしかないのですが、処方される医薬品に対して漢方薬の占める割合は低く、積極的に学ばなくても日常業務ではあまり困らないという事情があります。
とはいえ、患者さんに質問されたり、持参薬に入っていたりしたら、専門家としての力を発揮する必要があります。必要な情報はほとんどすべて添付文書にありますが、ごくまれにない場合でも、製薬会社へ問い合わせるなどの方法で入手し、必要な部署へ伝えるよう努力しています。
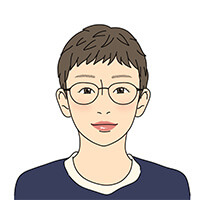
東北大学薬学部卒業後、ドラッグストアや精神科病院、一般病院に勤務。現在はライターとして医療系編集プロダクション・ナレッジリングのメンバー。専門知識を一般の方に分かりやすく伝える、薬剤師をはじめ働く人を支えることを念頭に、医療関連のコラムや解説記事、取材記事の制作に携わっている。
ウェブサイト:https://www.knowledge-ring.jp/