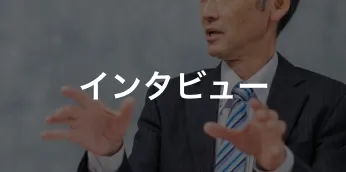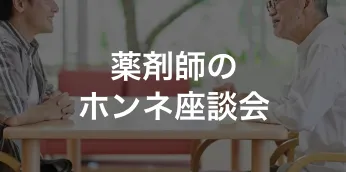薬剤師・薬局の仕事は、一般の利用者の立場からは分かりにくい部分も多いかもしれません。薬剤師・薬局に関する素朴な疑問について、薬剤師さんに詳しく解説してもらいました!
病院でもらった処方箋があれば、どこの薬局でも薬がもらえるの?
処方箋を持って行けば日本全国どこの薬局でも薬はもらえますが、在庫がない場合もあります

誰もが一度は抱きそうな疑問ですね。病院やクリニックの近くには、たいてい調剤薬局がありますが、これは患者さんの利便性を考えてのこと。「薬は必ずここでもらわないといけない」ということではありません。
基本的に、処方箋を持っていれば、どこの薬局に行っても薬をもらえます。しかし、例えば内科と外科で処方される薬は同じではないため、「近くに何科の医療機関があるか」によって在庫している薬は多少なりとも違います。そのため、患者さんが求める薬が在庫されていない場合もあるのです。
そうした時は、処方箋を受け付けた薬局が近隣の別の薬局に手配する(待ち時間が長くなる可能性がある)、医薬品卸に頼む(入手が翌日以降になる)などして対処します。
参照:薬局間における医療用医薬品の譲受・譲渡に関するガイドライン【概要】|日本薬剤師会・日本保険薬局協会・日本チェーンドラッグストア協会
医療機関の近くにある「門前薬局」ならたいていの薬は在庫していますが、複数の医療機関にかかっている場合の重複や相互作用のチェックが常にできるとは限りません。マイナ保険証を使い薬剤情報の提供に同意しているか、通信状態が良好か――といったハードルがあるからです。そうした時は自宅近くの「かかりつけ薬局」が便利です。
薬剤師としては、自宅近くにかかりつけ薬局を持ち、在庫がない場合は取り寄せてもらうことをお勧めします。遠方の医療機関にかかった場合は、処方箋をかかりつけ薬局へファクス送信してもらいましょう。送信代がかかる場合もありますが、薬局に到着する頃には調剤済みで、待ち時間の短縮になります。私の経験では「頼めば送ってくれる場合」と「自分で送る場合」がありますが、送信代はどちらも10円でした。
医師が処方箋を発行し、薬剤師が調剤し、患者さんが薬を受け取る制度を「医薬分業」と呼びます。この制度の目的は、医師と薬剤師が各々の分野で専門性を発揮し、医療の質の向上を図ることです。薬剤師が処方内容のチェックをすることで適切な薬物療法が行える、丁寧な服薬指導を行える、待ち時間が短縮されるなどの他、飲み残しのある薬を減らすなど残薬の解消にも貢献しています。
かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師の制度がスタートしたのは2016年。厚生労働省により「患者のための薬局ビジョン」が策定されたことに由来します。かかりつけ薬剤師の役割は、患者さんの薬の情報を一元管理することです。「薬局ビジョン」では、2025年までにすべての薬局がかかりつけ薬局としての機能を持ち、地域住民による主体的な健康の維持・増進を支援する機能を発揮すると謳われています。
さらに、休日を含めて電話相談や調剤などに24 時間対応する体制を確保すること、かかりつけ医をはじめとする医療機関などと連携強化することなど、薬局には多くの役割が期待されています。
参照:患者のための薬局ビジョン~「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ~|厚生労働省
「薬局ビジョン」の策定から10年がたち、皆さんのご自宅近隣の薬局の状況はいかがでしょうか。ちなみに、2023年の医薬分業率(処方箋受取率)は前年度比3.9%増の80.3%で、初めて80%を突破しました。
かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師を持つのは、それほど難しいことではありません。行きつけの調剤薬局に「かかりつけ薬局の機能」があるかどうか確認し、あれば同意書を提出するだけ。60円または100円程度の負担(かかりつけ薬剤師指導料)が増えるものの、相応のメリットを享受できるはずです。
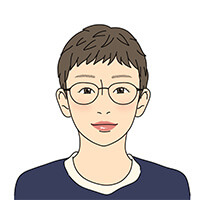
東北大学薬学部卒業後、ドラッグストアや精神科病院、一般病院に勤務。現在はライターとして医療系編集プロダクション・ナレッジリングのメンバー。専門知識を一般の方に分かりやすく伝える、薬剤師をはじめ働く人を支えることを念頭に、医療関連のコラムや解説記事、取材記事の制作に携わっている。
ウェブサイト:https://www.knowledge-ring.jp/