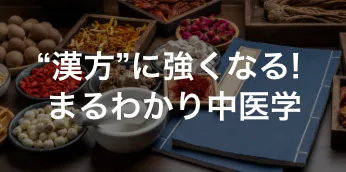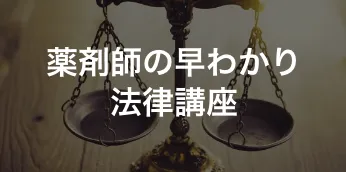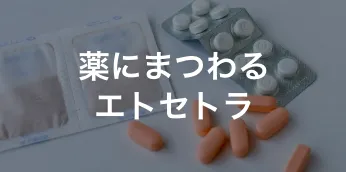知れば知るほど奥が深い漢方の世界。患者さんへのアドバイスに、将来の転職に、漢方の知識やスキルは役立つはず。薬剤師として今後生き残っていくためにも、漢方の学びは強みに。中医学の基本から身近な漢方の話まで、薬剤師・国際中医師の中垣亜希子先生が解説。
第115回 肝気を巡らせる養生20選~くよくよ・イライラに気づいたらやることリスト
第113回・第114回と、ストレスがかかったときに心と体に起こるパターンを学んできました。ストレス(主に精神的なもの)は、肝の気の巡りを悪くし、肝気鬱結(かんきうっけつ)を引き起こし、心身にさまざまな不調となって現れます。
今回は、肝鬱シリーズ対策編ということで、「肝鬱になりやすい人の特徴」と「肝鬱さんに向いた養生法」について解説します。ご自身の内面と照らし合わせながら参考にしてみてください!
- ストレスは肝気の巡りを悪くする
- 生きていれば、誰でも肝鬱になることはある
- 肝鬱になりやすい人の特徴2つ
- 肝鬱による症状の特徴
- 肝気の巡りをよくする食養生
- 気の巡りをよくする食材の例
- 上手に気分転換することが大切! 肝気を巡らせる養生
- 1. 大声で叫ぶ・歌う
- 2. ほどよく筋肉を動かす、有酸素運動をする
- 3. 健康的に汗をかく
- 4. 自然と触れ合う
- 5. いい匂いを胸いっぱい嗅ぐ
- 6. 深呼吸する
- 7. 暴れる
- 8. 泣く
- 9. 笑う
- 10. 太陽の光を浴びる
- 11. 触り心地のよい寝具・持ち物を持ち歩く
- 12. 人に話す
- 13. 紙に書きだす
- 14. 受け入れる
- 15. 「いつもはしないこと」をしてみる
- 16. “ちょっと贅沢”をしてみる
- 17. ちゃんと手を抜く
- 18. 好きなことに没頭する
- 19. 「なにもしない」をする
- 20. 早く寝る・よく寝る
- 気分転換する方法(ワザ)をたくさん持とう!
ストレスは肝気の巡りを悪くする
まずはざっくりと前回のおさらいです。不満、我慢、緊張感、悩みごと、心配ごと、嫌なこと、苦手なこと(人)、孤独感、荷が重すぎる、やることが多すぎるなど精神的な負荷により、肝気がのびのびと巡らなくなって、肝気鬱結(略して、肝鬱)を引き起こします。詳しくは前回・前々回の記事をご覧くださいね。
なお、肝鬱になるのは精神的なストレスだけが原因とは限りません。ほかの病気があって、なにかしらの原因で肝気の巡りが悪くなって引き起こされることもあります。
生きていれば、誰でも肝鬱になることはある
中医学における「肝気鬱結」は、現代医学の「鬱病」とは異なり、あくまで「肝の気の巡りが悪い状態」を言い表しているだけです。したがって、肝鬱=鬱病ではありません。
また、肝鬱は年齢や性別に関係なく、誰にでも起こり得るものです。実際に、保育園に通うくらいの小さな子どもから、学生さん、働き盛りの大人、ご高齢の方まで、幅広い年代で見られます。
例えば大切な人を失った時には誰でも肝鬱っぽくなるものですが、「ときぐすり」という言葉があるように、一般的には時間と共に和らいでいくものです。ただし、その期間があまりに長すぎたり、程度が強過ぎたりすると、治療が必要になることもあります。

肝鬱になりやすい人の特徴2つ
苦労のない人などいませんが、その人の性格・気質・体質・心の在り方・考え方の癖などは、かなり個人差があるものです。
人生は主観です。同じ出来事でも、受け取る人によって、ポジティブにもネガティブにもなります。ですから、「肝鬱になりやすい人」や、「自分から肝鬱になりにいっちゃう人」が存在するのも確かです。
【肝鬱になりやすいタイプの特徴】
② プライドが高過ぎる
こだわりもプライドも、よい仕事をするためには必要なことです。しかし、「強“過ぎる”」「高“過ぎる”」場合は、他者にも自分にも、「思っていたのと違う」「求めていたのと違う」と感じる頻度が多く、程度も大きいため、毎日、肝鬱がつぎ足されます。
肝気の巡りをよくする漢方薬を毎日飲んだとしても、肝鬱を生み続けていれば、体質改善は思うように進みません。
真面目な人ほど自分に厳しく、自身を縛りつけてしまいがちです。そういう方はちょっとちゃらんぽらんに過ごすくらいが、ちょうどいいのかもしれません。「~でなければダメ」「~であるべき」を意識して減らし、自分に負荷をかけ過ぎないよう、傷めつけないようにしてください。
また、「気血両虚(気と血のどちらも不足している)」などの虚弱な体質の人は、心身ともにパワーが足りないので、そもそもストレスや疲労に耐えられるキャパシティが小さい傾向があります。そのため、ちょっとした負荷でもキャパオーバーして、肝気鬱結になることもあるでしょう。例えば、「疲れすぎてイライラする」「疲れすぎて気分が落ちる」といった状態です。
肝鬱による症状の特徴
肝鬱は「気分がよいときには一時的におさまる」し、「緊張や嫌なことがあると、症状が強く現れる」のが特徴です。肝気はギュッと結ばれやすく、また、ほどけやすくもあるのです。
肝鬱さんの症状は、【憂鬱←→上機嫌】【便秘←→下痢】のように、振れ幅が極端な傾向があります。なるべくでいいので、気分がスッキリした状態を増やすことを心がけてみてください。そうすると、肝気の滞りがほどけて巡りやすくなります。
気分がスッキリしていると肝気は巡りやすくなり、また、ちゃんと肝気が巡っていると気分はスッキリします。
肝気の巡りをよくする食養生
中薬学では、「芳香性=体内を駆け巡って、通して巡らせる作用」とします。例えば、ハッカやシソの葉、柑橘類の香りなどは、気分をスッキリさせてくれるということです。
ただし、一般的にはよい香りでも、ご自身の好みでなければ(くさく感じるなら)他のものにしましょう。胸いっぱいに吸いたくなって、思わず呼吸が深くなる…そんな自分がよいと感じる香りを選んでみてください。よい香りを「食べる」「飲む」「嗅ぐ」といったように、生活の中にたくさん散りばめてください。
気の巡りをよくする食材の例
<フレッシュ系(新鮮)>
・柑橘類なら何でも(果実よりも果皮・葉のほうが香りが強く効果もある。胃腸が弱っているときは生の果実は胃腸を冷やすので控えること)
・食用菊、ハッカ、ミント、パクチー、バジル類、パセリ、レモングラスなど
<ドライ系(乾燥)>
・薄荷茶、ミントティ、アールグレイティ、バラ茶(マイカイカ)、菊花茶、石菖蒲のお茶、レモングラスティ、紫蘇の葉茶、陳皮(乾燥した温州ミカンの果皮)のお茶
また、アロマテラピーを楽しむのも、肝気の巡りをよくする方法のひとつです。コットンやティッシュに精油を数滴たらして小皿にのせてルームフレグランスにしたり、あるいは、足湯や入浴時に柑橘類の果皮を浮かせてみたり、お家にあるもので気軽に楽しんでみてください。

上手に気分転換することが大切! 肝気を巡らせる養生
「養生(ようじょう)」とは「生き方」を養うこと。食生活や睡眠といった具体的なものだけではなく、自分と向き合い「心の在り方」を見直す、心の癖や考え方の癖に“気づいて”、“認め”、意識してよりよい方向へ持っていくことも含まれます。
たとえば、くよくよ悩んだり、頭の中で同じことをぐるぐる考え続けてネガティブな気分に陥ったりやすい人は、まず「今、自分はそのモードに入っているな」と、なるべく早い段階で気づくことが大切です。自分がどういう状況やきっかけでそうなりやすいのか、一度立ち止まって考えてみてください。
「悩む」と「考える」は、似ているようで違います。感情にまかせてただグルグルと「悩む」のは、気の巡りを滞らせ、肝気鬱結や心脾両虚といった体質を悪化させる原因になります。一方で「考える」とは、問題を論理的に整理し、見つめ、必要な材料を集め、解決に向かうための行為です。
大人は子どもと違って、自分の機嫌は自分でとるしかありません。そのままネガティブに突っ走らないように、気分転換の技をいくつも常備して、すぐに繰り出せるようにしておきましょう。肝気を巡らせるための合言葉は、「スッキリ!」「スカッと!」「ごきげん」です。また、「ウットリすること」「癒されること」「感動して泣けること」も肝気の巡りをよくします。
ここからは気分転換できる技のアイデアをいくつか紹介します。優先順位はないので、気に入りそうなものから試してみてください。
1. 大声で叫ぶ・歌う
声を出すと肺気が通るので、肝気も通りやすくなります。お風呂や車内で歌ったり、1人カラオケに行ったり、スポーツ観戦で声を出して応援したり、子供と公園で遊ぶのもよいですね。
2. ほどよく筋肉を動かす、有酸素運動をする
ほどよく筋肉を動かすと肝気が巡りやすくなります。ストレッチ体操や散歩など自分に合った運動ならなんでもOKです。特に、虚弱な体質の人はエアロビのような激しい運動よりも、ゆったりとした有酸素運動が合います。
有酸素運動なら、ヨガや気功がおすすめです。どちらも元々は修行法ですので、軽く行えば健康法になります。気功は中国版のヨガのようなもの。世界的に人気な「太極拳」は武術ですが、本質的には気功の訓練が必要です。
私たちの意識はふだん、自分の外側に向いてばかり(外向き)ですが、ヨガも気功も自分の内側に意識を向ける(内向き)ものです。呼吸を意識することで、心身が整いやすくなります(なお、ヨガや気功は先生を選ぶことが大切です。どちらも宗教の勧誘などに悪用されることがあります)。
3. 健康的に汗をかく
発汗は肝気を通し、ストレス発散になります。ただし、サウナ・岩盤浴・ホットヨガなどのように、負荷をかけて無理に汗をかくのは、養生と正反対の行動です。
無理のない運動の中で、ふつうに汗をかくだけで充分です。また、足湯でじんわり汗をかくのもおすすめです。気功の後にやると、とてもよいです。
4. 自然と触れ合う
山登りやハイキング、あるいは、公園や神社仏閣など、緑が多い場所で過ごす時間を作ってみましょう。健康的で大きな樹は、そのものがパワースポットで、よい気を持っています。
自然豊かな場所の澄んだ空気は質の高い清気です。鼻から深呼吸するとよい気を取り入れられる上に、深呼吸によって肺気・肝気が通りやすいです。
5. いい匂いを胸いっぱい嗅ぐ
ペット・好きな人・お花・ハーブ・お香・アロマテラピーなど、よい匂いだなと自分が感じるものであればなんでもOK。自然に深呼吸になるので、肺気と肝気が通りやすくなります。
6. 深呼吸する
1〜5はどれも深呼吸と関係あることにお気づきでしょうか? 息を吐くときに副交感神経が優位になり、気持ちもリラックスします。
深呼吸は、自律神経系や精神情緒系を整え、水分代謝などの代謝も活性化されます。
7. 暴れる
お風呂などでバシャバシャ暴れて、ムシャクシャを発散しましょう!笑
8. 泣く
音楽や映画で泣いたら、なんだか気分がスッキリしたという経験はありませんか? 泪を流すと副交感神経が優位になってリラックスし、泪と一緒にストレスホルモンも洗い流されます。
「お風呂に入る前にひと泣きするか…!」くらいの気軽なテンションで、涙活するのも方法のひとつです。泪は心のデトックス!
9. 笑う
1日1回は笑いましょう! 笑いの効果は抜群です。今日1日を思い出して、もし笑ってなかったら、とりあえず「わはははは!」と笑ってください。理由がなくても構いません。作り笑いでも効果あり!
10. 太陽の光を浴びる
太陽光は、幸せホルモン(ハッピーホルモン)であるセロトニンの分泌をよくします。「手のひらを太陽に」という歌がありますが、本当に効果があるんですよ。
太陽や樹木に手の平を向けてパワーをもらうのは、気功の功法のひとつで「採気功」と名付けられています。

11. 触り心地のよい寝具・持ち物を持ち歩く
特別に肌触りがよいものに触れるのも、手っ取り早くリラックスする方法です。
パジャマ、下着、枕カバー、お布団はもちろん、肌触りのよいポーチやハンカチがあると、仕事中もリラックスできます。
12. 人に話す
モヤモヤしていることも、人に話しているうちに頭が整理されてスッキリすることがあります。守秘義務がある専門家(カウンセラー・漢方薬局の人など)や、信頼できる近しい人に、話してみるのもひとつです。気づきがあるかもしれません。
13. 紙に書きだす
自分の気持ちを紙に書き出して発散するのもひとつの方法です。きれいに書かなくて構いません。ぐちゃぐちゃでよいので、思いついたことをすべて書き出してみてください。
ひと通り書き出したら、もう一度書き直してみたりしましょう。だんだんと問題や優先順位が明確化されます。
14. 受け入れる
人生は小さな悟りの積み重ね。受け入れることで、生きやすくなるかもしれません。
15. 「いつもはしないこと」をしてみる
行ったことのない場所に行く、いつかはやってみたかったことを試してみる…など、非日常的な体験は、大きな気分転換になります。
16. “ちょっと贅沢”をしてみる
ちょっといいお茶を飲む・ふだんは買わない美味しいものを食べる…など、自分を甘やかして喜ばせることも大切です。
17. ちゃんと手を抜く
一つひとつはほんの小さなタスクでも、数が多すぎたら精神的・肉体的負荷になり得ます。減らせるタスクやサボれるタスクはないか、手を抜けるところを積極的に探すことも大切です。
あれもこれも完璧にやろうとしないことです。掃除はお掃除ロボットに任せる(細かいところはこだわらない)、食品や日用品の調達は配達に頼るなど、手を抜けるところは抜きましょう。そして、空いた時間でちゃんと自分を労ってください。
18. 好きなことに没頭する
好きなことに夢中になると、気持ちが日常から切り離され頭も心も休まります。ただし、やり過ぎは消耗し過ぎるので注意が必要です。
19. 「なにもしない」をする
「なにもしない」をするのも大切です。「Doing nothing often leads to the very best kind of something.(「何もしないこと」は、しばしば最高の何かを連れてくる)」とは、くまのプーさんの名言です。
人生いろいろありますが、頭を空っぽにして休む時間も必要です。昼(陽)と夜(陰)があるように、人間も動(陽)と静(陰)のバランスがとれてはじめて心身ともに健康でいられます。せわしく過ごしているなら、その分ぼーっと過ごす時間も必要です。デジタルデトックスも忘れずに!
20. 早く寝る・よく寝る
必要な記憶を整理して定着させるのも、嫌な記憶を消し去るのも、睡眠中におこなわれます。自分に合った睡眠時間を確保しましょう。

気分転換する方法(ワザ)をたくさん持とう!
このほかにも、気分転換の方法は、可愛いものに癒される(例えば、動物の赤ちゃんの動画を観る)、本や漫画を読む、ゲームをする、音楽を聴く…などいろいろあります。
気分転換の方法をたくさん持っていると、気持ちも安定しやすくなります。自分の機嫌をとる、気持ちを切り替えるワザをいくつか用意しておいて、いつでも繰り出せるようにしてください。
肝気鬱結していると気持ちがスッキリしないし、気持ちがスッキリしてないと肝気鬱結になります。体質が心の在り方をつくり、心の在り方が体質をつくります。悪循環はどこかで断ち切らなければなりません。
どうにもうまく解消できないときは、お医者やカウンセラー、漢方薬局などの専門家に相談してみてください。養生と肝気を巡らせる漢方薬を組み合わせると、より気分がスッキリしやすいかと思います。
参考文献:
・小金井信宏(著)『中医学ってなんだろう(1)人間のしくみ』東洋学術出版社 2009年
・内山恵子(著)『中医診断学ノート』東洋学術出版社 2002年
・丁光迪(著)、小金井 信宏(翻訳)『中薬の配合』東洋学術出版社 2005年
・凌一揆(主編)『中薬学』上海科学技術出版社 2008年
・中山医学院(編)、神戸中医学研究会(訳・編)『漢薬の臨床応用』医歯薬出版株式会社 1994年
・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための中薬学』医歯薬出版株式会社 2004年
・翁 維健(編集)『中医飲食営養学』上海科学技術出版社 2014年6月
・日本中医食養学会(編著)、日本中医学院(監修)『薬膳食典 食物性味表』燎原書店 2019年
・許 済群(編集)、王 錦之(編集)『方剤学』上海科学技術出版社 2014年
・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための方剤学』医歯薬出版株式会社 2004年
・伊藤良・山本巖(監修)、神戸中医学研究会(編著)『中医処方解説』医歯薬出版株式会社 1996年
・李時珍(著)、陳貴廷等(点校)『本草綱目 金陵版点校本』中医古籍出版社 1994年
・白川静(著)『常用字解』平凡社 2003年