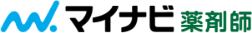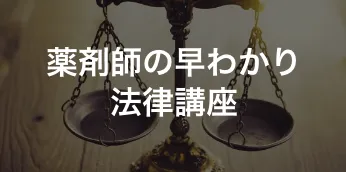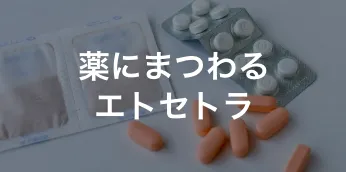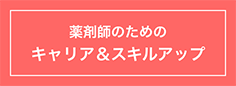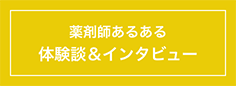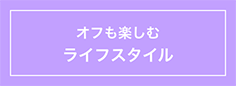学べば学ぶほど、奥が深い薬の世界。もと製薬企業研究員のサイエンスライター・佐藤健太郎氏が、そんな「薬」についてのあらゆる雑学を綴るコラムです。薬のトリビアなどを伝えられると、患者さんとの距離も近くなるかもしれませんね。
歴史上の様々な発明・発見の物語をひもといてみると、驚くほどに偶然の発見が寄与していることがわかります。リンゴの実が木から落ちるのを見て、万有引力の法則を思いついたニュートンの例は、その最も有名なケースでしょう。このような「本来探していたものとは別の、価値あるものを見つけること、あるいはその能力」を「セレンディピティ」と呼ぶことは、本連載の第3回でも触れました。
医薬発見の歴史にも、セレンディピティに恵まれた発見の例は数多く知られています。有名なのは、ED治療薬であるバイアグラのケースでしょう。この薬は血管を拡張する作用があるため、当初は狭心症の治療薬を目指して開発が行なわれていました。しかし臨床試験を行ったところ、狙っていた狭心症に対しては十分な作用を示さなかったものの、副作用として男性に勃起を促進することがわかったのです。ならばとこちらを主作用として開発を進めた結果、話題の新薬として大成功を収めました。
育毛剤ミノキシジル(商品名「リアップ」)もこれと似たケースで、もともとは降圧剤として開発されていた薬でした。しかし臨床試験中に、患者に毛が生えてくるという「副作用」が発見されたため、こちらに適応症を切り替えたことが功を奏したのです。頭皮の血管を広げ、血流をよくしたことが、発毛につながったと考えられています。
エーザイのアルツハイマー病治療薬アリセプトもまた、偶然の幸運が作用しています。この薬は中央に5員環部分をもちますが、これは狙って作られたものではありませんでした。もともとは、この5員環に窒素を挿入して6員環を合成する狙いであったのですが、せっかく作ったものだからとついでに5員環化合物の活性を測定したところ、予想外に強力な作用を示すことがわかったのです。本来作ろうとしていた6員環化合物には、ほとんど活性がなかったというから面白いものです。

またシスプラチンは代表的な抗がん剤として広く使われていますが、白金原子に塩素原子とアンモニア分子が結びついただけの、ちょっと他の医薬からはかけ離れた構造です。しかもこれを発見したのはがん研究者でも製薬企業でもなく、細菌学者であるB・ローゼンバーグでした。1960年代、彼は殺菌法の開発を目指し、大腸菌の培養液に電流を流す実験を行っていました。これによって大腸菌の増殖は止まったのですが、よく調べていくとその原因は電流ではなく、電極として用いていた白金が溶液中に溶け出し、大腸菌のDNAに結びついてその働きを止めていることがわかったのです。この発見をがん細胞に適用したところ、みごとその増殖を抑え込みました。もしローゼンバーグが電極に他の金属を使っていたら、白金系抗がん剤の数々はこの世に存在しなかったかもしれません。
しかし史上最大のセレンディピティといえば、やはり抗生物質ペニシリンのケースでしょう。ロンドンのある病院の実験室に放置されていたシャーレに、アオカビの一種が飛び込み、周りの菌を殺していたのです。この実験をしていたのが、抗菌作用について十分な知識のあったほぼ唯一の人物、アレクサンダー・フレミングでなければ、おそらくこの偶然は見過ごされていたことでしょう。そしてこれは、彼が長期の旅行中に起きた出来事でした。もしフレミングが長く留守にしていなければ、カビが十分に繁殖して菌を殺すことはなかったかもしれません。また、この時飛び込んだアオカビは、ペニシリンを多量に生産する、珍しい種類のカビだったのです。
このようにペニシリンは信じがたいほどの幸運が重なって生まれた薬であり、そのひとつでも欠けていれば世界の歴史は大きく変わっていたことでしょう。このあたりは、筆者の近著「世界史を変えた薬」(講談社現代新書)に詳しく書きましたので、興味のある方はご覧ください。
このような次第で、幸運に恵まれて見つかった薬は数多いのです。実際のところ、幸運の介在なしに世に出た薬のほうが珍しいといってもいいかもしれません。
というと、なんだ、創薬研究者などと偉そうなことを言っているが、ただのまぐれ当たり頼みなのか――と思われてしまうかもしれません。しかし、たとえ偶然の発見に恵まれても、それを本当に活かすには、発見の価値を正しく理解すること、その原因を究明できること、こだわらず柔軟に新たな発見の使いみちを考えられることなどなど、様々な能力が必要になります。
幸運は誰のもとにも巡ってきますが、それを捕まえ、活かすことができる人は一握りです。画期的な新薬を生み出し、多くの患者を救うために最も必要なのは、案外こうした能力であるのかもしれません。