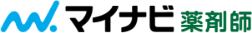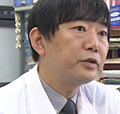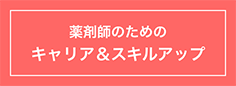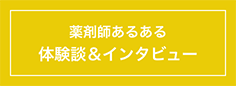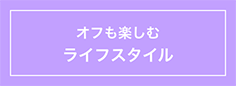映画・ドラマ

「たまには仕事に関連する映画を見てみようかな」と感じたことはありませんか? 医療や病気に関する映画・ドラマ作品は数多くありますが、いざとなるとどんな作品を見ればいいのか、迷ってしまう人もいるのでは。このコラムでは北品川藤クリニック院長・石原藤樹先生と看護師ライターの坂口千絵さんが、「医療者」としての目線で映画・ドラマをご紹介します。

vol.15「リリーのすべて」(2015年・イギリス)
風景画家のアイナー・ヴェイナーは肖像画家の妻ゲルダと結婚し、デンマークで充実の日々を送っていたが、ある日、妻に頼まれて女性モデルの代役をしたことを機に、自分の内側に潜む女性の存在に気づく。それがどういうことなのかもわからないまま、“リリー”という女性として過ごす時期が増え、心と身体が一致しない状態に苦悩するアイナー。一方のゲルダは夫の変化に戸惑いながらも、いつしか“リリー”こそアイナーの本質であると理解していく。

―人間の心と身体に潜む謎と夫婦の不思議―
こんにちは。北品川藤クリニック院長の石原です。
今日ご紹介するのは、2015年のイギリス映画『リリーのすべて』です。日本公開は昨年(2016年)ですから、映画館に足を運ばれた方もいるのではないかと思います。
1930年に世界で初めての性転換手術(性別適合手術)を受けたとされる、実在のベルギー人の画家リリー・エルベ(男性名アイナー・ヴェイナー)の実話をもとにした、アメリカ人作家による小説を原作とした作品です。
主役は演技派のエディ・レッドメイン。風景画家としてデンマークで成功し、同じ画家の妻がいながら、あるとき自分の心の中に住む「リリー」という女性の存在に気づき、次第にリリーとして生きるようになる主人公を、さすがの演技力で、説得力を持って演じています。
ただ、性同一性障害の物語かというと、そこはちょっと違います。
主人公の心の中には常に影響し合い、競争し合う、2つの性別の異なる人格が住んでいて、それが互いにせめぎ合い、最終的には女の人格であるリリーが、男の人格であるアイナーを殺してしまうのです。
この物語は実はリリーではなく、その妻であるゲルダが主役ともいえる作品です。ゲルダは男勝りの女性で、夫のアイナーとの関係も、夫婦というより同志という感じです。夫が女装してリリーを名乗るようになると、最初はそれを面白がるのですが、次第にそれが夫アイナーとの永遠の別れにつながることに気づき、アイナーとの夫婦の絆を守るために、勝てない戦いに挑むのです。アイナーは死にますが、ゲルダとリリーとの間には、夫婦とも友人とも違う、不思議な絆が生まれます。
映画でははっきりとは描かれませんが、原作ではリリーが性別を変えた時点で、夫婦は離婚し、アイナーは法的にはその存在を抹消されるのです。
ゲルダを演じたアリシア・ヴィキャンデルは、原作小説のいかついイメージとはちょっと違う感じがするのですが、感情の揺れ動きを繊細に演じてこれも素晴らしく、本作で第88回アカデミー賞助演女優賞を受賞しています。
映画の後半はリリーの性別適合手術が描かれて、性別と人格の悩みに対する、医療の無理解と残酷さとがクローズアップされます。世界最初の手術にこだわる外科医の姿や、手術の前のリリーの不安な気持ちの描写などは、今の医療とつながる部分もあり、薬剤師の皆さんにも参考になる部分が大きいと思います。
監督は『英国王のスピーチ』や『レ・ミゼラブル』で有名なイギリスのトム・フーパーで、映画としては地味な素材を、少人数のキャストで緻密で繊細な感性のドラマにしています。ヨーロッパの風景が非常に美しく、クラシックな趣で安定感があります。イギリスの巨匠、故デヴィッド・リーンを思い起こさせるところがあり、特にアイナーの故郷の荒涼とした崖の上で、風にあおられてリリーのスカーフが空を舞う場面は、リーンの『ライアンの娘』のオープニングにそっくりでした。
性同一性障害というより、解離性同一性障害の心理と、夫婦の愛情のさまざまなあり方を繊細に描いた美しい映画で、医療がこうした問題にどう取り組むべきかを、考えさせるという側面も持っています。ひとりでももちろんですが、夫婦や家族、友人同士で観て、人間同士の絆について考えるのも素敵だと思います。
あわせて読みたい記事