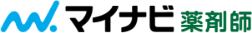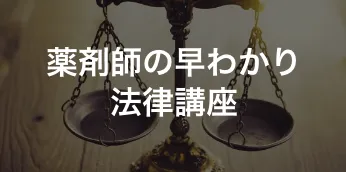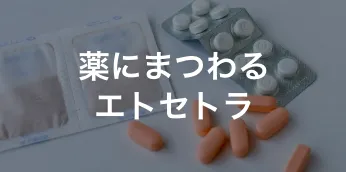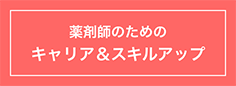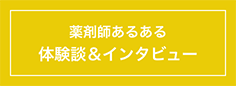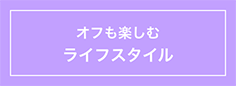学べば学ぶほど、奥が深い薬の世界。もと製薬企業研究員のサイエンスライター・佐藤健太郎氏が、そんな「薬」についてのあらゆる雑学を綴るコラムです。薬のトリビアなどを伝えられると、患者さんとの距離も近くなるかもしれませんね。
前回も述べた通り、薬価の高騰は近年極めて深刻になりつつあります。この問題の象徴となったのが抗がん剤オプジーボで、治療費が患者一人あたり年間約3500万円にも及びます。「この一剤の存在だけで保険医療制度が崩壊しかねない」とも指摘され、大きな議論が巻き起こりました。
オプジーボは、奏効率が約15~20%(肺がんの場合)に過ぎないとされます。このため大半の患者にとっては、この超高額薬はただの「無駄打ち」となってしまうのです。そして現状では、どの患者にオプジーボが有効かをあらかじめ知る手立てはなく、使い始めてから「効果が出ない」と見切るのも難しいといいます(里見清一「医学の勝利が国家を滅ぼす」(新潮新書)より)。一部の患者に対しては素晴らしい効能があるとはいえ、国庫に大きな負担をかけていながら8割が空振りというのでは、問題視されてもやむを得ないでしょう。
こうした問題が起きたため、「特例拡大再算定」という制度が導入され、2017年2月にオプジーボの薬価は50%引き下げられました。また、ソバルディやハーボニー(いずれもC型肝炎治療薬)などの薬価も、同様に切り下げられています。
とはいえ、この問題はこれで終わりでは済みません。現在の制度では、新薬の薬価は同じような先行薬の薬価を参考に決められますので、この制度がある限り今後も高額な医薬が登場し続けるのです。実際、2017年2月に承認された肺がん治療薬キイトルーダの薬価は、同タイプの医薬であるオプジーボと同額となりました。こうしたわけで、抗体医薬を中心とした抗がん剤の薬価は、高騰する一方となっています。
解決策は、薬価制度を抜本的に見直すしかありません。たとえば、第36回で述べたように、費用対効果を重視した制度づくりの検討なども進められています。しかし、闇雲に薬価引き下げだけを目指すのでは、製薬会社としてもなかなかハイリスクな医薬の開発に挑むことができなくなります。諸外国が利用できる優れた新薬に、日本人だけがアクセスできないという事態にもなりかねません。

こうした中、意外な方向から新たな提案がなされました。スイスの製薬大手であるノバルティス社が、効果があった場合にのみ対価が支払われる仕組み、すなわち「成功報酬型薬価」という方式を提示してきたのです。対象となるのは、この8月に米国で承認された小児・若年成人の急性リンパ性白血病治療薬「キムリア」です。
新薬といっても、キムリアは今までのような合成低分子や抗体を用いる医薬ではありません。患者の免疫細胞を取り出して、遺伝子操作を施した上で体内に戻し、がん細胞を攻撃させるというものです。こうした治療法が承認されるのは、これが初めてのことになります。
キムリアは米国で承認されましたが、その価格はなんと1回あたり47万5000ドル(約5400万円)に設定されました。オプジーボをもはるかに上回る超高額ですが、1回の投与で完全寛解を得られること、既存の骨髄移植療法に比べれば低コストであることを考えれば、これは妥当な額であるとノバルティス社は主張しています。
ノバルティス社はこのキムリアを、2018年前半にも日本で承認申請する予定としています。その際、超高額な薬価の代わりに、先に述べた成功報酬型薬価制度を導入することを提案しているのです。
この成功報酬型薬価は、すでに英国などで取り入れられており、たとえばベルケイド(多発性骨髄腫治療薬)では、効果がなければ返金されることとなっています。今回のキムリアも、治療開始から1カ月で反応があった場合にのみ、支払いが発生する仕組みが米国で採用されました。製薬会社側としては不利なシステムですが、キムリアはこれまで8割の患者に効果を示すというデータがあるため、効能に自信ありということなのでしょう。
医療費抑制に悩む政府としては渡りに船の提案――ではありますが、「ではそうしましょう」と簡単に飛びつける話ではないのも当然です。有効性をいつどう判定するか、支払いの仕組みをどうするか、今後の他の新薬への影響はどうなるかなど、議論すべきことは山積しています。しかし、前述のオプジーボのケースなどを考えれば、こうしたシステムは十分に必要性のあることと思えます。
細胞治療や遺伝子治療、再生医療など、既存の医薬の枠を超えた医療手段はこれからも続々登場してきます。薬価制度もこれらに対応すべく、大きく、かつ柔軟に変わっていかねばならない状況にあります。成功報酬型薬価を導入するか否か、またどのような形で取り入れるべきかは、その重要な分岐点の一つとなりそうです。