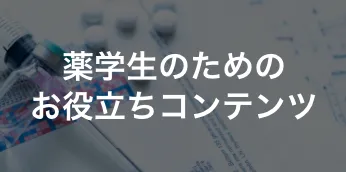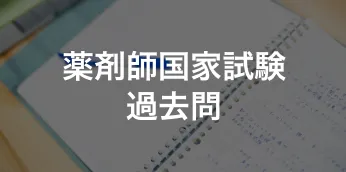薬学部は何年制で、何を学ぶのかを知っておくことは、進路選びにおいて重要なポイントです。また、「薬学部の6年制はいつから導入されたのか」といった制度の背景も知っておきましょう。本記事では、薬学部に通う年数や、4年制と6年制の違い、学費、就職先などについて解説します。

1.薬学部とは?
薬学部とは、薬に関する幅広い専門知識と技能を身に付ける学部です。薬剤師や薬学研究者、薬の開発職、行政が行う公衆衛生などを担える人材を育成します。
薬学生は、化学、物理、生物といった自然科学の基礎を学びつつ、薬の製造過程を扱う「製剤学」や、環境・公衆衛生と栄養の関係を学ぶ「衛生薬学」など、多岐にわたる科目を履修します。その他にも、薬局や病院での実務実習などを通じて、科学的な理論と医療現場での実践力の両面から、薬に関する高度なスキルを身に付けることができます。
大学の薬学部には、薬剤師国家試験の受験資格を得られる6年制と、薬学の知識を学べる4年制があります。薬剤師免許を取得するには、6年制薬学部に入学し、倫理観やコミュニケーション能力、多職種との連携スキル、臨床現場での実践力などを学んで卒業した上で、薬剤師国家試験に合格しなければなりません。
2.薬学部は何年通う?
前述の通り、薬学部には6年制と4年制の2つの課程があります。薬剤師になるには、薬剤師国家試験の受験資格が得られる6年制の薬学部に進学することが必要です。4年制薬学部は、主に薬学分野の知識・技能の習得を目的としており、卒業しても薬剤師国家試験の受験資格は得られません。
薬剤師資格を取得したいなら6年制、薬剤師資格を必要としない職業への就職を目指すのであれば4年制など、卒業後の進路を踏まえて薬学部の受験時に6年制・4年制を選択するとよいでしょう。ただし、医療関連の職種の場合、薬剤師資格を取得していた方が就職に有利になりやすい場合があるため、できるだけ具体的に進路を考えて選ぶことが大切です。
🔽 薬剤師になる方法を詳しく解説した記事はこちら
2-1.4年制から6年制になったのはいつから?
薬学部の6年制は、2006年度(平成18年度)から正式に導入されました。学校教育法と薬剤師法の改正により、原則として6年制の薬学部を卒業した人にのみ薬剤師国家試験の受験資格が与えられるようになっています。
4年制の薬学部は、薬剤師としてではなく、薬学の基本的な知識を習得して社会で活躍する人材を養成することが期待されています。そのため、6年制の導入後も、4年制薬学部を設けている大学は少なくありません。
参考:薬学教育制度の概要|文部科学省
参考:薬学部教育の質保証専門小委員会(第6回) 参考資料8-1 薬学教育関連資料|文部科学省
2-2.6年制になったのはなぜ?
薬学部の6年制が導入されたのは、医療が高度化したことに加え、より実践的で信頼される薬剤師の育成が求められたからです。
薬学はもともと、主に医薬品や化学物質などの「モノ」を対象とする学問でした。しかし、薬の「処方」と「調剤」を医師と薬局薬剤師が分担する「医薬分業」や、病院薬剤師に医療チームの一員としての役割が要求されるようになり、「人」の薬物治療を対象とする学問への発展が求められました。
そうした状況下にもかかわらず、当時、薬剤師養成のための教育は十分とはいえず、臨床経験を十分に積むのが難しいといった課題がありました。そこで、実施されたのが、2006年度の学校教育法と薬剤師法の改正です。医療人として質の高い薬剤師を養成するために、薬剤師資格の取得には6年制薬学部を卒業することが必須となりました。

3.薬学部の4年制と6年制の違い
薬学部の4年制と6年制には、どのような違いがあるのでしょうか。それぞれの違いについて解説します。
3-1.6年制薬学部では何を学ぶ?
6年制薬学部では、一般的に1年次から4年次までは基礎薬学や臨床薬学を学び、5年次から長期の実務実習、6年次には薬剤師国家試験の合格に向けて試験対策を行います。基礎薬学や医療薬学など、薬学の知識を幅広く学んだあと、臨床で必要な知識や薬剤師としての倫理観・態度を身に付けるのが目的です。
2006年の法改正では、薬学部が6年制となったほか、実務実習の時間数が2~4週間から6カ月程度に大幅に延長されました。5年次に行われる実務実習では、「認定実務実習指導薬剤師」の資格を持つ先輩薬剤師の指導のもと、病院や薬局で薬剤師業務を体験します。実際に医療の現場で働く薬剤師を見たり、薬剤師業務を体験したりすることで、臨床でしか学べない知識や考え方、薬剤師としての倫理観・責任感を身に付けるのが目的です。
🔽 薬学部の実務実習について解説した記事はこちら
また、実務実習を行う前には、必要な知識や技能、態度を保証するための薬学共用試験に合格しなければなりません。薬学共用試験は実習を行う前年度の12月~1月に行われ、知識を評価する「客観試験CBT」と、技能・態度を評価する「客観的臨床能力試験OSCE」の2種類があります。実務実習に至るには、これらの試験に合格できるレベルの知識やスキルを身に付けておく必要があります。
参考:薬学共用試験について|薬学共用試験センター
🔽 薬学部のCBTについて解説した記事はこちら
3-2.4年制薬学部では何を学ぶ?
4年制薬学部は、主に化学や薬学の分野で活躍できる研究者を育てることを目的としています。カリキュラムは大学によって異なりますが、一般的な6年制との違いとしては、研究を重視している点が挙げられます。
例えば、1、2年次は、6年制薬学部の生徒と一緒に、有機化学や分析化学、生化学など薬学の基礎知識や、薬理学・薬物動態学、製剤学・薬品化学など、幅広い薬学分野について学び、3年次以降は薬学研究に必要な高度な学科目や実験・研究を中心に学ぶカリキュラムを組む大学もあります。
国家試験対策や実務実習などに時間を取られることなく、専門性の高い研究に集中できるのが、4年制薬学部の特徴です。
4.薬学部の学費はいくら?
薬学部に通うために必要な費用はいくらくらいなのでしょうか。ここでは、薬学部の学費について紹介します。
4-1.6年制薬学部の学費
6年間も大学に通うとなれば、費用が気になる人も多いのではないでしょうか。薬学部に通うときにかかる費用は、国立大学と私立大学で大きく異なります。
国公立大学の場合、学費は6年間でおよそ350万円~400万円、私立大学は大学によって差があるものの、6年間で1000万円~1400万円程度が目安です。学費に加えて、参考書代や実務実習費、通学費、実家を離れる場合は生活費も必要となるため、実際には、さらに費用がかかる可能性があるでしょう。
🔽 薬学部の学費について解説した記事はこちら
4-2.4年制薬学部の学費
4年制薬学部の学費も、国公立・私立などの大学の種類によって大きく異なりますが、4年間の通学となる上に実務実習がないため、基本的には6年制薬学部と比較すると学費は安くなります。
国公立大学の学費は250万円~300万円程度、私立大学は700万円~1000万円程度が目安となるでしょう。ただし、私立大学の場合は、初年度の学費が200万円以上必要になることも珍しくありません。実験室や研究設備が充実している大学ほど、施設費や実習費が高額になる傾向があります。詳しくは、各大学のホームページを確認しましょう。
4-3.薬学部の学費に不安があるなら
費用面で不安がある場合には、奨学金や特待制度を活用する方法があります。日本学生支援機構では、給付型と貸与型の奨学金を提供しています。学力や家計の状況などにより利用できる奨学金が異なるため、日本学生支援機構のホームページで申込資格や基準を確認しておきましょう。
また、大学によっては特待制度を設け、条件を満たすことで入学料が免除されたり、授業料の負担が軽くなったりする可能性があります。大学ごとに条件が異なるため、受験を考えている大学のホームページも事前にチェックしておきましょう。
🔽 薬学部の奨学金について解説した記事はこちら

5.薬学部卒業後の就職先
薬学部を卒業後の就職先は、6年制と4年制でおおむね一致していますが、その割合は大きく異なります。詳しく見ていきましょう。
5-1.6年制薬学部卒業後の主な進路
薬剤師の就職先として多いのは、薬局や医療施設(病院や診療所)です。薬学協議会の資料によると、6年制薬学部卒業後の主な就職先(2024年3月)は、薬局やドラッグストアの調剤部門、病院・診療所が全体の約7割を占めています。その他には、医薬品関連企業、衛生関連の行政を担う国家公務員や地方公務員、大学院への進学などが主な進路です。
参考:2024(令和6)年3月卒業生および大学院修了者の就職動向調査結果報告書(一部)|薬学教育協議会
5-2.4年制薬学部卒業後の主な進路
4年制薬学部を卒業した薬学生のうち約7割の学生が、大学院などへの進学を選択しており、残り3割は薬局やドラッグストア、試験・研究機関、企業などに就職しています。進学を選んだ学生の修士および博士課程修了後の進路としては、医薬品関連企業の研究・開発職や営業職、化学系企業などへ就職したり、博士課程の修了を目指して進学したりしています。
参考:2024(令和6)年3月卒業生および大学院修了者の就職動向調査結果報告書(一部)|薬学教育協議会
🔽 薬学部の就職先について解説した記事はこちら

6.卒業後の進路によって6年制・4年制を選択しよう
薬剤師になるには薬学部に6年間通う必要があります。薬剤師資格を必要としない職業への就職を目指す場合は、4年制を選択してもよいでしょう。ただし、4年制を選択した学生の7割が大学院へ進学しています。そのため、結果的には6年間薬学について学ぶ可能性が高いでしょう。薬学部の受験を考えているのであれば、卒業後の進路を明確にして、6年制または4年制を選択することが大切といえます。

薬剤師ライター。2児の母。大学卒業後、調剤薬局→病院→調剤薬局と3度の転職を経験。循環器内科・小児科・内科・糖尿病科など幅広い診療科の経験を積む。2人目を出産後、仕事と子育ての両立が難しくなったことがきっかけで、Webライターとして活動開始。転職・ビジネス・栄養・美容など幅広いジャンルの記事を執筆。趣味は家庭菜園、裁縫、BBQ、キャンプ。
あわせて読みたい記事