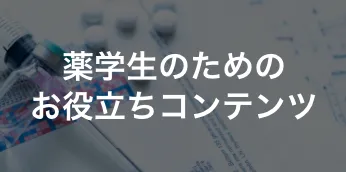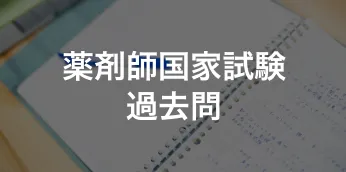薬学部は学習内容の幅広さや半年間に及ぶ実務実習、進級や国家試験へのプレッシャー、経済的な負担などから、他の学部と比べて心身ともに負荷を感じやすい環境かもしれません。しかし、薬学分野の専門知識が身に付いたり、卒業後には薬剤師のキャリアを目指せたりと、薬学部には多くの学びや将来につながる価値があります。本記事では、薬学部が「大変」「つらい」といわれることがある理由をはじめ、困難を感じたときに乗り越えるための具体策や有意義な学生生活を送るためのポイントを解説します。

- 1.薬学部が「大変」「つらい」といわれる理由とは?
- 1-1.学ぶ分野が多岐にわたるため、勉強量が多い
- 1-2.約半年間の実務実習がある
- 1-3.進級や卒業が大変
- 1-4.学費の負担が大きい
- 2.薬学部が「大変」「つらい」と感じたときの対処法
- 2-1.目標を明確にする
- 2-2.大学の支援制度を活用する
- 2-3.学業以外のリフレッシュ方法を見つける
- 2-4.同級生や先輩に相談する
- 3.薬学部の魅力やメリットとは?
- 3-1.薬学分野に関する専門知識を身に付けられる
- 3-2.学生同士で共に過ごせる時間が長い
- 3-3.卒業後に薬剤師としてキャリア構築を目指せる
- 4.薬学部で有意義な学生生活を送るためのポイント
- 4-1.1~2年生
- 4-2.3~4年生
- 4-3.5~6年生
- 5.薬学部の6年間を充実させよう
1.薬学部が「大変」「つらい」といわれる理由とは?
薬学部では、学習内容の幅広さや約半年間にわたる実習など、学業面での負担が大きくなりがちです。さらに、経済面や国家試験への不安から「大変」「つらい」と感じる場面もあるかもしれません。ここからは、薬学部が大変といわれる具体的な理由について解説します。
1-1.学ぶ分野が多岐にわたるため、勉強量が多い
薬学部では、薬に関する幅広い分野について学ぶため、勉強量が多くなりがちです。例えば、薬の成分や作用を科学的に分析する「基礎薬学」では、薬が体内でどのように吸収・分布・代謝・排泄されて作用するのか、そのメカニズムを詳しく学びます。
また、薬剤師になると、多職種との連携や患者さんへの服薬指導などを行うため、医療全体への理解や実践力も欠かせません。そのため、「医療薬学」「臨床薬学」「社会薬学」などの分野では、薬を適切に使用するための知識や判断力を修得していきます。
このように、薬に関する幅広い知識とスキルを身に付ける必要があることから、日々の勉強量が多くなり、負担に感じる学生も少なくありません。
1-2.約半年間の実務実習がある
医療現場における実践的な知識やスキルを身に付けるため、5年次には約半年間にわたる実務実習を受けます。実習先は薬局と病院で、期間はそれぞれ11週間ずつ、計22週間に及びます。
実習内容は処方箋に基づいた調剤だけでなく、処方内容の検討や医師への提案など、薬物療法に関する実践的なものが中心です。さらに、地域医療の一環として、在宅医療や災害時の対応、セルフメディケーションについても学びます。
これまで講義で学んだ知識を、実際の現場でどう生かすかが問われるため、緊張感や責任の重さを感じることもあるでしょう。実習は多くの学びが得られる貴重な機会である反面、精神的・体力的に負担を感じやすい期間ともいえます。
🔽 薬学部の実務実習について解説した記事はこちら
1-3.進級や卒業が大変
薬学部は進級や卒業に必要な要件が厳しいことから、学業についていけなくなってしまう学生も少なくありません。文部科学省が公表している「薬学部における修学状況等 2024年(令和6年)度調査結果」(※国公私立大学のデータの統計)によると、2018年度の薬学部入学生における5年生への進級率は78.1%、卒業率は68.3%となっており、データからもその厳しさがうかがえます。
特に、実務実習の前には「薬学共用試験」と呼ばれる試験に合格する必要があります。知識を問うCBT(Computer-Based Testing)と、技能や態度を評価するOSCE(客観的臨床能力試験)の2つで構成されており、いずれも一定の基準を満たせなければ、実習に進むことができません。
参考:薬学共用試験について|薬学共用試験センター
🔽 薬学部のCBTについて解説した記事はこちら
さらに、実習後には卒業試験や薬剤師国家試験が控えており、6年間を通じて厳しい条件をクリアしていく必要があります。こうした背景から、進級や卒業に向けて精神的なプレッシャーを感じてしまう薬学生もいるのが実情です。
1-4.学費の負担が大きい
薬学部は、文系学部や他の理系学部と比べて、学費が高くなる傾向があります。薬剤師の資格を目指す場合は6年間大学に通う必要があり、4年制の大学よりも2年分多く学費がかかるためです。
また、講義以外にも、実験や研究がカリキュラムに組み込まれており、設備費や薬品代、動物実験の管理費などが必要になります。さらに、病院や薬局で行う実務実習にも費用がかかります。
こうした理由から、薬学部の学費は高額になりやすく、私立大学では年間150万〜250万円程度かかるのが一般的です。長期間にわたってまとまった費用が必要となるため、経済的な負担を重く感じる学生もいるでしょう。
🔽 薬学部の学費について解説した記事はこちら
2.薬学部が「大変」「つらい」と感じたときの対処法
薬学部が「大変」「つらい」と感じたときは、自分の気持ちや環境を見つめ直してみることが大切です。ここからは、勉強への向き合い方や学業以外のリフレッシュ方法、大学の支援制度の活用法など、つらいと感じる状況を乗り越えるための具体策を紹介します。

2-1.目標を明確にする
薬学部での勉強や実習に追われていると、何のために努力しているのか分からなくなってしまうこともあるでしょう。そうしたときこそ、自分が薬学を学ぶ目的や将来なりたい姿について改めて考えてみることが大切です。
例えば、「病院薬剤師として患者さんと向き合いたい」「製薬会社で新薬の開発に携わりたい」など、進みたい方向が明確になれば、日々の学びにも意味を見出しやすくなります。
また、目標があることは計画的な行動にもつながり、試験勉強やレポート作成もゴールに向けた一歩として、前向きに取り組みやすくなるでしょう。
将来のビジョンが定まっていないときは、インターンに参加したり、先輩の話を参考にしたりするのもよい方法です。
2-2.大学の支援制度を活用する
薬学部での学びに行き詰まりを感じたときは、大学が提供している支援制度を活用するのもひとつの方法です。
一部の大学では、学習を支えるための専用窓口を設置し、学習の進み具合や理解度に応じたサポートを行っています。実務実習前の準備や国家試験対策など、学年ごとの課題に応じた支援を受けることが可能です。
また、学習面にとどまらず、卒業後の働き方や将来の目標について相談できる場としても活用できるため、進路に悩んだときなどにも心強い存在となるでしょう。
参考:充実した学習サポート体制|東京薬科大学
参考:学習支援室|北里大学薬学部
2-3.学業以外のリフレッシュ方法を見つける
心の余裕を保つためには、学業ばかりにならないよう、自分に合ったリフレッシュ方法を見つけることも大切です。
例えば、短時間の運動を行ったり、趣味の時間を持ったりと、気分転換できる習慣を取り入れることで、ストレスがたまりにくくなります。
継続的にリフレッシュの時間を確保することで、気持ちの切り替えがしやすくなります。その結果、学業への集中力も保ちやすくなるでしょう。
2-4.同級生や先輩に相談する
自身と同じ環境にいる同級生や先輩に悩みを打ち明けてみることも、心の整理に役立つ方法のひとつです。
身近な人と話すことで気持ちが落ち着き、新たな視点が得られることもあります。
3.薬学部の魅力やメリットとは?
薬学部は大変なこともありますが、その分得られるものも多くあります。薬学部ならではの魅力やメリットについて見ていきましょう。

3-1.薬学分野に関する専門知識を身に付けられる
薬学部の魅力のひとつは、薬に関する知識を体系的に学べることです。講義や実習を通して、薬の基礎から応用まで幅広く学べるため、薬の作用や適正な使い方を理論的に理解できるようになります。
学んでいく内容に難しさを感じることもあるかもしれませんが、学んだ知識がつながったときや、実習でそれを生かせたときの達成感は、大きなやりがいとなるでしょう。
また、薬や医療に関する専門性が高まることで、勉強内容が将来の仕事に直結しているという実感も得られやすくなります。
3-2.学生同士で共に過ごせる時間が長い
6年制の薬学部は、一般的な4年制の学部よりも学生同士で過ごす時間が長くなります。実習や国家試験といった共通の目標に向けて取り組む中で、自然と協力し合う関係が築かれやすいのが特徴です。
講義や実験、グループワークを通じて日常的に顔を合わせる機会も多く、友人との関係が深まりやすい環境といえるでしょう。
お互いに励まし合いながら過ごす6年間は、知識の習得だけでなく、人とのつながりという点でも、かけがえのない経験となるはずです。
3-3.卒業後に薬剤師としてキャリア構築を目指せる
6年制薬学部を卒業し、国家試験に合格すれば、薬剤師としてのキャリアを始められます。薬剤師は資格を生かして働ける専門職であり、病院や薬局など、さまざまな現場で活躍しています。
病院薬剤師は、医師や看護師と連携し、チーム医療の一員として患者さんの治療に深く関わります。調剤業務や薬物治療の提案を通じて、治療効果の向上に貢献できる点が魅力のひとつです。
一方、薬局薬剤師は地域の健康を支える存在として、患者さん一人ひとりと向き合いながら継続的なサポートを行います。人の役に立つ、やりがいのある専門職を目指せるのは、薬学部の大きな魅力のひとつといえるでしょう。
🔽 薬剤師のやりがいについて解説した記事はこちら
4.薬学部で有意義な学生生活を送るためのポイント
薬学部の6年間は、学年によって学習内容が大きく変わります。大学によっても異なりますが、一般的な薬学部の学習内容を踏まえて、1~2年生・3~4年生・5~6年生の段階ごとに有意義な学生生活を送るためのポイントを紹介します。

4-1.1~2年生
1~2年生は、薬学の基礎科目を中心に学ぶ時期です。化学・生物・物理・数学など、高校で学んだ理系科目の内容をさらに深掘りし、薬学の専門的な学びへとつなげます。この時期に基礎を固めておくことで、後々の実習や国家試験の勉強にも役立ちます。
授業以外にもサークル活動やアルバイトなどを通じて人間関係を広げておくと、後の学年で助け合える関係を築きやすくなるでしょう。
4-2.3~4年生
3年生からは、薬の専門知識を本格的に学ぶ段階に入ります。薬理学や病態学、医療薬学など、実際の医療現場を意識した講義が増えるため、理解力と応用力が一層求められるでしょう。
4年生の後期には「実務前実習」が始まり、薬剤師としての基礎的な実践力や現場感覚を養うことになります。「薬学共用試験(CBT・OSCE)」の受験も控えており、この試験に合格して初めて5年生の実務実習へと進めます。
勉強量が一層増える中で、計画的な学習が求められる時期です。日々の積み重ねに加え、同級生と協力したり、分からないことがあれば教員に積極的に相談したりすることが大切です。
4-3.5~6年生
5年生になると、実務実習が始まります。薬局と病院の両方で約半年間にわたり実習を行い、これまで学んだ知識を現場で応用する力を身に付けます。
6年生では、3年次から継続してきた卒業研究の成果を卒業論文としてまとめ、発表します。また、多くの大学で卒業試験や薬剤師国家試験の対策が本格化し、勉強に集中する時間が増えてきます。
実習・研究・試験と負担が重なる時期ではありますが、自分の将来や進路を意識しながら取り組むことで、学習の方向性が定まりやすくなるでしょう。
参考:薬学科で学べること|広島大学
参考:薬学部のカリキュラム|立命館大学薬学部
参考:薬剤師国家試験|厚生労働省

5.薬学部の6年間を充実させよう
薬学部が「大変」「つらい」といわれることがある理由としては、勉強量の多さや5年次の約半年間に及ぶ実務実習、進級や卒業に必要な要件の厳しさ、学費の負担の大きさなどが挙げられます。困難を感じたときには、改めて自分の目標を明確にし、大学の支援制度を活用したり、学業以外のリフレッシュ方法を見つけたりすることが大切です。仲間と励まし合いながら努力を重ねた経験は、達成感や自信につながり、薬剤師を目指す道のりをより充実したものにしてくれるでしょう。

執筆/篠原奨規
2児の父。調剤併設型ドラッグストアで勤務する現役薬剤師。薬剤師歴8年目。面薬局での勤務が長く、幅広い診療科の経験を積む。新入社員のOJT、若手社員への研修、社内薬剤師向けの勉強会にも携わる。音楽鑑賞が趣味で、月1でライブハウスに足を運ぶ。
あわせて読みたい記事