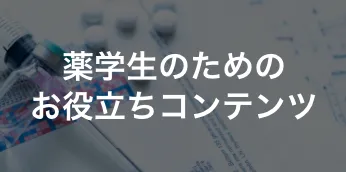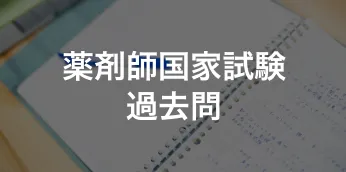薬剤師になるために奨学金を利用するのであれば、給付型や貸与型などの種類や奨学金制度を設けている企業・自治体、返済免除の可否などについて詳しく知っておくことが大切です。本記事では、奨学金の概要や薬学部の学費、奨学金を利用する薬学生の割合、平均的な返済額・返済期間について紹介するとともに、奨学金の主な種類や奨学金が返せないときの対応方法についても解説します。

- 1.奨学金とは?
- 1-1.薬学部の学費はいくらかかる?
- 1-2.薬学部で奨学金を利用している学生の割合はどのくらい?
- 1-3.薬学部の奨学金の平均返済額はいくらくらい?
- 1-4.薬学部の奨学金を返済するまでの平均年数はどのくらい?
- 2.薬学生が利用できる奨学金の主な種類
- 2-1.第一種奨学金
- 2-2.第二種奨学金
- 2-3.入学時特別増額貸与奨学金
- 2-4.高等教育の修学支援新制度
- 2-5.大学の奨学金制度
- 2-6.企業や病院などの奨学金制度
- 3.薬学部の奨学金が返せないときの対応方法
- 3-1.日本学生支援機構の減額返還制度を利用する
- 3-2.日本学生支援機構の返還期限猶予制度を利用する
- 3-3.企業や自治体などの奨学金返済免除・支援制度を利用する
- 4.薬剤師になるために奨学金制度を利用するなら
1.奨学金とは?
奨学金とは、一般的に経済的な理由で修学が困難な学生の教育関連の費用をサポートするために提供される金銭のことで、「給付型」や「貸与型」があります。給付型は返済の必要がない奨学金で、貸与型は返済しなければならない奨学金を指します。
奨学金は、学生が大学や大学院などの高等教育を受けるための費用として活用されるのが一般的です。教育基本法第4条第3項において「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。」と定められており、日本では独立行政法人日本学生支援機構や都道府県、市区町村のほか、学校、民間団体などが奨学金制度を設けています。
参考:教育基本法|文部科学省
1-1.薬学部の学費はいくらかかる?
薬学部の学費は、国公立大学と私立大学で大きく異なり、私立大学の場合は、特に大学によって学費の差が大きいです。
| 6年間で必要な学費の目安 | |
|---|---|
| 国立大学 | 約350万円~410万円 |
| 公立大学 | 約340万円~400万円 |
| 私立大学 | 約940万円~1,440万円 |
参考:薬学部の学費はいくらかかる?国公私立大学の学費一覧や免除制度などを紹介
※入学料と6年間分の授業料などを合算したおよその学費のため、別途費用が必要になる場合もあります。詳しくは大学のホームページをご確認ください。
国公立大学と私立大学では、6年間で必要な学費に600万円~1,000万円程度の差があり、私立大学は国公立大学と比較して高額であることが分かります。
1-2.薬学部で奨学金を利用している学生の割合はどのくらい?
厚生労働省の資料によると、薬学部の5~6年次に奨学金を利用している薬学生の割合は35%とされています。
回答者2,302人のうち805人が利用しており、奨学金を活用している薬学生は一定数いることが分かります。
参考:第12回薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会 参考資料2 検討会のとりまとめへの対応状況等(薬剤師確保・卒後臨床研修)|厚生労働省

1-3.薬学部の奨学金の平均返済額はいくらくらい?
厚生労働省の資料によると、薬学部の奨学金の平均返済額は、病院薬剤師・薬局薬剤師ともに総額450万円前後です。ただし、返済総額には1.7万円~3,000万円以上と幅があります。
| 平均金額 | 最小値 | 最大値 | |
|---|---|---|---|
| 病院薬剤師 | 約458万円 | 1万7,000円 | 3,000万円 |
| 薬局薬剤師 | 約446万円 | 5万円 | 2,000万円 |
参考:第12回薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会 参考資料3 薬剤師確保のための調査・検討事業 報告書(令和3年度厚生労働省医薬・生活衛生局総務課委託事業)|厚生労働省
🔽 薬剤師の就職先について解説した記事はこちら
1-4.薬学部の奨学金を返済するまでの平均年数はどのくらい?
厚生労働省の資料によると、薬学部の奨学金を返済するまでの平均年数は、病院薬剤師が15.6年、薬局薬剤師は15年です。
| 平均年数 | 最小値 | 最大値 | |
|---|---|---|---|
| 病院薬剤師 | 15.6年 | 1年 | 40年 |
| 薬局薬剤師 | 15.0年 | 1年 | 50年 |
参考:第12回薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会 参考資料3 薬剤師確保のための調査・検討事業 報告書(令和3年度厚生労働省医薬・生活衛生局総務課委託事業)|厚生労働省
🔽 薬剤師の年収について解説した記事はこちら
2.薬学生が利用できる奨学金の主な種類
薬学生が利用できる日本学生支援機構(JASSO)の奨学金には、以下のようなものがあります。
● 第二種奨学金
● 入学時特別増額貸与奨学金
● 高等教育の修学支援新制度
そのほかにも、大学や企業が設ける奨学金制度があります。ここでは、それぞれについて詳しくお伝えします。
2-1.第一種奨学金
第一種奨学金とは、国内の大学院や大学などに在学中または在学予定の学生・生徒が対象となる奨学金です。無利子の奨学金で、借りた金額だけを返済します。申し込むには学力基準や家計基準を満たす必要があります。
貸与額は、大学院や大学、短期大学など学校種別や、国立や公立、私立などの設置者、通学形態によって異なります。国公立大学や私立大学に通う場合に借りられる奨学金は、以下のいずれかの金額です。
| 自宅通学 | 自宅外通学 | |
|---|---|---|
| 国公立 | ● 2万円/月 ● 3万円/月 ● 4万5000円/月 |
● 2万円/月 ● 3万円/月 ● 4万円/月 ● 5万1,000円/月 |
| 私立 | ● 2万円/月 ● 3万円/月 ● 4万円/月 ● 5万4,000円/月 |
● 2万円/月 ● 3万円/月 ● 4万円/月 ● 5万円/月 ● 6万4,000円/月 |
自宅外通学の場合は、自宅通学の月額を選択することも可能です。また、申し込み時の家計収入が一定額以上の場合は、各区分の最高月額を選択することができません。
2-2.第二種奨学金
第二種奨学金も国内の大学院や大学などに在学中または在学予定の学生・生徒が対象となる奨学金です。有利子の奨学金で、借りた金額に利子を追加した金額を返済しなければなりません。
選考基準は第一種奨学金と比較して緩やかで、大学の場合、貸与金額は月額2万円~12万円(1万円刻み)ですが、私立大学の薬学部については、上限額に2万円をプラスした月額14万円まで増額できます。
参考:第二種奨学金の貸与月額|JASSO
2-3.入学時特別増額貸与奨学金
入学時特別増額貸与奨学金とは、入学した初月の分のみ増額して貸与する利子付きの奨学金です。
第一種奨学金または第二種奨学金を貸与する人のうち、以下のいずれかの要件を満たす場合に入学時特別増額貸与奨学金を借りられます。
(4人世帯の給与所得者の場合年収400万円程度以下)
● 日本政策金融公庫の「国の教育ローン」に申し込んだが利用できなかった世帯
貸与額は以下から自由に選択できます。
● 20万円
● 30万円
● 40万円
● 50万円
ただし、入学前の貸与や入学時特別増額貸与奨学金だけの貸与はできません。

2-4.高等教育の修学支援新制度
高等教育の修学支援新制度とは、2020年4月からスタートした奨学金の返済が不要な給付型の奨学金です。
学生が経済的な理由で大学や専門学校への進学を諦めないようにすることを目的としています。
給付型奨学金に加え、授業料や入学金の免除または減額をして、以下の高等教育の無償化をします。
● 短期大学
● 高等専門学校
● 専門学校
給付型奨学金の支給は日本学生支援機構が実施しますが、授業料や入学金の免除・減額は大学等が行うため、各大学等に詳細を確認することとされています。
2-5.大学の奨学金制度
大学によっては独自の奨学金制度を設けている場合があります。給付型や貸与型の奨学金に加えて、特待生制度や学費減免制度などを設けているところもあり、学生が安心して勉学に専念できるよう環境を整えています。
大学によって、制度や奨学金を利用するための条件はさまざまなため、詳しくは各大学のホームページを確認しましょう。
2-6.企業や病院などの奨学金制度
近年、人材確保を目的として奨学金制度を設ける企業や病院などが見られます。企業や病院が設ける奨学金制度では、薬学部卒業後、自社に就職し、一定期間働くことを条件としているところがほとんどです。
返済の一部または全額免除されることはメリットですが、卒業時に働きたい職種や企業などが、奨学金を借りた時点と変わった場合には、自身の希望とは異なる職場で働くことになります。そのため、企業や病院の奨学金制度を利用する場合は、就職活動を行うつもりで利用先を選択することが大切です。
3.薬学部の奨学金が返せないときの対応方法
薬学部在籍中に借りた奨学金が返せなくなるケースとして、失業や災害、傷病などが挙げられます。日本学生支援機構では、奨学金の返済が難しくなった場合の対応方法を提示していますが、基本的にはいずれも奨学金の返済そのものを免除・減額する制度ではありません。
ただし、奨学金を貸与した本人が、死亡または精神・身体の障害により働けない場合は、返還未済額の全部または一部の返還が免除されます。
ここでは、日本学生支援機構の減額返還制度・返還期限猶予制度と、企業や自治体の奨学金返済支援制度について紹介します。
3-1.日本学生支援機構の減額返還制度を利用する
減額返還制度とは、災害や傷病、失業などにより返還が難しくなった場合に、一定期間、返還金額を減額して、月々の返済額を少なくする制度です。減額返還制度を利用する場合は、自己申請が必要です。
減額返還制度は、返還期間が延長されるものであるため、返還総額は減額されません。また、すでに支払いが延滞している場合には利用できないため、延滞する可能性がある場合は、早めに申請しておくとよいでしょう。
参考:減額返還制度の概要|JASSO
3-2.日本学生支援機構の返還期限猶予制度を利用する
返還期限猶予制度とは、奨学金の返還が困難な場合に、申請することで返還しない期間を設ける制度のことです。
審査で承認された期間は、返還の必要がありませんが、返還すべき元金や利子は免除されません。そのため、返還期限が延長された分だけ、返還終了年月も延長されます。
参考:返還を待ってもらう(返還期限猶予)|JASSO
3-3.企業や自治体などの奨学金返済免除・支援制度を利用する
日本学生支援機構では、自治体による奨学金返還支援制度を紹介しています。地域内への就職者を対象にした助成制度や、奨学金返還支援事業を実施する企業を対象にした補助金制度などがあります。
また、地域の薬剤師の確保を目的として、地域内の病院等に一定期間勤務することを返還免除の要件とする自治体もあります。
そのため、失業等で奨学金の返還が難しくなった場合や返済総額が大きい場合などは、自治体や企業の奨学金返済免除・支援制度を利用するのも方法のひとつです。
参考:都道府県(基金設置団体)|JASSO
参考:「山形県病院薬剤師奨学金返還支援事業」について|山形県

4.薬剤師になるために奨学金制度を利用するなら
薬剤師になるために奨学金制度を利用するのであれば、どんな奨学金があるのかを把握して、自身に合った制度を利用するとよいでしょう。一般的には日本学生支援機構の奨学金制度を利用するケースが多いかもしれませんが、大学や企業などの制度を活用することも可能です。
就職後は、完済できるよう計画的に自身の収支を管理することはもちろん、返還が難しくなった場合には早めに対応することが求められます。奨学金制度を利用するのであれば、奨学金の種類やシステム、卒業後の返済計画についてもしっかり把握しておきましょう。
🔽 薬剤師になる方法について解説した記事はこちら

薬剤師ライター。2児の母。大学卒業後、調剤薬局→病院→調剤薬局と3度の転職を経験。循環器内科・小児科・内科・糖尿病科など幅広い診療科の経験を積む。2人目を出産後、仕事と子育ての両立が難しくなったことがきっかけで、Webライターとして活動開始。転職・ビジネス・栄養・美容など幅広いジャンルの記事を執筆。趣味は家庭菜園、裁縫、BBQ、キャンプ。
あわせて読みたい記事