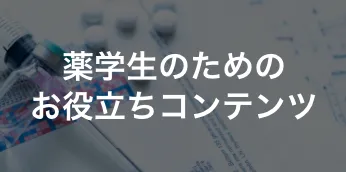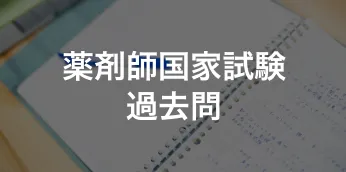薬学部の学生の中には、就職活動を進めるにあたりインターンシップに行くのか、行かないのか迷っている人もいるかもしれません。本記事では、薬学部のインターンシップについて、始まる時期、職場ごとの特徴、参加するメリット、参加方法などを解説しているので、ぜひ参考にしてください。

- 1.インターンシップとは?
- 2.薬学部向けのインターンシップはいつから始まる?
- 2-1.エントリーの時期
- 2-2.インターンシップに参加する時期
- 3.薬学部向けのインターンシップの特徴
- 3-1.病院
- 3-2.調剤薬局
- 3-3.ドラッグストア
- 3-4.製薬企業
- 4.薬学生がインターンシップに参加するメリット
- 4-1.自分がどの職業に向いているのか適性が分かる
- 4-2.企業や薬局などに対する理解度が深まる
- 4-3.業務を体験することで自分の将来像が見えてくる
- 4-4.薬学生同士の交流が深まる
- 4-5.採用によい影響を与える可能性がある
- 5.薬学生がインターンシップに行かないのはアリ?
- 5-1.無理にインターンシップへ参加する必要はない理由
- 5-2.Webインターンシップを検討しよう
- 6.薬学生がインターンシップに参加する方法
- 6-1.大学の掲示板やホームページなどをチェックして申し込む
- 6-2.企業や病院のホームページから申し込む
- 6-3.就職情報サイトを活用して申し込む
- 7.薬学部のインターンシップは現場体験ができる貴重な機会
1.インターンシップとは?
インターンシップとは、一般的に学生が専攻分野や将来のキャリアに関連した就業体験を行う制度のことを指します。
参考:インターンシップの推進に当たっての基本的考え方|文部科学省
興味のある企業を訪問したり、仕事を体験したりできるため、社内の雰囲気や業務の流れなどを詳しく知るのに役立つでしょう。
Webインターンシップを開催している企業であれば、遠方でも参加できるため、就職先を考える上で参考になります。
インターンシップの実施期間は、短いもので数時間から数日程度、長いものでは数カ月と企業によってさまざまですが、薬学生のインターンシップについては短期のものが中心となるでしょう。
2.薬学部向けのインターンシップはいつから始まる?
インターンシップに参加するためには、基本的にエントリーを行う必要があります。ただし、すべての企業がインターンシップを行っているわけではありません。
参加人数が決まっているものもあるため、興味のある企業が見つかったら、インターンシップの有無やエントリーの時期、参加人数などを確認しましょう。
2-1.エントリーの時期
「マイナビ薬学生Switch」が公開している調査結果によると、6年制薬学部の場合は5年次、4年制薬学部の場合は3年次からインターンシップへのエントリーを行う薬学生が多いようです。
7月後半からインターンシップのエントリーを行う人が増え、10月~12月がエントリーのピークとなっています。5月以前にエントリーする薬学生も一定数いることから、早めにインターンシップへの参加を検討するケースも多いことが分かります。
参考:薬学部の先輩に聞いたインターンシップ&キャリア最新事情|マイナビ薬学生Switch
2-2.インターンシップに参加する時期
同じく「マイナビ薬学生Switch」が公開している調査結果によれば、インターンシップに参加する時期は11、12月が多いものの、5月以前や夏休み中の時間があるタイミングで参加している薬学生も少なくないようです。
なるべく早くインターンシップに参加しておくと、その後の学業のスケジュールに余裕ができるため、インターンシップの募集については随時、確認するのがおすすめです。
参考:薬学部の先輩に聞いたインターンシップ&キャリア最新事情|マイナビ薬学生Switch
マイナビでは、学生のインターンシップやキャリア形成をサポートする「インターンシップ&キャリア」というプログラムを設けています。インターンシップに興味のある薬学生は、活用してみてはいかがでしょうか。
参考:インターンシップ&キャリアとは|マイナビ2027

3.薬学部向けのインターンシップの特徴
薬学生を対象としたインターンシップにはさまざまなものがあります。ここでは、薬学部向けのインターンシップの特徴についてお伝えします。
3-1.病院
病院での薬剤師の主な仕事は、内服薬や注射などの調剤、がん化学療法、病棟業務、治験業務、院内製剤業務などが挙げられます。
そのため、病院のインターンシップでは、調剤業務や病棟業務について学んだり、院内の見学をしたりするのがメインです。大きな病院では、抗がん剤の調製やカンファレンスの見学などもできるでしょう。
また、薬剤師として働き始めて数年程度くらいの比較的年が近い先輩と交流できるチャンスもあるかもしれません。
🔽 病院薬剤師の仕事内容について解説した記事はこちら
3-2.調剤薬局
調剤薬局の仕事は、調剤業務や在宅業務などが挙げられます。調剤薬局のインターンシップでは、薬局内での業務はもちろんのこと、医療機関や患者さんとの信頼関係をどのように築いているのか、在宅医療にどう関わっているのかなどを学べます。
薬局によっては、薬の味見やグループワーク、先輩との交流会などがインターンシップのプログラムに組み込まれている場合があります。
🔽 薬局薬剤師の仕事内容について解説した記事はこちら
3-3.ドラッグストア
ドラッグストアの仕事は、調剤業務や一般用医薬品の販売、品出し、レジ対応、マネジメント業務などです。
ドラッグストアの特徴のひとつは、調剤業務や一般用医薬品の販売といった医療従事者としての仕事に加え、日用品や健康食品などを販売する業務がある点です。
薬剤師は医療従事者としてだけでなく、売り上げのために経営の視点を身に付けることが求められる部分もあります。ドラッグストアのインターンシップでは、調剤薬局との違いにも注目するとよいでしょう。
🔽 ドラッグストア薬剤師の仕事内容について解説した記事はこちら
3-4.製薬企業
製薬企業での仕事は、企業の特徴や配属先によって異なります。研究職や開発職、営業職、学術職などによって仕事内容が異なるため、インターンシップに参加する場合は見学できる部署などを確認するとよいでしょう。
製薬企業のインターンシップでは、企業の信念や在り方について学ぶ機会が設けられたり、業務内容を見学できたりするほか、社員との交流会、インターンシップに参加している学生とのグループワークなどが行われることもあります。
🔽 企業薬剤師の仕事内容について解説した記事はこちら
4.薬学生がインターンシップに参加するメリット
薬学生の中には、インターンシップに興味があっても参加をためらう人もいることでしょう。インターンシップが実習や定期試験などの時期と重なってしまう場合もあり、参加する余裕があるのか不安に思うことがあるかもしれません。
しかし、できることなら、インターンシップには参加しておくとよいでしょう。ここでは、インターンシップに参加するメリットについてお伝えします。
4-1.自分がどの職業に向いているのか適性が分かる
薬学部を卒業した後の進路としては、病院や調剤薬局、製薬企業などがあります。「調剤薬局で働きたい」「MRになりたい」と思っていても、いざ働いてみると自分には合っていなかったと感じることがあるかもしれません。
こうした入社後のミスマッチを防ぐのに役立つのが、インターンシップのメリットです。インターンシップで体験するのは業務のほんの一部ですが、雰囲気や業務の様子を見て「無理なく働けそうか」「興味を持てそうか」を確認することができます。
4-2.企業や薬局などに対する理解度が深まる
気になる就職先の情報は、知り合いからの口コミやインターネット検索などを通じて収集している人が多いのではないでしょうか。しかし、いくら念入りに情報収集をしても、職場の雰囲気をリアルに感じるのは難しいものです。
インターンシップでは、実際の職場を自分の目で見られるので、そこで働く人たちの様子や職場環境、スタッフ間の人間関係なども垣間見ることができる貴重な機会となるでしょう。
4-3.業務を体験することで自分の将来像が見えてくる
インターンシップを通して、実際にさまざまな業種の仕事に触れることで、それぞれの仕事のやりがいや課題、職場環境が肌感覚で理解しやすくなります。
また、座学だけでは分からない実務の流れを学び、チームの連携の重要性を実感する経験は、将来像をより鮮明に描くことにつながるでしょう。そのため、インターンシップは、進路の選択に自信を持つための貴重なステップとなります。
4-4.薬学生同士の交流が深まる
インターンシップにはさまざまな大学から薬学生が集まります。そのため、他大学の薬学生と交流を広げるチャンスです。
他大学の薬学生と接点ができることで視野が広がったり、ほかの就職先に興味を持つきっかけができたり、国家試験の情報を交換できたりする可能性もあります。
4-5.採用によい影響を与える可能性がある
インターンシップを通して実際に業務を体験することで、企業への理解が深まり、志望動機やキャリアの目標をより具体的に伝えられるようになります。
インターンシップ経験の有無が選考に直接影響するとは限りませんが、業務を実際に体験したという実績は、企業側に熱意や自身の適性をアピールする際にも役に立つでしょう。結果として、採用につながる可能性が高まると考えられます。
5.薬学生がインターンシップに行かないのはアリ?
薬学生がインターンシップに参加しない選択をすることも、状況によっては問題ないと考えられます。ここでは、無理にインターンシップへ参加する必要がない理由と、Webインターンシップについてお伝えします。
5-1.無理にインターンシップへ参加する必要はない理由
実習や授業で多忙な薬学生にとって大切なことは、基本的に進級・卒業を目指すことです。インターンシップへの参加が時間的・体力的な負担となり、進級・卒業に支障をきたしてしまうのは本末転倒といえます。
また、進路がすでに明確である場合は、無理にインターンシップに参加しなくても納得のいく就職活動ができるかもしれません。
とはいえ、前述のとおり、インターンシップへの参加は就職活動をする上でのメリットになります。インターンシップに参加しないことが、就職活動に不利に働くとは限りませんが、別の形で職場理解や企業研究を深める工夫が必要です。自分に合った方法で進路選択の準備をするようにしましょう。
5-2.Webインターンシップを検討しよう
企業によっては、Webインターンシップを行っているところもあります。「忙しくてインターンシップまでなかなか手が回らない」という人は、Webで参加できるインターンシップも検討してはいかがでしょうか。
Web会議システムを利用して説明を聞いたり、他の参加者や職場の人と意見を交わし合ったりできます。Webインターンシップなら、遠方の企業であっても気軽に参加しやすく、移動も必要ないため時間を有効活用できます。

6.薬学生がインターンシップに参加する方法
インターンシップに申し込む方法は、主に次の3つがあります。自分に合う方法で申し込んでみましょう。
6-1.大学の掲示板やホームページなどをチェックして申し込む
就職活動が始まる時期になると、大学内の掲示板やホームページなどに、インターンシップや求人の情報が掲載されるようになります。
大学によっても異なりますが、大手だけでなく中小や個人経営の情報も多く紹介されている場合があり、掲示板でしか見つけられないような情報もあるかもしれません。定期的にチェックしておくと、参加するインターンシップの選択肢の幅を広げられるでしょう。
6-2.企業や病院のホームページから申し込む
多くの場合、春・秋のインターンシップ開催前になると、薬局・病院や企業のホームページに開催概要や募集要項が掲載されます。インターンシップの実施期間や受け入れ条件を確認して、応募方法に従って申し込みましょう。
応募先によっては、応募動機や課題の提出を求められるケースがあります。こまめにチェックして早めに準備を進めることが大切です。
6-3.就職情報サイトを活用して申し込む
複数の就職先が気になっている場合には、薬学生向けの就職情報サイトを活用すると便利です。
サイトによっては、あらかじめ気になる企業や調剤薬局などをお気に入りに登録しておくとインターンシップや選考のお知らせがメールで届く機能などが設けられているため、活用してみましょう。

7.薬学部のインターンシップは現場体験ができる貴重な機会
インターンシップに参加すれば、気になる職場のリアルな情報を収集できたり、将来像を明確にイメージできるようになったりします。就職後のミスマッチを防ぎ、理想と現実とのギャップを減らす方法としても有効でしょう。
多くのインターンシップは、6年制の場合は5年次、4年制の場合は3年次から始まります。6年制の薬学生は、薬局実習や病院実習と時期が重なり、参加が難しいかもしれません。Webインターンシップも検討して、スケジュールを調整してみてはいかがでしょうか。

薬剤師ライター。病院・薬局で幅広い診療科を経験。現在は2児の子育てをしながら、Webライターとして活動中。専門的な資料や情報をわかりやすくかみ砕き、現場のリアルに寄り添う言葉で伝えることを大切にしている。同じ薬剤師として、日々の悩みやモヤモヤに共感しながら、少しでも役立つヒントや気づきを届けられるように試行錯誤中。
あわせて読みたい記事