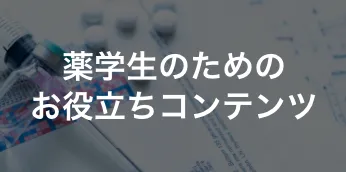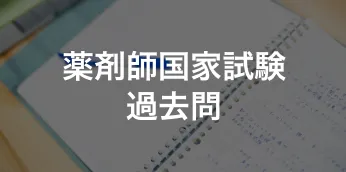将来の進路を考える中で「薬学部に編入したい」と思う方もいるのではないでしょうか。特に文系出身の方や社会人の場合は、編入ができるのか気になるかもしれません。本記事では、薬学部への編入可否をはじめ、薬学部に編入するメリット、出願から入学までの流れ、編入における注意点について詳しく解説します。

- 1.薬学部に編入することはできる?
- 1-1.国公立大学の薬学部への編入は可能?
- 1-2.社会人から薬学部への編入は可能?
- 1-3.文系から薬学部への編入は可能?
- 2.薬学部に編入するメリット
- 2-1.医療や薬に関する専門知識を身に付けられる
- 2-2.薬剤師国家試験の受験資格を得られる
- 2-3.創薬や臨床応用など薬学分野の研究に関与できる
- 3.薬学部へ編入する方法
- 3-1.出願資格を確認する
- 3-2.出願書類を提出する
- 3-3.編入試験を受ける
- 3-4.入学手続きを行う
- 4.薬学部に編入するときの注意点
- 4-1.募集人数が限られるため難易度が高い
- 4-2.学費のための資金計画を立てておく
- 4-3.薬剤師を目指す場合、6年制薬学部を選択する
- 5.薬学部から他学部への編入はできる?
- 6.医療や薬の分野で活躍したいなら、薬学部への編入を検討しよう
1.薬学部に編入することはできる?
薬学部への編入は可能ですが、すべての大学で編入制度を導入しているわけではなく、年度によって募集の有無が変わる場合もあります。
ここからは、国公立大学への編入の可否に加えて、社会人や文系出身の方が薬学部を目指せるのかについて、それぞれのケースを見ていきましょう。
1-1.国公立大学の薬学部への編入は可能?
2025年度時点で、国公立大学の薬学部で編入制度を実施している大学はありません。そのため、薬学部への編入を目指す場合は、基本的に私立大学が選択肢となります。
なお、現在国公立大学に在籍している場合、同一大学内で薬学部への「転学部」が認められていることもあります。転学部は、大学入学共通テストの結果や在学中の成績などをもとに審査されるのが一般的です。薬学部への転学部を検討している場合、まずは大学に確認してみるとよいでしょう。
参考:転学部・転学科|大分大学
参考:千葉大学転部,転科等の取扱いに関する細則|千葉大学
1-2.社会人から薬学部への編入は可能?
社会人から薬学部へ編入することは可能です。例えば、日本大学薬学部の2026年度編入試験では、「大学を卒業した者または2026年3月に卒業見込みの者」といった出願資格が明記されており、薬学部以外の学部出身でも受験が認められています。
編入制度を利用すると、2年次や3年次からの入学となるケースもあるため、一般入試で1年次から通う場合と比べて、卒業までの期間を短縮できるのが特徴です。
参考:編入学試験(一般)|日本大学薬学部
1-3.文系から薬学部への編入は可能?
文系学部からでも、薬学部への編入は可能です。ただし、大学によっては出願資格に制限があり、理学・工学・農学といった理系学部の出身者に限定しているケースもあります。そのため、希望する大学がどのような出願条件を設けているかを事前に確認しましょう。
また、書類選考に加えて学力試験や面接などの選抜が行われるため、あらかじめ試験対策を進めておくことが大切です。特に理系の専門知識が必要となるケースもあるため、試験範囲や出題傾向を把握した上で、計画的に対策を進めましょう。
2.薬学部に編入するメリット
薬学部に編入すると、次のようなメリットが得られます。
● 薬剤師国家試験の受験資格を得られる
● 創薬や臨床応用など薬学分野の研究に関与できる
それぞれのメリットについて見ていきましょう。
2-1.医療や薬に関する専門知識を身に付けられる
薬学部に編入することで、薬に関する専門知識を体系的に学べます。例えば、有機化学や物理化学を通じて薬の構造や性質への理解を深め、創薬や製薬に必要な技術を身に付けられます。また、生化学や薬理学を通じて、人体や疾患に対する薬の働きを学ぶことで、医療における薬の役割を深く理解できるようになるでしょう。
さらに、上級学年になると、自分の関心や希望する進路に応じた専門科目を学べるケースも少なくありません。薬に対する幅広い視点と専門性を得られるのが、薬学部の大きな魅力です。
2-2.薬剤師国家試験の受験資格を得られる
6年制課程の薬学部を卒業すると、国家試験の受験資格が与えられます。薬剤師は国家資格であり、資格を取得するためには国家試験に合格しなければなりません。
その受験要件として、6年制薬学部の卒業(見込み)が定められています。薬剤師になると、病院や調剤薬局、製薬会社、行政機関など、さまざまな職場で専門性を生かしたキャリアを築けます。
🔽 薬剤師になる方法について解説した記事はこちら
2-3.創薬や臨床応用など薬学分野の研究に関与できる
薬学部では、創薬や臨床現場への応用を見据えたさまざまな研究が行われています。実践薬学系・応用薬学系・基礎薬学系といった幅広い分野の中から、自分の興味や将来の目標に合った研究に取り組むことが可能です。
製薬企業や医療機関などで創薬や臨床応用に関わる仕事を目指す方にとって、貴重な経験を積める環境といえるでしょう。
参考:6年制薬学部での学び|京都薬科大学
参考:薬科学科|横浜薬科大学
参考:薬剤師国家試験|厚生労働省
参考:研究室紹介|日本大学薬学部
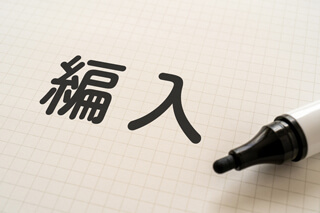
3.薬学部へ編入する方法
薬学部への編入は、募集人数が限られている上に、出願条件や試験内容は大学ごとに異なるため、早めの情報収集が欠かせません。ここからは、薬学部へ編入する方法について、具体的に解説します。
3-1.出願資格を確認する
薬学部への編入を目指すと決めたら、はじめに志望する大学の出願資格を確認しましょう。出願資格は、各大学の公式ホームページや募集要項で公開されており、以下のような条件が具体的に記されています。
● 大学の在籍年数や修得済みの単位数
● 出身学部(文系や理系など)
● 特定の科目の履修要件(化学、生物、物理、数学など)
一例として、明治薬科大学の2026年度編入試験では、次の条件が示されています。
● 学士の学位を有する者、または2026年3月取得見込みの者
● 大学に2年以上在学し62単位以上修得した者、または2026年3月修得見込みの者
● 短期大学・高等専門学校卒業者、または2026年3月卒業見込みの者
● 文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校の専門課程を修了した者、または2026年3月修得見込みの者(但し、大学入学資格を有する者)
● 文部科学大臣が定める基準を満たす高等学校の専攻科の課程を修了した者、または2026年3月修了見込みの者(但し、修業年限が2年以上であること)
参考:特別選抜|明治薬科大学
出願資格は大学によって異なり、募集時期や入学年次もさまざまです。年度ごとに条件が変わることもあるため、最新の情報を確認するようにしましょう。
3-2.出願書類を提出する
出願資格を満たしていることを確認したら、出願書類を用意します。主な出願書類は以下のとおりです。
● 志望理由書
● 成績証明書
● 卒業(見込み)証明書
大学や経歴によって提出する書類は異なるため、各大学のホームページで最新の情報を確認してください。
また、入学志願票や志望理由書は指定の様式が用意されているケースも少なくありません。提出方法(郵送や窓口持参など)や提出期限も確認しておき、余裕を持って準備を進めましょう。
3-3.編入試験を受ける
出願書類が受理されたあとは、編入試験を受けます。選抜方法は大学によって異なりますが、書類選考に加えて、学力試験や面接が行われるのが一般的です。
学力試験では、数学や化学、生物といった理系科目が出題されるケースが多く見られます。大学によって試験科目や配点、出題範囲が異なるため、志望校の公式ホームページで情報を確認しましょう。
特に文系出身の方や社会人は、理系科目の学び直しが必要になることもあるため、余裕を持って対策を進めることが大切です。
3-4.入学手続きを行う
合格後は、入学金や授業料の納付、必要書類の提出などの入学手続きが必要です。提出方法や支払い期限などの詳細は、合格通知と合わせて送付される案内に記載されている場合が多いため、内容をよく確認して手続きを進めましょう。
期限を過ぎてしまうと入学できなくなる可能性があるため、早めに取りかかることが大切です。
参考:特別選抜|明治薬科大学
参考:編入学試験(一般)|日本大学薬学部
4.薬学部に編入するときの注意点
薬学部への編入には、いくつか押さえておくべき注意点があります。募集人数や学費、6年制・4年制の違いなど、編入先の条件をよく確認した上で計画的に準備を進めることが大切です。
4-1.募集人数が限られるため難易度が高い
編入制度は、募集人数が非常に少なく、難易度が高い傾向があります。そのため、学力試験や面接などの選考を突破するための入念な対策が必要です。
編入を実施している大学の情報を早めに収集して対策を進めましょう。
4-2.学費のための資金計画を立てておく
薬学部へ編入すると、入学金や授業料などでまとまった費用が必要になります。初年度に数百万円かかる場合もあるため、あらかじめ十分な資金計画を立てておくことが大切です。
また、6年制の薬学部では在学期間が長期にわたるため、毎年の学費や生活費も見越して計画しておく必要があるでしょう。
🔽 薬学部の学費について解説した記事はこちら
4-3.薬剤師を目指す場合、6年制薬学部を選択する
薬学部には4年制と6年制の2つの課程があり、薬剤師を目指す場合は6年制を選ぶ必要があります。6年制では、薬剤師国家試験の受験資格を得るために必要なカリキュラムが組まれており、実務実習や国家試験対策も含まれています。
一方、4年制は研究職などを目指す方向けの課程で、薬剤師国家試験の受験資格は得られません。薬剤師になりたい場合は、必ず6年制を選びましょう。
参考:薬剤師国家試験|厚生労働省
🔽 薬学部の6年制と4年制の違いについて解説した記事はこちら

5.薬学部から他学部への編入はできる?
他学部から薬学部への編入と同様、薬学部から他学部への編入は可能です。特に理学・工学・農学など薬学と関連性の高い理系学部は、学問領域が近いため編入しやすいと考えられます。
一方で文系学部への編入では、薬学では扱わない分野が試験科目になることがあり、対策が難しくなる場合もあるでしょう。
さらに、編入先によっては文系科目の単位取得が条件になっていることもあるため、事前の確認が欠かせません。
参考:2025年度島根大学法文学部【3年次編入学】学生募集要項|島根大学
参考:令和8年度 大阪大学人間科学部第3年次編入学学生募集要項|大阪大学

6.医療や薬の分野で活躍したいなら、薬学部への編入を検討しよう
薬学部への編入は可能であるものの、2025年度時点において国公立大学では編入制度を実施していないため、私立大学が選択肢となります。社会人や文系出身でも、出願資格を満たせば受験が可能です。
薬学部に編入することで、薬に関する専門知識を体系的に学べる上、6年制薬学部を卒業すれば薬剤師国家試験の受験資格を得られます。また、製薬企業や医療機関などで創薬や臨床応用に関わる仕事を目指す方にとって、創薬や臨床応用などの研究ができる点は大きなメリットです。
医療や薬の分野で活躍したいなら、薬学部への編入はおすすめの選択肢です。志望校の最新情報をチェックして、今からできる準備を進めていきましょう。

執筆/篠原奨規
2児の父。調剤併設型ドラッグストアで勤務する現役薬剤師。薬剤師歴8年目。面薬局での勤務が長く、幅広い診療科の経験を積む。新入社員のOJT、若手社員への研修、社内薬剤師向けの勉強会にも携わる。音楽鑑賞が趣味で、月1でライブハウスに足を運ぶ。
あわせて読みたい記事