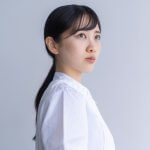医療におけるPOS(問題志向型システム)は、一見難しそうに感じるかもしれませんが、多くの薬剤師はPOSの考え方を実務で取り入れているでしょう。本記事では、POSの概要やメリット、SOAPとの違いやPOSの活用例などを解説し、POMR(問題志向型診療録)についてもお伝えします。
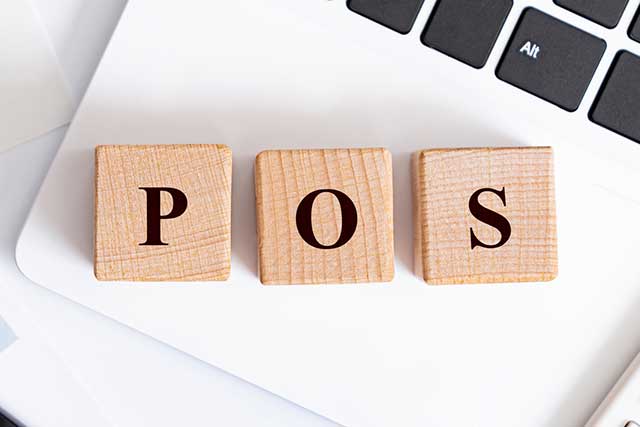
1.医療におけるPOS(問題志向型システム)とは?
医療におけるPOS(問題志向型システム)とは、Problem Oriented Systemの略で、患者さんの治療における問題を論理的に解決し、記録する一連の流れのことです。1968年にアメリカでローレンス・レナード・ウィード氏によって提唱されました。
参考:eラーニング|日本POS医療学会
1-1.薬剤師の業務におけるPOSとは?
薬剤師の業務におけるPOSの具体例として、糖尿病の治療中の患者さんが低血糖になった場合について紹介します。
低血糖の原因としては、以下のようなことが考えられます。
● 薬が効きすぎた
● 薬を飲みすぎた
薬剤師は、上記のような原因を予測して、患者さんから聞き取りを行いながら、以下のような解決方法を考えるでしょう。
● 体調変化がないのに頻繁に低血糖を起こしていたり、服用方法を頻繁に間違っていたりするのであれば、処方変更や一包化などを検討する
POSは、患者さんの基本情報や訴え(糖尿病の治療中、低血糖が起こった)などから、問題・課題(食欲が落ちたなど)を明らかにし、解決策を検討する一連の流れを記録しながら論理的に実施することです。そのため、日常業務でPOSの考え方を実践している薬剤師は多いのではないでしょうか。
今まで無意識にやっていた人も、改めてPOSの考え方を理解して実践すると、より丁寧に患者さんの状態や解決策を分析・検討できます。医療の質を向上させるためにも、POSを理解しておくのがおすすめです。
1-2.POSの構成
POSは、大きく3つのステップに分かれます。
| ステップ1 | POMRの作成 |
| ステップ2 | POMRの監査 |
| ステップ3 | 記録の修正 |
POSは、POMR(問題志向型診療録)を作成して情報を整理した後、内容の監査を行い、必要に応じて修正を行うことで、完全なPOMRに仕上げることを目的としています。
1-3.POSとSOAP
SOAPは、POMRの経過記録や退院時要約などを記載するときの記載方法を指します。SOAP形式とも呼ばれており、「S」「O」「A」「P」に記載する内容は、以下のとおりです。
| 意味 | 記載内容 | ||
| S | Subjective Data | 主観的情報 | ● 患者さんの訴え ● 相談 |
| O | Objective Data | 客観的情報 | ● 病歴 ● 診察所見 ● 検査データ |
| A | Assessment | 評価 | ● 判断 ● 考察 ● 評価 ● 目標意見 |
| P | Plan | 計画 | ● 診断 ● 治療方針 ● 薬物治療の開始・中止 |
SOAPは、各項目について箇条書きで記載し、誰が見ても一目で分かるように意識して作成するのがポイントです。
🔽 SOAP薬歴について解説した記事はこちら
1-4.POSのメリット
各地域で地域包括ケアシステムが構築されており、今後は病院薬剤師と薬局薬剤師がそれぞれの視点で情報共有することが求められます。
POSは、患者さんごとの問題点や対応方法などが論理的に記録できるため、医療連携の重要なツールとなるでしょう。薬剤師以外の医療関連職種とも連携する機会が増えたときにも、患者さんの情報や治療内容、治療経過をまとめるPOSにはメリットがあります。
また、POSは患者さんを中心に治療について考えることから、薬学的な視点に加えて、患者さんの心理状態や生活環境などを踏まえたサポートができます。多角的に課題や問題点を分析し、解決策を検討できる点もメリットといえるでしょう。
2.POMR(問題志向型診療録)とは?
2.問題リスト(Problem List)
3.初期計画(Initial Plans)
4.経過記録(Progress Notes)
参考:日本POS医療学会「POS医療認定師」のためのワークショップ資料|日本POS医療学会
POSでは、まずPOMRを作成することから始まります。POMRは基本的に4項目で構成されますが、患者さんの担当医が変わる場合や転院する場合、退院時などには、5つ目の項目として、退院時の要約や最終的な経過ノートの作成が加わります。そのため、患者さんによってPOMRは4つまたは5つの項目で作成されます。
ここでは、POMRの項目について詳しく見ていきましょう。

2-1.基礎情報
基礎情報には、患者さんの生活像や病歴、診察所見、検査データを記載します。診断や治療方針は、基礎情報をもとにさまざまな情報を加味して決定されるため、基礎情報は最も重要な材料となります。そのため、基礎情報の内容は明確で信頼できる確実なものでなければなりません。
患者さん本人だけでなく、家族や医師、看護師、ケアマネジャーなどの医療関連職種から確実な情報を得ることが大切です。
2-2.問題リスト
POMRにおける問題リストとは、病歴や患者さんの訴え、診察所見、検査データから得られた所見で、患者さん自身や医療従事者が異常と見抜く事柄をリスト化したものです。
病名や症状、所見や徴候、社会的・精神的な問題などをピックアップしてナンバリングします。
2-3.初期計画
初期計画では、問題リストに対して以下のような計画を立てます。
2.治療上の計画
3.患者さんや家族への教育的計画
診断上または患者さんのケアに必要な計画では、検査データや基礎データを集めたり、病気や問題の経過状況を判断したりするための計画を作成します。
2-4.経過記録
経過記録では、患者さんの問題の経過状況を、以下の方法で診療記録に記載します。
● 経過一覧表
いずれもSOAPを基本として記録を残します。叙述的経過ノートは、SOAPの4項目を整理して記載します。経過一覧表は、SOAP形式と呼ばれるもので、4項目それぞれを端的に記載し、一目で内容が把握できるように作成する方法です。現在における薬局薬剤師や病院薬剤師の記録方法としては、経過一覧表が一般的でしょう。
2-5.退院時要約または最終的経過ノート
退院時要約または最終的経過ノートは、患者さんの担当医の変更や転院、退院などで、引き継ぎが必要になる場合に、以下の内容について記載します。
● O:病歴や診察所見、検査データの中から、将来的に分析や評価が必要と考えられるものを中心に客観的な情報を記載
● A:今後の経過の見通しや治療の指針となる目標、専門家のアドバイスを要請するタイミングなどの意見、未解決の問題について記載
ここで重要なポイントは、未解決の課題を中心に記述することです。解決済みの課題については、簡単に記載することが求められます。

3.POMRの監査と修正
POMRを監査することで、POMRが徹底して分析され、信頼性や能率性があるかを判断できます。POMRの監査では、以下の点をチェックします。
2.PORMの4項目について、徹底して信頼のおけるように能率的にされているかを監査する
3.記録内容の不足や不適切な点を確認し修正する
POMRを監査・修正することは、患者さんにより良い医療を提供するために欠かせません。医療関連業種とコミュニケーションを上手に取り、さまざまな視点から監査・修正をすることが、適正なPOMRの作成につながります。
また、POMRの作成・監査・修正をすることは、医療関係職種への教育的な要素もあります。多職種の知見を組み合わせて良質なPOMRにすることは、あらゆる視点や知識を得る機会になるため、医療関係職種のスキルアップにもつながるでしょう。
参考:日本POS医療学会「POS医療認定師」のためのワークショップ資料|日本POS医療学会
4.POSの活用例
ここでは、患者さんが風邪をひいて病院を受診した場合のPOSの活用例を紹介します。風邪症状で医療機関を受診し、処方箋を持って薬局に来局した患者さんについて考えてみましょう。
| 基礎情報 | ● 女性 60歳 ● 症状:38.0℃ 鼻水(+)咳(+)食欲低下 インフルエンザ(−) ● アレルギー歴:なし ● 副作用歴:なし ● 他科受診:あり 糖尿病治療薬服用中 ● 家族歴:父が高血圧症 ● 妊娠・授乳:なし ● 運動習慣:なし 職場へ車で通勤 |
| 問題リスト | 1.シックデイに注意(糖尿病治療中) 2.処方薬による副作用の発現に注意 |
| 初期計画 | 1. シックデイに注意(糖尿病治療中) ● 糖尿病の患者さんは風邪や食欲低下によって血糖値が乱れやすくなるため、シックデイに注意 ● 水分と食事を摂るように。食欲がない場合は、医師や薬剤師に相談するよう促す 2.処方薬による副作用の発現に注意 ● 処方薬に抗ヒスタミン剤があるため、車の運転時の眠気注意 |
| 経過記録 | ● S:数日前から鼻水、咳がある。38.0℃の熱もありつらい。仕事が休めないので早く治したい。 ● O:糖尿病治療薬服用中 ● A:車の運転中の眠気、シックデイに注意 ● P:処方薬に眠気が出るものがあるので注意。できる限り車の運転を控えるように。糖尿病の治療中のため、食欲低下による低血糖が起こる可能性がある。食事や水分をしっかり摂ってシックデイの予防に努めましょう。 |
上記のようなPOMRを監査・修正して最適なPOMRを目指します。問題リストや初期計画は、作成者の知識や経験などによって異なるため、複数のスタッフと検討して最適なPOMRを作成しましょう。
ただ、実際にPOMRを作成して、監査・修正をする機会のある薬剤師は少ないかもしれません。実施する機会がなかったとしても、POSの考え方を実務に取り入れることで治療への理解が深まり、より良い医療を提供できるでしょう。患者さんの治療に携わるための知識として、POSについて学んでおくことは大切です。

5.POS医療の今後
薬剤師が服薬指導を行う上で、POSを活用することはとても大切です。①患者さんの目線に立ち、②治療での悩みや不安などをくみ取って、③専門的な視点で問題や課題を見出し、④解決策を提案することは、より良い医療へとつながります。
こういったPOSの考え方は、服薬指導の基本ともいえるのではないでしょうか。そのため、実務を積み重ねることで、POSの考え方を自然と身に付けていった薬剤師は少なくないでしょう。
これからの日本の医療は、高齢社会や労働人口の減少などによって地域包括ケアが求められます。多職種と密に情報共有をする機会が増えるため、今まで頭の中で行っていたPOSを、文章化して共有することが求められるかもしれません。医療におけるPOSについて、改めて学ぶ必要性が高まっているといえるでしょう。

薬剤師ライター。2児の母。大学卒業後、調剤薬局→病院→調剤薬局と3度の転職を経験。循環器内科・小児科・内科・糖尿病科など幅広い診療科の経験を積む。2人目を出産後、仕事と子育ての両立が難しくなったことがきっかけで、Webライターとして活動開始。転職・ビジネス・栄養・美容など幅広いジャンルの記事を執筆。趣味は家庭菜園、裁縫、BBQ、キャンプ。
あわせて読みたい記事