薬剤師外来を認知症に拡大~AD薬の投与前から介入 亀田総合病院
亀田総合病院は、早期アルツハイマー病治療薬「レケンビ」(一般名:レカネマブ)、「ケサンラ」(ドナネマブ)の登場を受け、脳神経内科で医師と薬剤師の協働による認知症特別外来を行っている。厚生労働省の最適使用推進ガイドラインに基づき、両剤の使用に際し多職種が連携した運用フローを作成し、薬剤師は投与前から投与後まで患者に介入する。同院薬剤部は昨年6月から癌領域で薬剤師外来を始めたが、認知症領域にも拡大。薬剤業務向上加算の算定を受け、鴨川市立国保病院に出向した薬剤師2人が地域医療での経験を生かして患者への支援を行っている。
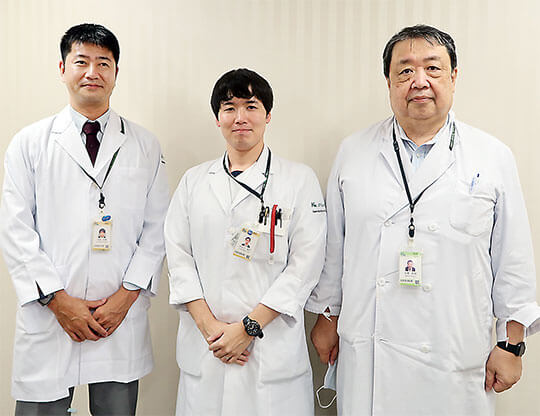
同院の脳神経内科は、毎週水曜日午後にレケンビとケサンラの投与患者を診察する認知症特別外来を実施している。運用フローでは医師や薬剤師、看護師、検査技師の多職種が関与してチームで治療を行う仕組みを整備した。
運用フローでは、投与の6週以上前に一般外来で該当患者を選定し、認知機能検査、アミロイドPET検査を経て初回投与へと進む。薬剤師は初回投与前に両剤の副作用であるARIA(アミロイド関連画像異常)の説明や発熱などの症状が現れるインフュージョンリアクション予防目的で処方される解熱鎮痛薬「カロナール」を交付する。検査技師が担当するアミロイドPET検査の調整も行う。2回目投与以降は投与後に患者への指導を行う。
10月20日時点での投与実績は6例。現段階ではARIAの発現は見られていないという。
両剤の投与で最も負担が大きい工程は投与患者の選定だ。アルツハイマー病の進行抑制という薬剤の有効性が患者には分かりづらく、副作用については脳内出血などを引き起こすARIAの不安がある。治療を受けるかどうかを決める患者の意思決定を支援するためには、患者への丁寧な説明が必要になる。
亀田脳神経センター脳神経内科の安藤哲朗部長(写真右)は、医師の立場から「ケサンラ、レケンビは良くなる薬ではなく、投与した患者は少しずつ悪くなっていく。治療には患者の通院負担や経済的な負担を考慮する必要があり、(投与期間である)1年半投与した場合の半年間の進行抑制効果をどう考えるか。患者のインフォームドコンセントには1時間を要している」と述べ、患者への説明に心を砕く。
薬剤師も医師と患者が対話する場に同席する。認知症外来を担当するのは出向を経験した2人の薬剤師である。宇田川雄也氏(写真中央)は、脳神経内科の病棟薬剤師として脳梗塞や脳出血、パーキンソン病患者のADL(日常生活動作)の低下を見てきた。そこで指導した入院患者の1人とは、出向した鴨川市立国保病院で在宅医療を経験した際に、予期せず対面することになった。病状は入院時からさらに進行しており、ADLが低下した患者が薬を正しく服用する難しさを痛感した。
宇田川氏は「入院時の服薬指導では理解力があった患者さんが、自宅に行くと服薬できておらずショックを受けた」と話す。出向時の経験から「薬剤師外来でも、患者さんの生活に寄り添った薬剤指導が必要と実感した。レケンビ、ケサンラを服用する患者さんにもきちんと内服できるのか、家族の方がどのように関わって内服の調整をしているのか気にして話をするようにしている」と語る。
今後、同院では同居する家族がアルツハイマー病患者の病状に変化がないかを確認可能な評価法の開発を検討している。同院薬剤部も評価法の開発に関与し、レケンビやケサンラの有効性評価法の確立に貢献したい考えである。
🔽 「レケンビ」(レカネマブ)について解説した記事はこちら
出典:薬事日報













薬+読 編集部からのコメント
千葉県鴨川市にある亀田総合病院では、早期アルツハイマー病治療薬「レケンビ」(一般名:レカネマブ)、「ケサンラ」(ドナネマブ)の登場を受け、脳神経内科で医師と薬剤師の協働による認知症特別外来を実施。厚生労働省の最適使用推進ガイドラインに基づき、両剤の使用に際し多職種が連携した運用フローを作成し、薬剤師は投与前から投与後まで患者に介入します。