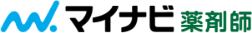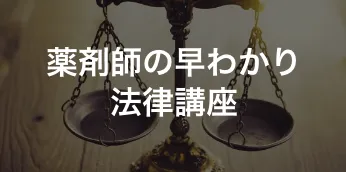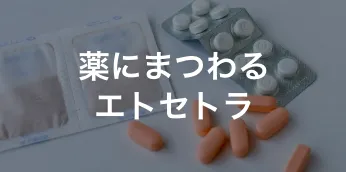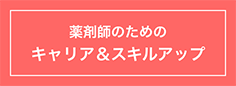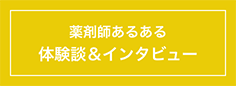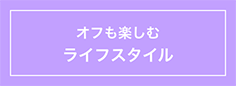知れば知るほど奥が深い漢方の世界。患者さんへのアドバイスに、将来の転職に、漢方の知識やスキルは役立つはず。薬剤師として今後生き残っていくためにも、漢方の学びは強みに。中医学の基本から身近な漢方の話まで、薬剤師・国際中医師の中垣亜希子先生が解説。
第61回 補薬の王様! 薬用人参の効能と用い方
漢方や中医学を知らない人でも一度は聞いたことがある「薬用人参(やくようにんじん)」。代表的な補気薬(=気を補う薬)のひとつで、前回ご紹介した“飲む点滴”と呼ばれる「生脈散」にも配合されています。今回は、「薬用人参」についてお話ししたいと思います。
目次
1.薬用人参とは
中医学では単に「人参(にんじん)」と言うことが多いこの生薬は、日本では、「薬用人参」「朝鮮人参」「高麗人参」、「御種人参(おたねにんじん)」など、いろいろな呼ばれ方をしています(以下、「人参」と書きます)。スーパーで売られている野菜のニンジン(キャロット)とは全く別物ですので、ご注意を。

「○○人参」という名前の物は他にも沢山あります。たとえば、シベリア人参(五加参、エゾウコギ)、竹節人参(ちくせつにんじん、とちばにんじん)、西洋人参(アメリカ人参)、田七人参(三七人参、田三七)などです。これらは、原材料となる植物(基原植物と言います)が違うので、四気五味・帰経・効能が異なります。
2.人参の効能効果
中医学の書籍を紐解くと、人参は補薬の中でも「補気薬(ほきやく)」に分類され、主に、「慢性の虚弱症と急性ショック」に用いられます。

効能の欄には、「補気固脱」とか「生津止渇」といった、四字熟語のような文字が並んでいます。一瞬ギョッとするかもしれませんが、漢字の意味と効能が端的に結びついており、イメージを掴むのにとても役立ちます。
人参(野山人参、吉林参、朝鮮参、高麗参、紅参、白参、鬚参など)
【基原】
ウコギ科Araliaceaeのオタネニンジン Panax ginseng C.A.MEYERの根。加工調整法の違いにより種々の異なった生薬名を有する。
※以上、『中医臨床のための中薬学』(医歯薬出版株式会社)より
【性味】
甘・微苦、微温
【帰経】
脾・肺経
【効能】
大補元気(だいほげんき)、補脾益肺(ほひえきはい)、生津止渇(しょうしんしかつ)、安神増智(あんしんえきち)
※以上、『中薬学』(上海科学技術出版社)より
【効能と応用】
(1)補気固脱(ほきこだつ)
大病・久病・大出血・激しい吐瀉などで元気が虚衰して生じるショック状態で脈が微を呈するときに、単味を大量に濃煎して服用する。
方剤例)独参湯(どくじんとう)
(2)補脾気(ほひき)
・脾気虚による元気がない・疲れやすい・食欲不振・四肢無力・泥状~水様便などの症候に、白朮(びゃくじゅつ)・茯苓(ぶくりょう)・炙甘草(しゃかんぞう)などと用いる。
方剤例)四君子湯(しくんしとう)・参苓白朮散(じんりょうびゃくじゅつさん)
・気虚下陥による内臓下垂・子宮下垂・脱肛・慢性の下痢などの症候に、黄耆(おうぎ)・柴胡(さいこ)・升麻(しょうま)などと使用する。
方剤例)補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
(3)益肺気(えきはいき)
肺気虚による呼吸困難・咳嗽・息切れ(動くと増悪する)・自汗などの症候に、蛤蚧(ごうかい)・胡桃肉(ことうにく)・五味子(ごみし)などと用いる。
方剤例)補肺湯(ほはいとう)
(4)生津止渇(しょうしんしかつ)
・熱盛の気津両傷で高熱・口渇・多汗・元気がない・脈が大で無力などを呈するときに、石膏(せっこう)・知母(ちも)などと用いる。
方剤例)白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)
・気津両傷による元気がない・息切れ・口渇・皮膚の乾燥・脈が細で無力などの症候に、麦門冬(ばくもんどう)・五味子(ごみし)などと用いる。
方剤例)生脈散(しょうみゃくさん)・炙甘草湯(しゃかんぞうとう)・清暑益気湯(せいしょえっきとう)(中略)
(5)安神益智(あんしんえきち)
気血不足による心神不安の不眠・動悸・健忘・不安感などの症候に、竜眼肉(りゅうがんにく)・茯苓(ぶくりょう)・遠志(おんじ)などと使用する。
方剤例)帰脾湯(きひとう)
(6)その他
血虚に対して補血薬と用いて益気補血し、陽虚に対し補陽薬と使用して益気壮陽し、補血・壮陽の効果を高める。
正虚の表証や裏実正虚に、解表薬や攻裏薬とともに少量を使用して、扶正祛邪する。(中略)
【使用上の注意】
(1)一般に補剤には量を少なく、救急用には大量に用いる。(中略)
(3)大出血のショックなどに救急的に使用するが、抵抗力を増して生命を救うのが目的であり、止血の手段であると考えてはならない。危急状態を乗りきったなら、出血の根本治療に切りかえるべきである。(中略)
※以上、『中医臨床のための中薬学』(医歯薬出版株式会社)より
実証・熱証・正気が虚していないものには禁忌。人参をお茶や大根と一緒に使用すると効果が落ちる。
※上記は『中薬学』(上海科学技術出版社)より抜粋し、筆者が和訳したもの
3.加工方法などによる効能・特徴の違い
人参は加工方法などによって、効能もやや異なります。カッコ内は、別名です。
| 種類 | 加工方法と作用 | 生晒参(人参) | 日光に晒して乾燥させたもの。 |
|---|---|
| 糖参(白参・白糖参) | 氷砂糖汁に漬けたのち、日光に晒して乾燥させたもの。表面は黄白色。【人参の作用+滋陰作用】 | 紅参 | 蒸したのち、日光に晒して乾燥させたもの。蒸すことで温熱性が強まる。表面は赤褐色。【人参の作用+補陽作用】 | 野山人参(野山参) | 野生品。非常に貴重。補益力(補うチカラ)に優れる。 | 園参(養参) | 人工栽培品。野生品に比べて効能は劣るが、現在用いられているものはほとんどが園参である。遼寧・吉林で主に栽培される。 吉林省で作られた人参を、「吉林参」と呼ぶなど、「産地名+省略した生薬名」で生薬を呼ぶことがよくあります。 |
参鬚(人参鬚・参鬚尖・鬚参) | 鬚根や加工の過程で出るクズ品。補う作用が弱く劣る。 |
4.人参の用い方
人参は「気虚証」を中心とした虚証に用いられます。人参はとても温かく(温性)、補う作用が非常に強い生薬です。したがって、用いる対象の状態や体質を選びます。人参は補うチカラが強い分、不必要に使用したときの害があらわれやすかったり強かったりします。
虚証がないとき、つまり、「正気(せいき:気血陰陽)」の不足がない状態のときには人参を用いません。また、「実証(じつしょう)」といってなんらかの滞りや邪気がある状態にも基本的には用いません。虚証・虚実について詳しく知りたい方は「日本漢方と中医学で異なる『虚実』の考え方」をご参照ください。
これは人参に限らず補薬全般に言えることですが、実証に補薬を用いるとかえって病状を悪化させてしまいます。ただし、邪がある(実証)が正気は不足している(虚証)ような場合は、補薬とともに祛邪薬(きょじゃやく:邪を追い出す薬)を用いて、「扶正祛邪(ふせいきょじゃ:正気を補い、邪を追い出す)」するケースもあります。

また、年が若いと人参が合わないことが多く、特に子どもへの用い方には注意が必要です。極端な例ですが、たとえば、真冬でも半袖半ズボンで頬を赤くして走り回る元気いっぱいの子供が、人参を服用するとどうなるでしょう。人参は気(熱)の塊のようものですから、気(熱)がこもってしまい、火照って顔が真っ赤になったり、鼻血が出たり、寝込んだりする可能性があります。ただし、もしこの子が大怪我をして大出血によりショック状態になった場合には、中医の救命救急では「大量の人参」を必要とします。
5.他の生薬と組み合わせて、体質に合わせる
韓国土産の「高麗人参(単品)」を服用したら火照りがひどかったけれど、人参・麦門冬・五味子の3味が配合された「生脈散」に変更したら、とても調子がいい、という話を患者さんから聞いたことがあります。
これは、人参単味(単品)を服用すると、むき出しの人参の性質そのものを身体に取り入れることになり体質に合わなかったけれども、他の生薬を組み合わせることによって体質に合わせられるようになったという例です。
上述したように、人参は温める性質が強いため、服用により熱象がひどくなる恐れがあるときには、麦門冬(ばくもんどう)・天門冬(てんもんどう)などの涼潤薬(寒涼性で潤す薬)を加えて防ぐことができます。
6.人参の代用品「党参(とうじん)」
人参は貴重で非常に高価であることから、中国では救急以外は党参を使用することが多いようです。党参は人参ほどの薬力はないため、軽症や慢性病に対して人参の代用として用いられます。

党参は平性で補う作用が穏やかなので、人参ほど厳しく体質を選ばず比較的に用いやすいです。日本ではあまり知られていませんが、その使いやすさから、中医学の専門家は好む人が多いように感じます。
人参はウコギ科、党参はキキョウ科なので全然違う植物なのですが、似たような働きをして、しかも安価なため、党参は庶民の味方的存在です。ただし、重症・いざという時の救命救急では、「大補元気・益気固脱」することができる人参の底力に頼ります。
参考文献:
・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための中薬学』医歯薬出版株式会社 2004年
・神戸中医学研究会(編著)『中医臨床のための方剤学』医歯薬出版株式会社 2004年
・中山医学院(編)、神戸中医学研究会(訳・編)『漢薬の臨床応用』医歯薬出版株式会1994年
・伊藤良・山本巖(監修)、神戸中医学研究会(編著)『中医処方解説』医歯薬出版株式会社 1996年
・凌一揆(主編)『中薬学』上海科学技術出版社 2008年
・許 済群 (編集)、 王 錦之 (編集)『方剤学』上海科学技術出版社 2014年
・惠木弘(著)、戴銘錫(著)、(株)東洋薬行(監修)『地道薬材』樹芸書房 2007年