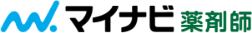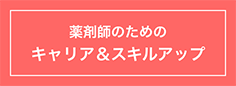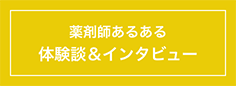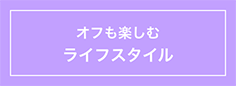映画・ドラマ

「たまには仕事に関連する映画を見てみようかな」と感じたことはありませんか? 医療や病気に関する映画・ドラマ作品は数多くありますが、いざとなるとどんな作品を見ればいいのか、迷ってしまう人もいるのでは。このコラムでは看護師ライターの坂口千絵さんが、「医療者」としての目線で映画・ドラマをご紹介します。

vol.1「ダラス・バイヤーズクラブ」(2013年・アメリカ)
【あらすじ・作品紹介】
ロン・ウッドルーフは賭博と酒と女の日々を送るデタラメな男。ある日突然、「あなたはHIV陽性で、残された時間は30日」と宣告される。が、落ち込むどころか特効薬を求めて東奔西走。ある時は神父になりすまし、ある時はパイロット、ある時はビジネスマンルックで世界中を飛び回り、最新薬を集める。薬を国内に持ち込んだ彼は、患者たちにさばき始めるが、ゲイ・コミュニティーに嫌悪感を持つロンが販路を広げるのは難しかった。そこで美しいトランスジェンダーのレイヨンを仲間に引き入れ、<ダラス・バイヤーズクラブ>という組織を立ち上げることで、会費制で無料で薬を配り多くの客を得て勢いづいていく。しかし、前に立ちはだかったのがAZTの投薬を推奨し始めた医師に製薬会社、そして政府だった。

はじめまして。坂口千絵です!
看護師をはじめ、カウンセリングやコーチングの資格を活かし、お悩み相談やライターなどの活動をメインに行っています。今回から、医療者の視点で映画を紹介するコラムの連載をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、今回ご紹介する『ダラス・バイヤーズクラブ』。本作は、1980年代後半にHIV陽性患者として余命宣告を受けたロン・ウッドルーフの半生を元に制作された実話です。
世界で最初にエイズ患者が発見されたのは1981年ですが、その原因ウイルスがヒト免疫不全ウイルス1型(HIV-1)であることが判明したのは1983年でした。
感染様式が明らかでなく、有効な治療法も確立されていない1980年代後半。エイズは「ゲイの病」「死に至る病」とも言われ、同性愛者や一部の薬物常用者だけが感染する病気という強い偏見や激しい差別がありました。
しかしその後の調査で男女間の性交渉や母子といった感染ルートも明らかになり、患者が急増。「このままではエイズが世界を滅ぼす」とまで言われていたことも記憶に新しいところです。
作中に出てくるAZT(アジドチミジン)は、1985年にアメリカ国立がん研究所に所属していた日本人研究者・満屋裕明氏により、抗HIV作用があることが初めて明らかになりました。
その後、1987年に世界初のHIV治療薬として正式に認可され、米国で使用が開始されたことは世界中の注目を集める大きなニュースとなっています。
ロンがエイズで余命宣告をされた当時、AZTは未承認の新薬で臨床試験が始まったばかり。副作用や耐性、適合性などに関するさまざまな問題があり、服用はおろか入手することも難しい状況でした。
しかしロンは諦めることなく、同じく当時は未承認新薬だった「ddC(抗レトロウイルス薬)」や「ペプチドT(ウイルスの侵入を阻害するHIV/AIDSの新種の治療剤)」を手に入れます。そしてその薬を自分以外の患者たちへも分け与える有料会員制の「ダラス・バイヤーズクラブ」を設立しました。
ddCは現在もAZTと同様にさまざまな薬との併用療法で使用されています。またペプチドTは細胞にウイルスが侵入するのを防ぐ効果があることから、エイズの治療薬として研究が進められています。
最初は自分が何としてでも生き延びるための策であったはずが、次第に多くのエイズ患者たちにも希望を与えていくロン。しかし彼の行為は法的に許されるものではなく、医師や製薬会社、政府の取り締まりが始まります。
本作品で私にとって印象的だったのは、余命宣告の29日後に車の中でロンが銃を握りしめ、ひとり号泣するシーンです。エイズを公表した途端、仲間から不当な扱いを受けたことへの孤独感、つきまとう死への恐怖、そして絶望……言葉では言い尽くせないさまざまな感情に、ロンが押しつぶされそうになっていることがうかがえます。
自分の死と向き合う立場に立たされた患者にとって何より必要なのは、支えてくれる周りの人たちとの交流なのではないかと思います。たとえシビアな状況であったとしても、決して諦めないロン、そしてロンを支える人たち。彼らの強さや温かさは、医療側に身をおく私たちにも希望の光をもたらしてくれます。
あわせて読みたい記事