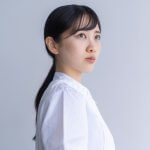薬薬連携とは、入院から退院後までの患者さんの薬物治療を安全安心に実施できるように、病院薬剤師と薬局薬剤師が情報を共有して連携することです。本記事では、薬薬連携の概要、メリット、薬薬連携の現状と課題などについてお伝えします。加えて、薬薬連携の取り組みの具体例、関連する診療報酬の加算についても解説します。

1.薬薬連携とは?
薬薬連携とは、患者さんが安全安心に薬物治療を受けられるように、病院薬剤師と薬局薬剤師が情報を共有して連携することです。患者さんの中には、入退院を繰り返し、その都度服用薬が変更となる人もいます。薬局薬剤師は、入院によってどのような治療を行い、服用薬が変更になったのかを把握することで、在宅での薬物治療について適切な指導ができます。
また、病院薬剤師は、自宅での服薬状況や他医療機関の受診の有無などを把握し、院内で情報共有することで、医師や看護師などとともに、入院に至った要因や治療方針などを検討できるでしょう。入院前後の薬物治療を情報共有するためには、薬薬連携が欠かせません。診療報酬でも薬薬連携を評価するさまざまな項目があることから、病院薬剤師と薬局薬剤師の連携が求められているといえます。
2.薬薬連携のメリット
薬薬連携のメリットの一つに、患者さんの健康管理や服薬管理を丁寧に行えることが挙げられるでしょう。治療や状態ごとに必要なサポートや検査、指導、服薬管理におけるポイントなどを共有できるため、治療方針に合わせた丁寧な服薬指導が実施できます。
また、関連する部署や医療機関、医療従事者への情報共有が容易になることも利点です。入院時の治療や在宅での治療については、薬剤管理サマリー(施設間情報連絡書)や服薬情報提供書(トレーシングレポート)などを活用して、薬剤師間で情報共有することができます。
共有した情報は、病院薬剤師が院内のスタッフへ、薬局薬剤師は在宅療養を担う医師や看護師、ケアマネジャーなどへ伝達することで、患者さんに関わるさまざまな医療・福祉関連職種と連携を図れるでしょう。
参照:地域医療連携の手引き(Ver.2.0)|日本病院薬剤師会

3.薬薬連携の現状と課題
全国での在宅患者数は、2040年以降にピークを迎えることが見込まれています。今後、多くの地域で在宅患者数が増加するとされていることから、薬薬連携の重要性はさらに高まるでしょう。
参照:新たな地域医療構想に関する検討の進め方について|厚生労働省
厚生労働省の資料「地域における薬剤師サービスの提供」に記載されている地域の基幹病院と薬局の連携状況に関する地域薬剤師会へのアンケートの結果によると、約60%の地域で、基幹病院との間で抗がん剤治療の説明会・勉強会、その他一般的な勉強会が実施され、約30%の地域で、退院時サマリーの発行や、退院時カンファレンスへの薬局の参加が行われているとされています。
同資料には、普段から勉強会などで顔の見える関係性を構築することで、連携が取りやすくなるといった薬剤師の意見も掲載されており、薬局薬剤師と病院薬剤師が接点を持つ機会を増やすことが、薬薬連携の推進につながるといえるでしょう。
また、同資料によれば、以下のように回答した医師の割合が高いという調査結果も報告されています。
● 薬局と病院薬剤師と医師が情報を共有し、連携することが必要だと思う
薬局薬剤師が在宅で治療を行う患者さんを適切にサポートするためには、病院薬剤師との連携が欠かせませんが、今後は薬剤師間だけでなく、医療機関や施設などとの連携も求められていくでしょう。
4.薬薬連携の取り組みの具体例
さまざまな医療機関で、薬薬連携の取り組みが行われています。ここでは、日本病院薬剤師会の「地域医療連携実例集(Vol.3)」をもとに、具体的な例を紹介します。
4-1.外来がん化学療法を安全に行うための体制整備
外来がん化学療法を安全に行うための体制整備には、地域医療連携と薬薬連携が不可欠です。例えば、医療機関が外来がん化学療法のレジメンを公開したり、地域の薬局やクリニックなどに向けて定期的に研修会を行ったりするなど、外来がん化学療法について積極的に情報発信することは、安全な薬物治療につながるでしょう。
薬局薬剤師は、レジメンや研修内容をもとに患者さんの服薬状況や副作用の有無などを確認し、医療機関へ情報提供することが求められます。
また、病院薬剤師が、薬局薬剤師からの情報提供や問い合わせに丁寧に対応したり、確認してほしい副作用や服用時の注意点などを共有したりすることも薬薬連携の取り組みとなるでしょう。
4-2.入院中の薬物治療や治療経過についての情報提供
薬局薬剤師が患者さんの入院時の治療経過を把握することは、服薬指導を行う上で役立ちます。例えば、入院前に服用していた薬が中止となった場合、その理由や治療経過が分かっていると、患者さんへ正確な指導ができます。患者さんと認識に相違があった場合には、問い合わせなどで確認することができ、より安全な薬物治療につながるでしょう。
そのため、病院薬剤師が、お薬手帳に入院中の薬物治療について経過を記載したり、退院時服薬指導書を作成したりすることは薬薬連携の取り組みといえます。
4-3.服薬情報提供書(トレーシングレポート)での情報共有
服薬情報提供書とは、患者さんの在宅での薬物治療について、薬局薬剤師が病院の薬剤師や医師などに向けて情報提供をする文書です。患者さんの服薬状況や管理状況、体調変化、副作用の有無などについて定期的に報告をすることで、情報共有ができます。
多くの場合、服薬情報提供書の受付は病院の薬剤部となるでしょう。薬剤部に届く情報は、病院薬剤師を通して医師や看護師などと共有され、薬物治療の評価や治療方針の検討などに活用されます。
🔽 トレーシングレポートについて解説した記事はこちら
4-4.長期入院患者さんの退院支援
長期入院を経て退院する患者さんは、療養する環境が大きく変わります。そのため、退院後の支援を担う家族や医師、薬剤師などの医療関連職種が、自宅での療養に必要な支援や薬物治療を行う際の注意点などを共有することが大切です。
自宅療養に備えて、病院薬剤師や薬局薬剤師に加え、医師や看護師、訪問医など患者さんに関わるさまざまな人が情報共有することは、薬薬連携や地域医療連携の取り組みとなります。患者さんも退院前に薬局薬剤師などの医療関連職種と顔合わせをすると、安心して自宅療養ができるでしょう。
5.診療報酬における薬薬連携の評価
薬薬連携の取り組みの中には、診療報酬で評価されるものがあります。ここでは、薬薬連携が評価される診療報酬について紹介します。
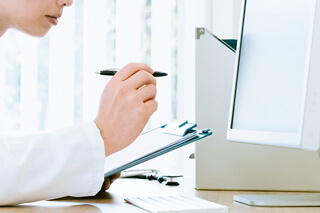
5-1.連携充実加算
連携充実加算は、医科診療報酬における外来腫瘍化学療法診療料1のイの(1)の加算です。外来がん化学療法を受ける患者さんへ情報提供や服薬指導を行うとともに、地域の薬局と連携するための体制整備をしている医療機関を評価しています。
連携充実加算を算定するためには、レジメンの公開や研修会の開催、問い合わせ対応など、地域の薬局や医療機関と連携するための体制を整える必要があります。
🔽 連携充実加算について解説した記事はこちら
5-2.退院時薬剤情報管理指導料
退院時薬剤情報管理指導料とは、医科診療報酬における医学管理料等の一つです。
入院患者さんの薬物治療についてお薬手帳に記録を残し、患者さんや家族へ必要な指導を行った場合に算定できます。
🔽 退院時薬剤情報管理指導料について解説した記事はこちら
5-3.退院時薬剤情報連携加算
退院時薬剤情報連携加算とは、医科診療報酬における退院時薬剤情報管理指導料の加算です。地域で患者さんの薬物治療を継続的にサポートすることを目的に、医療機関から薬局へ必要な情報を文書で提供することで算定できます。
お薬手帳とは別に文書で交付しなければならないため、お薬手帳に情報を貼付した場合には算定できません。
5-4.服薬情報等提供料
服薬情報等提供料とは、調剤報酬における薬学管理料の一つです。薬局薬剤師が、調剤後も継続して患者さんの服薬サポートを行い、必要に応じて医療機関などへ情報提供することで算定できます。
服薬情報等提供料には3区分あり、それぞれ算定要件が異なります。薬局薬剤師は区分ごとの違いを理解し、適切に算定することが必要です。
🔽 服薬情報等提供料について解説した記事はこちら
5-5.退院時共同指導料
退院時共同指導料とは、入院中の患者さんについて、医療機関や薬局などが連携して情報共有・指導を行うことを評価したものです。
入院していた病院や退院後の在宅療養を担う病院、薬局など多くの医療機関が関わるため、調剤報酬や医科診療報酬、歯科診療報酬で設けられています。
🔽 調剤報酬の退院時共同指導料について解説した記事はこちら
5-6.在宅移行初期管理料
在宅移行初期管理料とは、2024年度の診療報酬改定で新設された薬学管理料の一つで、在宅での療養に移行する患者さんについて、薬局薬剤師が計画的な訪問薬剤管理指導を実施する前に患者さんの自宅に訪問し、退院時の処方内容などを踏まえた薬学的管理・指導を行うことを評価したものです。
退院直後の患者さんについては、薬局薬剤師と入院していた医療機関が連携して服薬支援を実施することが望ましいとされています。そのため、退院後に在宅療養へ移行する患者さんについては薬薬連携が求められます。
🔽 在宅移行初期管理料について解説した記事はこちら

6.薬薬連携に取り組もう
日本の医療は、人口減少と高齢化によって、高齢者の医療ニーズ増加と労働力人口の減少が課題となっています。限られた入院施設を効率的に活用し、在宅で治療を行う患者さんの薬物治療を適切にサポートするためには、病院薬剤師と薬局薬剤師の密な連携が必要です。患者さんが安全安心で質の高い薬物治療を受けるためにも、薬剤師は互いに共通認識を持って患者情報を引き継ぎ、専門的な視点から医療関連職種へ伝達するといった役割を担うことが期待されています。

薬剤師ライター。2児の母。大学卒業後、調剤薬局→病院→調剤薬局と3度の転職を経験。循環器内科・小児科・内科・糖尿病科など幅広い診療科の経験を積む。2人目を出産後、仕事と子育ての両立が難しくなったことがきっかけで、Webライターとして活動開始。転職・ビジネス・栄養・美容など幅広いジャンルの記事を執筆。趣味は家庭菜園、裁縫、BBQ、キャンプ。
あわせて読みたい記事