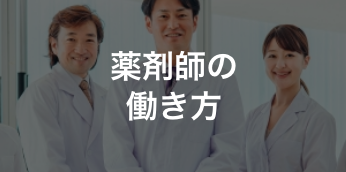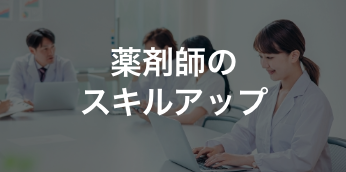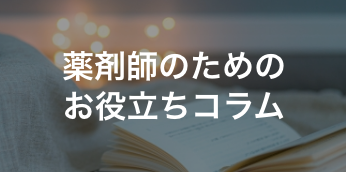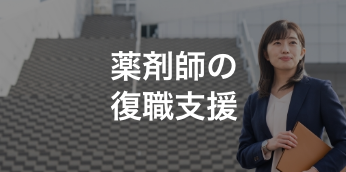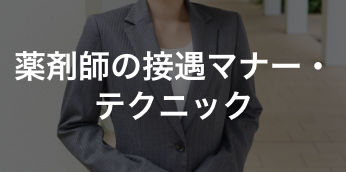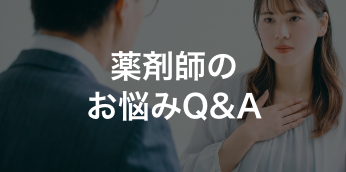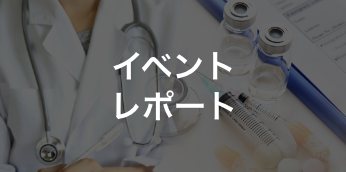さまざまな国で導入が進んでいるリフィル処方箋。日本でもたびたび検討されていましたが、2022年度診療報酬改定から導入されました。今回は、リフィル処方箋の概要やメリット・デメリットを解説するとともに、海外におけるリフィル処方箋の扱いや日本で導入する上での課題についても見ていきましょう。
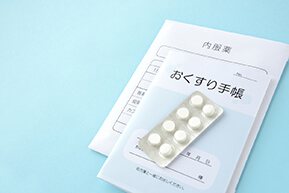
- 1.リフィル処方箋とは?
- 2.リフィル処方箋と分割調剤との違い
- 2-1.分割調剤とは
- 2-2.分割調剤にはないリフィル処方箋のメリット
- 3.リフィル処方箋にはどんなルールがある?
- ル―ル① 処方箋の様式・有効期限
- ル―ル② 投薬期間の制限
- ル―ル③ リフィル処方箋の保管義務
- ルール④ リフィル処方箋における服薬管理のポイント
- 4.リフィル処方箋導入のメリットとデメリット
- 4-1.メリット
- 4-2.デメリット
- 5.リフィル処方箋導入によって薬剤師の役割に変化が
- 6.海外におけるリフィル処方箋の導入状況
- 6-1.アメリカのリフィル制度
- 6-2.カナダのリフィル制度
- 6-3.イギリスのリフィル制度
- 7.日本におけるリフィル処方箋の導入状況
- 8.リフィル処方箋導入後の課題
- 8-1.処方箋のリフィル記載欄が十分でない
- 8-2.患者さんの次回来局日の管理が難しい
- 8-3.現状、病院や医師がリフィル処方箋を交付しやすい制度になっていない
- 8-4.薬剤師の知識・スキル向上が求められる
- 9.リフィル処方箋は今後どうなる?
- 9-1.リフィル処方箋とオンラインでの診療・服薬指導
- 9-2.電子処方箋の普及でリフィル処方箋の管理が簡略化
- 10.リフィル処方箋は薬剤師の技量が問われる
1.リフィル処方箋とは?
リフィル処方箋とは、医師が指定した一定の期間であれば、繰り返し使用できる処方箋を指します。症状が安定していることを前提として(中医協資料より)、期間中は医師の診察を受けずに処方薬を購入できるシステムで、アメリカやカナダ、イギリスなどの先進国ではすでに導入されています。

日本では、2022年度診療報酬改定からリフィル処方箋を導入しました。リフィル処方箋を利用できるのは「医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処方箋の反復利用が可能である患者」が対象で、有効期限や投薬期間など、いくつかのルールが設けられています。
2.リフィル処方箋と分割調剤との違い
リフィル処方箋と混同されやすいのが分割調剤です。ここでは、分割調剤について簡単に説明するとともに、分割調剤にはないリフィル処方箋のメリットを見ていきましょう。
2-1.分割調剤とは
分割調剤は、使用期限が短く長期保存が難しい薬剤や、ジェネリック医薬品の使用に不安を抱く患者さんに対してお試し期間を設けるために利用するものです。医師による分割指示は、1回目の調剤について指示通りに調剤を行い、2回目以降は患者さんの服薬状況などを確認し、処方医に対して情報提供を行った場合に算定できます。
► 分割調剤を行う3つのケースとは?算定方法とリフィル処方との違いを解説
2-2.分割調剤にはないリフィル処方箋のメリット
一方、リフィル処方箋は細かな制限がほとんどなく、医師がリフィル可にチェックを入れるだけで、利用条件内であれば普通の処方箋とほぼ同じように扱うことができます。分割調剤のように、交付日数や2回目以降の来局日などを考えて調剤日数を調整するなどの煩雑な作業は必要ありません。
3.リフィル処方箋にはどんなルールがある?
リフィル処方箋への対応に向けて、具体的なルールを確認しておきましょう。基本的な4つのルールを紹介します。
ル―ル① 処方箋の様式・有効期限
新たな処方箋様式では、医師により処方箋の「リフィル可」欄にレ点と使用回数を記入して提供される仕組みになっています(「個別改定項目より)。また、備考欄の下に、調剤薬局の薬剤師が記入する調剤実施回数の記録欄が追加されました。調剤薬局では、1回目、2回目に行った調剤の調剤日と次回調剤予定日を記載するとともに、調剤薬局の名称と保険薬剤師の氏名を余白または裏面に記載しなければなりません。
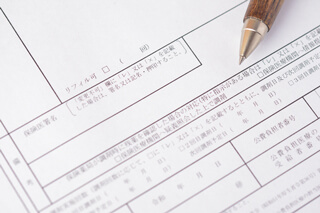
処方箋の有効期限は、1回目の調剤は従来と変わらず4日以内、2回目以降の調剤は、前回の調剤日を起点として、次回調剤予定日となる日の前後7日以内とされています。
► 処方箋とは?調剤薬局での患者さんからのよくある質問と回答集
ル―ル② 投薬期間の制限
1回あたりの投薬期間や総投薬期間については、医師の判断に任せられていますが、リフィル処方箋の使用回数は3回までとされています。また、投与量に限度が定められている医薬品や湿布薬については、リフィル処方箋による投薬はできません。例えば、新薬や向精神薬、麻薬など、14日制限や30日制限など投与期間に制限がある医薬品についてはリフィル処方の対象外となります。
ル―ル③ リフィル処方箋の保管義務
リフィル処方箋の原本の保管義務は、調剤実施回数によって異なります。最終調剤を終えたリフィル処方箋の原本は調剤薬局が保管し、調剤が終わっていないリフィル処方箋の原本は患者さんが保管、調剤薬局はリフィル処方箋の写しを保管します。
例えば、総使用回数が3回のリフィル処方箋の場合、1回目、2回目の調剤ではリフィル処方箋の写しを調剤薬局で保管し、原本は患者さんに返却します。3回目の調剤が終了したら、調剤済み処方箋として調剤薬局がリフィル処方箋の原本を保管します。
ルール④ リフィル処方箋における服薬管理のポイント
リフィル処方箋に基づく調剤を行った場合は、必要に応じて処方医へ情報提供することとされています。服薬指導で得た情報から医師の診断が必要であると判断できる場合、薬剤の交付は行わず患者さんに受診を促し、同時に処方医へ情報提供を行います。

また、リフィル処方箋は継続的な薬学的管理指導を行う必要があるため、なるべく同じ調剤薬局を利用するよう患者さんに説明する必要があります。次回調剤予定日に患者さんが来局しない場合は電話などで確認を取り、他薬局で調剤を受ける予定であれば、その調剤薬局へ情報提供を行うこととされています。
4.リフィル処方箋導入のメリットとデメリット
リフィル処方箋は、医療費の削減や医師・患者さんの負担軽減といった利点があります。リフィル処方箋の導入がもたらすメリットとデメリットを見ていきましょう。
4-1.メリット
リフィル処方箋の導入は、患者さんや医師、薬剤師にメリットがあります。
例えば、対象となる患者さんは、病院へ行く労力や時間の負担が軽減します。患者さんの中には、診察なしで薬だけを入手したいと考える人もいますが、医師は体調の変化などを確認してからでないと処方箋を交付できません。その点、リフィル処方箋になれば、病院での診察やそのための順番待ちをすることなく、薬局でスムーズに薬を受け取ることができるのがメリットです。
・医師の負担軽減
医療提供側のメリットとしては、医師は、状態が安定していない患者さんの治療に集中しやすくなり、 医療の質の向上につながるでしょう。リフィル処方箋を交付することで、状態の安定した患者さんの受診が減ります。その分、早急な診療が必要な患者さんを優先して診察することができます。時間にも余裕ができるため、より丁寧な診察が可能になるだけでなく、医師不足に悩む病院にとってもメリットがあるでしょう。
・より丁寧な服薬管理の実現
リフィル処方箋は定期的に薬剤師が介入するため、安全性の向上や残薬の削減が望めます。例えば、今まで90日分で処方されていた薬剤が30日分3回などで処方されると、定期的に薬剤師による体調や残薬のチェックが可能となります。長期処方よりも丁寧な服薬サポートができるのが利点です。
・医療費削減が期待される
リフィル処方箋は、患者さんの受診回数が少なくなり、病院でかかる再診料費などが削減できるため、医療費節減効果も期待できます。高齢化などによって日本の医療費は増加傾向にあるため、リフィル処方箋の交付は医療費削減対策として期待されています。

4-2.デメリット
続いて、リフィル処方箋を導入するデメリットについても見ていきましょう。
通常の処方箋であれば、医師と薬剤師の双方で経過観察を行うため、患者さんの状態変化を把握しやすい状況にあります。しかし、リフィル処方箋は、期間中に医師の診察がなく、薬剤師のみの経過観察となるため、状態変化に気が付きにくい点はデメリットといえるでしょう。結果として、患者さんの健康被害につながることも考えられます。
・医療機関の収入減と病院離れ
慢性疾患の患者さんであれば、再診料や処方箋料、特定疾患療養管理料などを受診ごとに算定できます。これらを算定する頻度が減るため、医療機関の収入減となるでしょう。また、月1回程度、顔を合わせることで、医師と患者さんは信頼関係を構築してきました。数カ月に1度の診察となると、医師と患者さんとの関係が希薄になり、患者さんの病院離れが起こる可能性も考えられます。
・医薬品転売のリスク
通常の処方箋を介するよりも医薬品の入手がしやすくなることから、医薬品を転売されるリスクが高まる可能性も考えられます。
► 病院に行かず「薬だけほしい」という患者さんにどう説明する?
5.リフィル処方箋導入によって薬剤師の役割に変化
リフィル処方箋での調剤では、医師に代わって薬剤師が病状や副作用など患者さんの経過観察を行う必要があります。そのため、今まで以上に高度な薬学的知識に加え、疾患の知識や判断力が求められます。さらに、患者さんとの信頼関係をしっかりと構築し、薬剤師と患者さんが何でも話せる関係をつくることにより、より詳しい情報を聞き取ることも必要です。
また、薬剤師は医師の判断が必要なケースだけでなく、気になることがあれば、医師へ報告や相談ができる体制を整えなければいけません。より丁寧に患者さんから聞き取りを行い、医師と情報共有することが、リフィル処方箋を扱う薬剤師の大きな役割といえるでしょう。
6.海外におけるリフィル処方箋の導入状況
前述したように、海外ではすでにリフィル制度を導入している国があり、それぞれ薬剤師に任されている権限やリフィル処方箋の扱いが異なります。リフィル処方箋を取り扱うにあたり、参考としてアメリカ、カナダ、イギリスの例を見てみましょう。
6-1.アメリカのリフィル制度
アメリカ(カリフォルニア州)では1951年からリフィル制度を導入しています(制度は州により異なる)。対象患者さんに規制がありませんが、対象薬剤は一部規制があります。リフィル処方箋の有効期限に法的制限がないものの、一般的に2年を超えたリフィル処方箋の調剤は行われていないようです。

アメリカでは初回調剤後、調剤薬局でリフィル処方箋を保管します。2回目以降のリフィル処方箋による調剤は調剤薬局で保管している処方箋を基に実施され、転居等で異なる調剤薬局での調剤を希望する場合は、調剤薬局間で処方箋の移動が行われます。
6-2.カナダのリフィル制度
カナダでは慢性疾患の患者さんを対象とし、リフィル処方箋の有効期限は6カ月または12カ月となっています。アメリカと同様に、リフィル処方箋の保管は調剤薬局となっています。患者さんと薬剤師が相談しながら2~3カ月分の薬を調剤することが可能です。
6-3.イギリスのリフィル制度
2002年からリフィル制度を導入したイギリスでは、定期的に同じ薬剤を使用する患者さんを対象とし、対象薬剤に一部規制があります。リフィル処方箋の有効期限は12カ月ですが、初回調剤は処方箋発行から6カ月以内、管理薬は28日以内となっています。
リピート回数はGP(General Practitioner:日本での「かかりつけ医」にあたる医師)が設定する決まりです。イギリスでは、紙の処方箋でも対応していますが、大部分が電子的に行われており、薬剤が不要になった場合は、以降の回数を電子的に取り消すことができます。
7.日本におけるリフィル処方箋の導入状況
リフィル処方箋の導入状況は、病院や診療所、薬局などによってさまざまではないでしょうか。「思っていた以上にリフィル処方箋を扱う頻度が高い」「一度もリフィル処方箋を扱ったことがない」など、薬局や薬剤師によって状況は異なるでしょう。

一般社団法人日本保険薬局協会が公開している資料「リフィル処方箋応需に関する調査報告書(2022年6月)」によると、リフィル処方箋発行予定・意向のある医療機関は約5%、リフィルの受け付け割合が1%以上の薬局は62薬局でした。また、全体として、リフィル処方箋の受け付け実績のある薬局は17.6%、受け付け割合は0.053%でした。調査対象となったのはNPhA正会員で、2022年5月24日~6月6日の回答期間のうち、103社、11,881薬局から回答を得た結果とされています。
2022年6月15日に開催された中央社会保険医療協議会によると、今後、2022年度、2023年度の2カ年にわたって、リフィル処方箋の導入状況に関する調査を行うとされています。リフィル処方箋の活用によって、どのような影響があったのか、医療機関や薬局、患者さんを対象に調査が行われます。主な調査事項は、リフィル処方箋の実施状況や患者さんへの影響、薬局におけるリフィル処方箋の対応状況などで、調査結果が待たれます。
アメリカやカナダなどでは一般的なリフィル制度ですが、日本では2022年度の診療報酬改定から始まったばかりです。リフィル処方箋の動向について様子を見ている医師もいることでしょう。今後、リフィル制度が普及して導入実績・導入事例が公開されるようになれば、リフィル処方箋を交付する医師も増えていくかもしれません。
► 服薬情報等提供料とは?1、2、3の違いや算定要件、算定例を詳しく解説
8.リフィル処方箋導入後の課題
リフィル処方箋には多くのメリットがあるものの、導入にはさまざまな課題があります。詳しく見ていきましょう。
8-1.処方箋のリフィル記載欄が十分でない
2022年8月時点で提示されている処方箋様式では、処方箋のリフィル可の欄にチェックを入れて、リフィル処方の指示をする形式となっています。チェック欄に二重線を引くことでリフィル不可の指示を入れる病院もありますが、空欄の場合、リフィル不可なのかチェック忘れなのか、判断することが難しいでしょう。

また、手書きでも記入できるため、空欄の場合、患者さんが自身で記入することも可能です。リフィル不可の欄や医師の押印または署名を記載する欄を作るといった対策が必要かもしれません。
さらに、処方箋には来局可能期間を記入する欄がなく、次回調剤予定日の前後7日間が来局可能期間であることが記載されていません。患者さんは自宅で次回来局可能期間を確認することができないため、薬剤師が口頭で指示することになっています。調剤日と次回調剤予定日を記入する欄に加えて、次回来局可能期間を記入する欄や次回調剤予定日の前後7日間といった記載があるとよいかもしれません。
8-2.患者さんの次回来局日の管理が難しい
上述したように、リフィル処方箋は、次回来局日の管理を薬剤師側に任されています。そのため、患者さんごとに次回調剤予定日と次回来局可能期間を管理し、来局されない場合は電話などで連絡をしなければなりません。数人であれば、ノートやカレンダーなどを使った管理も可能ですが、リフィル処方箋の件数が増えるほど作業が多くなるため、記載漏れ・連絡漏れなどが起こる可能性があります。状況に合わせてシステムの導入などを検討する必要があるかもしれません。
8-3.現状、病院や医師がリフィル処方箋を交付しやすい制度になっていない
2022年度の診療報酬改定では、クリニックや診療所などがリフィル処方箋を交付する金銭的なメリットはありません。前述した通り、90日分などの長期処方を30日分のリフィル処方箋にして3回反復利用をするケースであれば、医療機関の収益はほとんど変わらないでしょう。

しかし、今まで30日分の処方を毎月出していた患者さんに対して3回反復利用できるリフィル処方箋を交付すると、2回分の診察費が得られなくなります。リフィル処方箋の導入を進めていくのであれば、相応の診療点数を病院側にもつける必要があるかもしれません。
8-4.薬剤師の知識・スキル向上が求められる
リフィル処方箋を扱う上で欠かせないのが、薬剤師の知識やスキルの向上です。症状が安定している患者さんとはいえ、医師に代わって薬剤師が体調や病状のチェックを行うことになります。とはいえ、薬局内で行えることは、ヒアリングや血圧などの簡単な検査のみです。少ない情報の中で、患者さんの状態を把握し、病院への受診を促すか、このまま継続するかを判断しなければなりません。そのため、今以上に疾患についての知識やコミュニケーションスキルを高める必要があるでしょう。

リフィル処方箋は、薬剤師の責任が重くなる印象があり、プレッシャーに感じる薬剤師もいることでしょう。しかし、医療現場において薬剤師の役割が広がることは、薬剤師のイメージを変えるきっかけにもなります。リフィル処方箋が普及するとともに、薬を集めるだけと思われがちな薬剤師のイメージが変わるかもしれません。
► 薬剤師におすすめの勉強法は?ノート・本・アプリの活用から勉強時間の確保まで
9.リフィル処方箋は今後どうなる?
リフィル処方箋は今後どのように広がっていくのでしょうか。現状のシステムを踏まえて考えてみましょう。
9-1.リフィル処方箋とオンラインでの診療・服薬指導
リフィル処方箋は患者さんが病院やクリニックの受診回数を減らせるメリットがあります。しかし、薬局への来局回数は減らすことができません。そのため、今後は来局回数を減らすために、オンライン服薬指導の普及率が高まる可能性があります。オンラインで服薬指導を行い、郵送や宅配で処方薬を患者さんへ届けることで、患者さんの利便性はさらに高まるでしょう。

また、オンライン診療と組み合わせることで、患者さんは病院にも薬局にも行くことなく自宅にいながらいつもの薬を購入することができます。オンラインによる診療や服薬指導は、得られる情報が少ないといった課題があるため、全ての患者さんに行うことは難しいかもしれません。しかし、利便性という点では、今後普及する可能性は十分にあるでしょう。
► オンライン服薬指導の導入ポイントとは?メリット・デメリットも紹介
9-2.電子処方箋の普及でリフィル処方箋の管理が簡略化
リフィル処方箋は、調剤実施回数を満たすまで患者さんが保管しておかなければなりません。薬局では調剤したことを証明するために処方箋の写しを保管します。電子処方箋の運用が本格的に始まれば、リフィル処方箋はオンラインで管理できるため、患者さんにとっても、薬局にとっても利便性が高まるでしょう。
10.リフィル処方箋は薬剤師の技量が問われる
リフィル処方箋の導入によって、薬剤師の役割は大きく変わります。薬学的知識や判断力、疾患の知識に加え、さらに高いコミュニケーション能力を身に付ける必要があるでしょう。薬剤師は、高齢化社会による医師の負担を緩和して日本の医療を支えるとともに、医療費削減に貢献することが期待されています。これからは、今まで以上の高いスキルと豊富な知識、医療従事者として責任感のある薬剤師が求められます。
参考URL
■ 中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)|厚生労働省
■ 中央社会保険医療協議会 総会(第523回)議事次第|厚生労働省

執筆/秋谷侭美(あきや・ままみ)
薬剤師ライター。2児の母。大学卒業後、調剤薬局→病院→調剤薬局と3度の転職を経験。循環器内科・小児科・内科・糖尿病科など幅広い診療科の経験を積む。2人目を出産後、仕事と子育ての両立が難しくなったことがきっかけで、Webライターとして活動開始。転職・ビジネス・栄養・美容など幅広いジャンルの記事を執筆。趣味は家庭菜園、裁縫、BBQ、キャンプ。
あわせて読みたい記事