調剤報酬の退院時共同指導料は、入院患者さんが退院後も安心安全に薬物治療を継続できるよう、薬局薬剤師が医療機関の医師や看護師、薬剤師などの医療関連職種と共同して指導、説明を行うことを評価したものです。本記事では、退院時共同指導料の概要や医科診療報酬における退院時共同指導料の1と2の違い、算定要件・点数について分かりやすく解説するとともに、算定方法や算定のタイミング、算定できない事例、レセプト摘要欄への記載事項についても詳しく解説します。

1.退院時共同指導料とは?
退院時共同指導料とは、入院中の患者さんが退院後にも円滑な治療を受けられるように、入院している医療機関と在宅療養を担う医療施設、クリニック、薬局などの医療従事者が共同して説明や指導を行った場合に算定できるものです。
調剤報酬における退院時共同指導料は、退院後の訪問薬剤管理指導を担う薬局の薬剤師が、患者さんが入院している医療機関の医師や看護師、薬剤師などと共同して、在宅療養で必要な薬剤に関する説明および指導を行い、文書により情報提供した場合に算定が可能です。
薬局薬剤師は、退院時共同指導料に関わる合同カンファレンスに参加することで、入院中にどのような治療を行い、どういった経緯で服用薬を変更したかなどを把握できます。
2022年度の診療報酬改定では、退院時共同指導料の算定要件について、以下の点が変更されました。
● 退院時共同指導に参加する医療従事者
2022年度の診療報酬改定により、薬局薬剤師がビデオ通話を用いて共同指導に参加する場合の要件が緩和されました。
また、改定前の算定要件には、退院時共同指導に参加する医療機関のスタッフに病院薬剤師などが含まれていませんでしたが、改定により明記されています。
参考:令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)|厚生労働省
🔽 2022年度の調剤報酬改定について詳しく解説した記事はこちら
1-1.医科診療報酬の退院時共同指導料とは?
調剤報酬と同じく、医科診療報酬にも「退院時共同指導料」があります。
医科診療報酬における退院時共同指導料とは、退院後に在宅療養を担当する医療機関の医師や看護師、薬剤師などが、入院治療を行う医療機関の医師などと共同して、患者さんや家族などへ退院後の在宅療養で必要な説明や指導を行い、文書で情報提供した場合に算定するものです。
調剤報酬における退院時共同指導料との違いは、1・2の区分がある点や、加算が設けられている点などが挙げられます。
参考:医科診療報酬点数表に関する事項|厚生労働省
1-1-1.医科診療報酬の退院時共同指導料1と2の違い
医科診療報酬における退院時共同指導料1・2は、以下のように算定できる点数が異なります。
| 区分 | 点数 | |
|---|---|---|
| 退院時共同指導料1 | 在宅療法支援診療所 | 1500点 |
| 在宅療養支援診療所以外 | 900点 | |
| 退院時共同指導料2 | 400点 | |
また、設けられている加算などにも違いがあります。退院時共同指導料1・2の算定要件や加算の詳細については、厚生労働省のホームページなどで確認しましょう。
参考:医科診療報酬点数表に関する事項|厚生労働省
2.退院時共同指導料の算定要件と点数
調剤報酬における退院時共同指導料の算定要件と点数は、以下のように定められています。
| 点数 | 600点 |
|---|---|
| 対象患者 | 退院後に在宅での療養を行う入院患者さん |
| 算定回数 | 入院中に1回に限り算定可 ※ただし、厚生労働大臣が定める疾病等の患者さんについては、入院中2回に限り算定可 |
| 患者さんの同意 | 必要 |
| カンファレンスの実施 | ● 原則、患者さんが入院している医療機関にて対面で実施 ● 以下の要件を満たすことで、ビデオ通話による実施も可 1. 患者さんの個人情報をビデオ通話の画面上で共有する際は、患者さんの同意を得ていること 2. 医療機関の医療情報システムと共通のネットワーク上の端末でカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること |
| カンファレンスを共同して行う医療関連職種 | 薬局薬剤師と、医療機関の以下の医療関連職種 ● 医師 ● 看護師等 ● 薬剤師 ● 管理栄養師 ● 理学療法士 ● 作業療法士 ● 言語聴覚士 ● 社会福祉士 |
| 薬局薬剤師の要件 | 患者さんが指定する退院後に訪問薬剤管理指導を担う薬局の薬剤師 |
| 患者さんへの指導・説明 | ● 退院後の在宅療養で必要な薬剤に関する説明および指導 ● 文書による情報提供 ● 家族など退院後に患者さんの看護を担当する人に対して指導を行った場合でも算定可 |
| 記録 | ● 薬歴に指導内容の要点を記載 ● 提供した文書の写しを添付 |

3.退院時共同指導料の算定方法と算定のタイミング
退院時共同指導料の算定のタイミングは、指導を実施した時点とされており、処方箋の受付によって実施・算定するものではありません。
そのため、算定するためには、処方箋とは別の調剤報酬明細書(レセプト)を作成し、審査支払機関へ提出する必要があります。
また、処方箋の受付によるものではないため、退院時共同指導料の算定は受付回数に計上できません。誤って受付回数に含めてしまわないよう注意しましょう。
参考:保険調剤Q&A 令和6年版|じほう
3-1.退院時共同指導料を2回算定できるケース
退院時共同指導料の算定は、基本的に入院中に1回までとされています。しかし、以下のケースについては「別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者」にあたるため、2回まで算定が認められています。
● 在宅での療養を行っている患者さんであって、高度な指導管理を必要とするもの
また、以下を受けている状態にある患者さんで、ドレーンチューブまたは留置カテーテルの使用、もしくは、人工肛門または人工膀胱を設置している患者さんについても、退院時共同指導料を入院中に2回まで算定できます。
● 在宅血液透析指導管理
● 在宅酸素療法指導管理
● 在宅中心静脈栄養法指導管理
● 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
● 在宅人工呼吸指導管理
● 在宅麻薬等注射指導管理
● 在宅腫瘍化学療法注射指導管理
● 在宅強心剤持続投与指導管理
● 在宅自己疼痛管理指導管理
● 在宅肺高血圧症患者指導管理
● 在宅気管切開患者指導管理
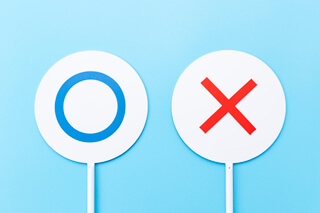
4.退院時共同指導料を算定できない事例
退院時共同指導料が算定できない事例について見ていきましょう。
4-1.患者さんが算定対象外となるケース
退院時共同指導料は退院後に在宅で療養する患者さんを対象としているため、以下の施設に入院または入所する場合は算定できません。
● 社会福祉施設
● 介護老人保健施設
● 介護老人福祉施設
なお、介護保険の適用患者さんであっても、退院後に在宅療養をする患者さんで医療保険が適用される場合には算定対象となります。
参考:保険調剤Q&A 令和6年版|じほう
4-2.算定後に死亡退院となったケース
退院時共同指導料は指導を実施した時点が算定のタイミングとなるため、指導を行い保険請求を行った後に患者さんが亡くなったケースでは、退院時共同指導料に関する保険請求を取り下げなければなりません。
参考:保険調剤Q&A 令和6年版|じほう
4-3.退院直後に合同カンファレンスを行うケース
退院後に在宅医療へ移行する場合、退院直後に患者さんの自宅で合同カンファレンスを行うケースもあるでしょう。こういったケースでは、退院時共同指導料を算定することができません。
退院時共同指導料は、入院中の患者さんに指導を行うことで算定できるものです。そのため、退院後に患者さんの自宅で合同カンファレンスを実施し、指導を行った場合については算定できないことになっています。
参考:保険調剤Q&A 令和6年版|じほう
4-4.特別調剤基本料Bを算定しているケース
特別調剤基本料Bを算定している薬局は、薬学管理料が算定できません。そのため、特別調剤基本料Bを算定する薬局の薬剤師が、退院に向けた共同カンファレンスに参加し、患者さんや家族などへ指導・説明を実施したとしても、退院時共同指導料は算定できません。
🔽 特別調剤基本料について解説した記事はこちら
5.退院時共同指導料のレセプト摘要欄への記載事項
退院時共同指導料のレセプト摘要欄には、指導年月日、共同して指導を行った患者さんが入院している医療機関の医師等の氏名、医療機関の名称、在宅医療担当医療機関の名称を記載することとされています。
| レセプト電算処理 システム用コード |
レセプト表示文言 |
|---|---|
| 850100385 | 指導年月日(退院時共同指導料); (元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
| 830100450 | 患者が入院している医療機関の医師等の氏名(退院時共同指導料); ****** |
| 830100451 | 患者さんが入院している医療機関名(退院時共同指導料); ****** |
| 830100452 | 退院後の在宅医療を担う医療機関名(退院時共同指導料); ****** |
参考:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について|厚生労働省

6.退院時共同指導料の算定はハードルが高い?
厚生労働省が公開している資料「調剤(その2)」には、薬局における退院時共同指導料の算定回数の推移についての調査結果が掲載されており、2020年度までの時点で「退院時共同指導料の算定回数は2020年度を除き増加傾向だが、多くない」としています。この調査からも、薬局薬剤師が患者さんの退院後サポートに参画する機会は少なかったことがうかがえます。
薬局薬剤師が退院時共同指導料を算定するには、定期的な来局が滞っている患者さんについて、家族や医療機関に問い合わせるといった積極的な対応が求められます。また、入院していることが判明した場合には、退院の情報を得る必要もあるでしょう。
退院時共同指導料を算定する機会を得るためには、患者さんや家族と信頼関係を築き、かかりつけ薬剤師やかかりつけ薬局など、地域の薬局としての機能を今まで以上に充実させることが求められるでしょう。
🔽 かかりつけ薬剤師の役割について詳しく解説した記事はこちら
7.患者さんの自宅療養をサポートするために
退院時共同指導料は、退院後に自宅で療養される患者さんを対象としています。患者さんが自宅で安心して治療を受けるためにも、在宅医療に関わる薬剤師が入院中の治療経過を把握することは大切です。また、さまざまな職種の視点から治療に関する情報を共有することは、よりよい医療の提供につながるでしょう。共同カンファレンスへ積極的に参加して、患者さんの薬物治療をサポートしましょう。
🔽 調剤報酬に関連する記事はこちら

薬剤師ライター。2児の母。大学卒業後、調剤薬局→病院→調剤薬局と3度の転職を経験。循環器内科・小児科・内科・糖尿病科など幅広い診療科の経験を積む。2人目を出産後、仕事と子育ての両立が難しくなったことがきっかけで、Webライターとして活動開始。転職・ビジネス・栄養・美容など幅広いジャンルの記事を執筆。趣味は家庭菜園、裁縫、BBQ、キャンプ。
あわせて読みたい記事


















































































